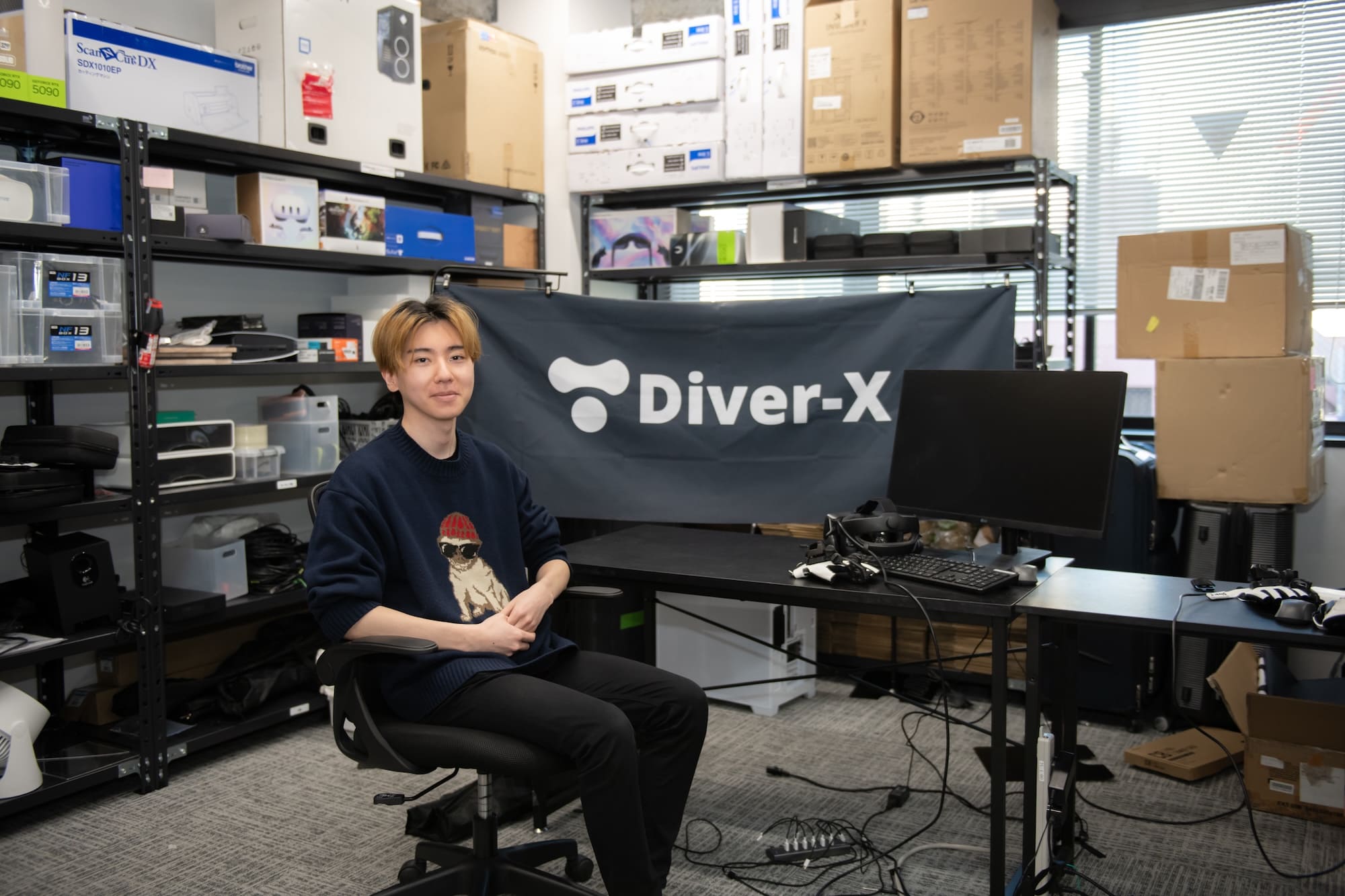交流より衝突、コミュニティよりコ・ラーニング。都市の可能性からみる「現代のほどよい距離感」とは

文:葛原 信太郎 写真:須古 恵
自己変革を起こすためにはコミュニティよりコ・ラーニング、交流より衝突。MEZZANINE編集長・吹田良平さんに訊く、世界の都市から見えてきた創造性を生む距離感とは。
現代の社会における「ほどよい距離感」とはなんだろうか。
デジタルテクノロジーの進化により物理的に離れた人同士が気軽にコミュニケーションできるようになる一方、リアルな場での対話の大切さも見直されている。スマートフォンやスマートスピーカーに喋りかけることで情報を得たり、ロボットを愛でたりすることが人々に受け入れられ、人と物の距離感も縮まった。「人と人」や「人と物」などさまざまな距離感のこれからについて考えていきたい。
今回お話を聞いたのは「都市の進化に向けた世界中のアイディアとチャレンジ」をテーマにした書籍『MEZZANINE』編集長の吹田良平さん。世界中の都市を回りながら、そこに住む人々や企業を見てきた吹田さんは、都市における人と人との距離感をどのように考えているのだろうか。

多様な人々が相互作用しあい、連携進化できるのが都市
――まずは吹田さんがなぜ都市にフォーカスするのか教えてください。
ちょっと大げさですが「人間の可能性」について興味があるからです。東京大学東洋文化研究所教授の中島隆博先生によれば「人間の可能性とは変化するということ」である。つまり、常に変わり続ける、成長することだとおっしゃっています。その意味で、人間は英語で"Human Being"ですが、むしろ"Human Becoming"の方が適切ではないかと続きます。
さらにおもしろいのは「人間の変化にとって、他人との関与が不可欠である」という点です。よって、先生は、Human Becomingをさらに発展させて、Human Co-becomingというコンセプトを披露します。ここからは僕の解釈ですが、都市とは、多様な人が存在し相互に影響し合う触媒のようなものである。その都市において人々は相互作用しあい、連携進化していく。それが都市の可能性であり、同時に人間のケイパビリティそのものである。だからおもしろいんです。

――ここでいう「都市」の定義とはなんでしょう。
都市の定義はさまざまで、いくつかの分野や学問毎に定義されています。
地方自治法で言えば「人口が5万人以上であること、地方自治の中心市街地に6割以上が住んでいること、地方自治体の6割以上が三次産業の従事者あるいはその家族であること」。都市経済学では「人口の集積。物やサービスの交易が起こっていること」。都市社会学であれば「様々な消費の機会が存在すること。多種多様な使い方ができる施設の存在。様々な個性を持った異質な人間、組織・企業があること」。さらに、都市計画の世界では「他の地域に比べて高い密集性があること。相対的に高い人口密度のあるところ。高密な都市利用がされていること」とされています。
僕の興味はもっぱらこっちの方なのですが、作家の曽野綾子さんは、かつて都市についてこう書いています。「過去になかったものを遠慮なく存分に作り出していく、それが都市に許された使命である」と。さらにこう続けます。「都会では生きているだけで、教養を得ることができる」、その代わり「地方では哲学を得ることができる」と。
自分なりの都市の定義を言うならば「多種多様な人間が集まって、絶えず接触しながら情報やアイディアの交換を行なう場所であり、そこにおいて新しい技術や独創的なサービスが生まれ、持続的な成長を果たす場」です。
「コミュニティ」から抜け出すことで都市の可能性を使い切る
――つまり人と人との距離感や関係性が、都市を定義する要素である、と。
はい。生物学の世界でも比喩的な現象があります。細胞を培養する時、細胞をただ広い場所に置いておいても相互作用は起きない。シャーレの中で高密度な状況を作ってやる必要があります。そうすると細胞同士が増殖してコロニーを形成するそうです。人間社会で言えば、コミュニティですね。そして飽和状態となり増殖が終わると、やがてシャーレ内の細胞は衰退する。
つまり、一定の密度にならなければ、相互作用は起こらない。密度を高めてやれば相互作用は加速する。そして、相互作用が終わればその細菌環は消滅する。どうですか、都市のアナロジーそのものですよね。だからバイオミミクリなんです。
しかし、日本において都市に住む人々が、そうした都市の可能性を生かし切れているかというと、疑問もあります。

――都市に住む人のどのような姿をみて、そう感じられたのでしょうか?
内には優しく外には厳しい、村社会的な狭く閉じたコミュニティ感覚が都市に住む人にも染み付いてしまっているように見えます。知っている者同士では必要以上に気を使う一方、一旦その集団から外に出た途端、例えば駅で人にぶつかっても謝らない。店に入ると、「俺は客だぞ」とばかりに「おもてなし」という名の過剰サービスを要求する。人間、「受け身」になったら、それで終わりです。相互作用や化学反応は起こりません。自分のコミュニティの外にいる他人と関わり合うための術がまだ身についていないのではないでしょうか。
古くからあるいわゆる農村的コミュニティは、地縁や血縁などで人がつながっていましたよね。近年、頻繁に使われるコミュニティや交流の根底にも、同じ関心を持つ人、共通点を持つ人同士でつながり、連帯を深めたいという欲求が強いように思います。それでは都市にいる恩恵を生かしているとは言えない。「互いにわかりあえる人たち」の集団に閉じているのはもったいないんじゃないか、と思います。
もちろん連帯を深めるタイプのコミュニティにも役割はあるでしょう。しかし、自己変革を起こしていくためには、狭く閉じた「お約束のコミュニティ」を超えて、フロンティアに出ていかないといけません。インターネットにおけるフィルターバブルの問題と同じように、自分と同じような、想像の範囲内に収まる考え方にしか出会えないからです。それでは、Human Co-becomingを果たせません。
『WIRED UK』創刊編集長デイビッド・ローワンも「自分がやっていないことをやっている人と話すこと」の重要性を新著に記しています。
コミュニティよりコ・ラーニング、交流より衝突といったキーワードが、都市の利点を使い切るために重要だと思います。言うは易しなんですが、これを現実社会で実現するには「シティ(市)」よりもひとまわり小さい範囲である「ネイバーフッド(界隈)」という距離感が適しています。次号のMEZZANINEでは、ネイバーフッドにフォーカスする予定です。言うなれば「クリエイティブシティ」ではなく「クリエイティブネイバーフッド」です。
「会える距離」が創造性を生む
――「シティ」だと大きすぎるのですか。
そうですね。必要に応じてすぐに会いに行けるくらいの「ネイバーフッド」な距離感が知識の衝突には適していると思います。これも有名な調査結果ですが、研究論文の共同執筆においてチーム内メンバーの物理的な距離が近いチームと遠距離チームとを比較した場合、近い範囲にいる者同士のチームのほうが優れた論文を書き上げるそうです。内容の優越は引用された数で測るんだそうです。
2005年に出版された『フラット化する世界』の著者トーマス・フリードマンは「インターネットを始めとするテクノロジーの進化によって、物理的な距離は意味を失くす」と主張しました。しかしそれから15年経った今も、現実はそうなっていない。未だに世界中の投資マネーや優秀なエンジニアはシリコンバレーや北京やニューヨークなど決まった場所に集積しています。つまり、インターネットは物理的な距離を壊してはいないのです。
もう一つ、ネイバーフッドにこだわる理由は、ワークとライフを融合させた職住近接型の生き方に適しているからです。
――リクルートでも、2020年のトレンド予測の中で、住まい分野のトレンドとして「職住融合」を挙げています。自宅の間取りの一部をオフィス仕様にする「家なかオフィス化」や、街の中のコワーキングで仕事する「街なかオフィス化」が生まれ、さらには職場に縛られない「街選びの自由化」が進む兆しもあるのではないかと。

同感です。個人が働く場所は必ずしもオフィスやオフィス街でなくてもよいでしょう。最近、オフィスデザインの世界では「ABW(Activity Based Workplace)」がキーワードですね。これは生産性を基準にオフィス環境を再編しようとする考え方。でも本来はオフィス内をフリーアドレスにするといった自社の建物内に閉じた話ではありません。生産性が上がるのであれば、働く場所はオフィスから外に出て、自宅でも、カフェでも、コワーキングスペースでも良いというのが本来のABWです。
つまり、オフィスと家、オフィス街と住宅街、就労時間とプライベート時間といった区分が溶けてなくなっていく。2008年の金融危機からわずか10年間で世界第2位の起業都市に成長したニューヨークのイノベーションディストリクト、ブルックリンの調査では、そこに所在する新興企業の7割は「従業員の大半がブルックリンに住んでいる」そうです。さらに、3分の1の企業が、従業員全員がブルックリン在住。多くの人が、働く街に住んでいるのです。
市民もビジネスパーソンもコラボレーションするクリエイティブネイバーフッド
――世界の都市を見てきた吹田さんが「ここはクリエイティブネイバーフッドだな」と感じたエリアはありましたか?
実は、ここぞという場所はまだ見つけていません。しかし、ヒントはいくつか見てきました。例えば『MEZZANINE VOL.2』に載せたアメリカのオレゴン州、ポートランドの話です。

コロラド州で会社勤めをしていたとある男性は、60歳を機に会社をリタイア。終の棲家を探して北米のたくさんの都市を調べた末、最終的にポートランドを選びました。理由は不動産や物価が安かったこと。車が無くても住める街だから。そしてビールがうまいから(笑)。ひっそりと暮らそうと越してきた彼でしたが、ほどなく自身が旗振り役になりイベントを立ち上げたそうです。
なぜならば、氏曰く、「自分がしたいことがあるなら、それを実行に移さないと、この街では奇異な目でみられる」と言うのです。周りの人たちも「失敗するのは当然。まずはやってみる」というマインドセットがここではコモンセンスになっているようなのです。だから、年齢を気にせず、自分も挑戦したくなったと教えてくれました。もちろん、ビールを堪能しながらね(笑)。
同じく、ポートランドのハンドメイド製品のメイカーさんの話も興味深い。「僕らはよくライバル企業の工房を互いに行き来し合う。相手が新しい機材を導入したら、すぐに試させてもらうそうです」。なぜなら、「僕たちはお互いにゼロサムで物事を考えないから。相手との競争にかける時間があったら、互いに共創し合って相互にスキルアップした方がクールだろ」と。
社会学者のチャールズ・ヘイング教授はこう言っています。「ポートランドでは、起業家たちが率先して、自分の技術とリソースを潜在的な競争相手と共有し合っている。その方が健全な競合が生まれるから。やがて、そうしたビジネスパーソンやスタートアップの考え方、姿勢は一般市民にも影響を及ぼす」
さらに続けて「この街には、何かをしたい人を支える文化がある。それに引かれて何かをしたい人が外から集まってくる」。その結果、「大量生産時代に分離された仕事と生活が、創造的社会では再統合される。生活、仕事、社交の境界線が楽しくぼやける地域社会が生まれている」というのです。まるでウィリアム・モリスが夢見た世界ですね。
私の感じるあの地の魅力とは、コミュニティ論でも、まちづくり論でも一切ない。第一、僕は社会関係資本より創造資本、関係人口より共創人口の方が大事だと考えてる人間です。社交的な人より自分の世界に没頭する人を信じます。ああ、言っちゃった(笑)。僕が学んだのは、「挑戦する精神を持ち続けるということ、挑戦する人を排除せずに受け入れるということ」。さらに、「街自体が自ら率先して実験的なことに挑戦すること、街が挑戦する人を具体的に応援すること」。そうした態度が街中にコモンセンスのように広がっている。だから、パーパスシティであり、エイブルシティであり、オポチュニティシティであり、挑戦特区なんです。これこそが僕がイメージするクリエイティブネイバーフッドです。この2月に募集を締め切った、政府が推進する「スタートアップ拠点都市構想」も、こういうコモンセンスの街を最初に作ることから考えないと、そのそもスタートアップは集まらないのではないでしょうか。

――ポートランドで根付く、人と人の距離感や、コラボレーションへのモチベーションは、他の都市にも再現可能でしょうか?
スマートシティが次の段階に行けば、その機能を果たせるかもしれません。現段階のスマートシティは、街なかにカメラやセンサーをくまなく設置し、集めたビックデータをAIで解析してフィードバックすることで、街を合理的に運営する、という考えですよね。
テクノロジーにより人間がやっていた仕事をAIやロボットが代替してくれても、余った時間を無為に過ごしていては意味がない。僕はそれをスマートな都市とは決して言いたくはありません。
スマートシティにおける、ビックデータやAIの次の段階は、テクノロジーによる他人との共創や衝突のためのサポートではないでしょうか。「こういう関心を持っているなら、こっちの分野のこの人に会いなさい」と、マルチディシプリンでサジェッションしてくれるような。僕も既存の街をクリエイティブネイバーフッドに変えるためのアプリを今開発しています。街に人を呼ぶための情報を伝えるのではなく、街にすでにいる人の行動を変えていくようなアプリです。
スマートシティが目指すべきは、機械による利便の提供ではなく、機械によって人々の交流機会の敷居が下がり、自己変容していくための行動を促すこと。つまり仕事を作ること。それこそが本当の意味でのスマート(賢い)シティと呼べるし、それを、今のデータ駆動型スマートシティとは区別して、クリエイティブネイバーフッドと呼んでいるのです。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 吹田良平(すいた・りょうへい)
-
1963 年生まれ。(株)アーキネティクス代表取締役。MEZZANINE編集長。大学卒業後、浜野総合研究所を経て、2003年、都市を対象にプレイスメイキングとプリントメイキングを行うアーキネティクスを設立。都市開発、商業開発等の構想策定を中心に関連する内容の出版物編集・制作を行う。主な実績に渋谷QFRONT、「北仲BRICK & WHITE experience」編集制作、『日本ショッピングセンター ハンドブック』共著、『グリーンネイバーフッド』自著等がある。2017年より新雑誌『MEZZANINE』を創刊。