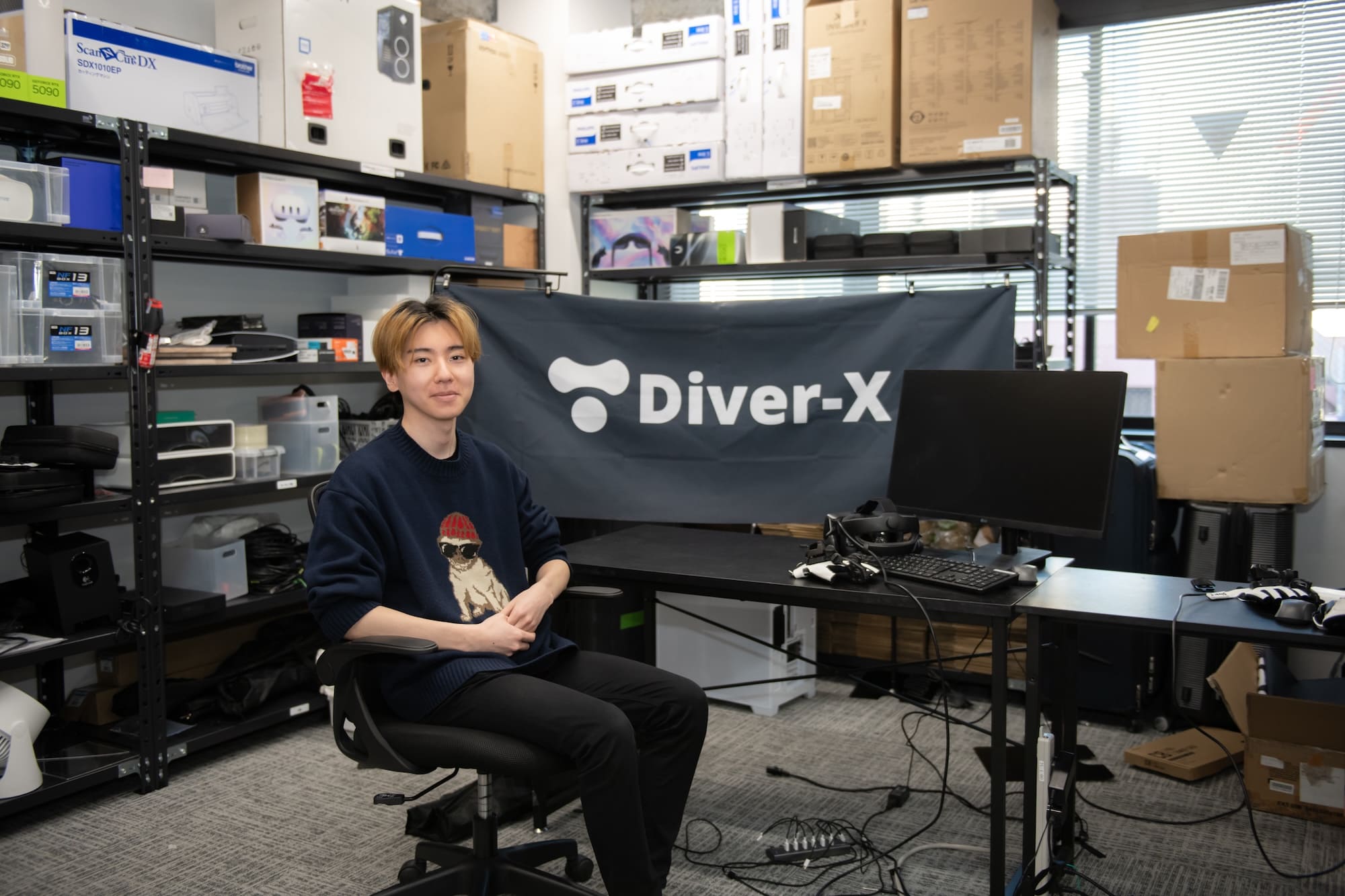クリエイティブチーム「goyemon」に学ぶ、失敗を恐れないチャレンジングなチームの作り方

“日本の伝統×最新技術”で革新的プロダクトを発表するブランド「goyemon」。創業メンバー大西 藍さん・武内賢太さんの道のりから、現代らしい挑戦の秘訣を学ぶ
自らの興味や好奇心を原動力に人生を突き進み社会で活躍をしている人々は、どのような出来事に影響を受け、どのような価値観を持っているのだろうか。今回登場するのは、株式会社goyemon CEOの大西 藍(おおにし・あい)さんと、COOの武内賢太(たけうち・けんた)さん。1993年生まれのふたりは、社会人3年目だった24歳のときにプロダクトデザインユニットとして「goyemon(ごゑもん)」を立ち上げ、日本の伝統的な履物である雪駄にスニーカーの機能性を加えた『unda-雲駄-』を発表。その後も電子レンジ対応の切子グラス『Fuwan-浮碗-』や、ソーラーLEDの提灯『ANCOH-庵光-』など、日本の伝統文化に最新技術を組み合わせた現代のライフスタイルに馴染むプロダクトへと昇華させているのが特徴だ。
大手ブランドとのコラボレーションも続々と実現し、2025年大阪・関西万博日本館のユニフォームにも起用されるなど、世間からの注目度も年々上がっている『goyemon』。現在の活躍は、ふたりのどのような行動や価値観によるものなのだろうか。東京渋谷にあるショップ兼オフィスで話を聞いた。
“無名の若者”だったふたりが、戦略的にたどり着いたブランドコンセプト
― はじめに、「goyemon」というブランドについてご紹介ください。
武内:「goyemon」は、日本の伝統と最新技術を融合させた商品を展開するブランドです。僕たち世代や更に若い世代は、日本の伝統製品を知っている人がすごく少ない。伝統製品には、先人たちの努力や工夫で生まれた良いものもたくさんあるのに、このまま衰退してしまうのは非常にもったいないと思っていて。伝統製品を持続的に発展可能にするには、今の若者たちが自然と手にしたくなるようなアップデートが必要。そこで、伝統製品を新しい技術と掛け合わせて、現代のライフスタイルにも馴染むようなプロダクトを届けるのはどうだろうか。そう考えて立ち上げたのが「goyemon」のブランドコンセプトなんです。
― これまでの実績についても教えてください。
大西:ファーストプロダクトとして発表した、雪駄×スニーカー『unda-雲駄-』をはじめ、クラウドファンディングでの支援額は2024年で累計1億円を突破しました。また、オンラインショップや店舗での販売は日本だけでなく外国の方も購入しています。自社オリジナルの製品だけでなく、「A BATHING APE®」「Snow Peak」「White Mountaineering」といったブランドからお声がけいただき、コラボレーションも実現できました。

― おふたりは、なぜ日本の伝統文化や最新技術に注目したのでしょうか。
武内:「goyemon」のはじまりは、2018年に(大西)藍ちゃんと僕でプロダクトデザインユニットを結成したこと。その時点では今のブランドコンセプトが決まっていたわけではないんです。また、そのときは社会人3年目。自分は照明メーカーでプロダクトデザインや商品企画を行う会社員でしたし、ふたりともデザイン賞などの受賞実績もない“無名のデザイナー”だった。そんなふたりがただブランドを立ち上げても、世間に注目される可能性はあまりにも低い。そう思っていたところ、藍ちゃんが「クラウドファンディングを使うのがいいよ」と言ってくれたのがきっかけなんです。
大西:僕がクラファンに目を付けたのは、資金を集めたかっただけじゃないんです。クラファンで注目を集めている他のプロジェクトを見て、自分たちに実績がなくても、プロダクトのアイデア次第で多くの人の目に止まる可能性があるんじゃないかと思った。また、アパレル関係者や流通・小売のバイヤーなどがリサーチ目的でクラファンサイトを見ていると知り、ここで話題になることがヒットの近道だと考えました。
そこで、クラファンで過去に注目を集めていたプロジェクトを徹底的に調べてみた。すると当時は「メイドインジャパン(日本のものづくり)にフォーカスした商品」と、「最新のテクノロジーを活用したガジェット」が人気な傾向にありました。だったら、この二つを掛け合わせて何ができるだろうかと僕たちは考えんです。
興味を持って日本の伝統文化を調べてみると、そこには先人たちが紡いできたストーリーがあった。また、今の人たちがものづくりにかける情熱にも僕たちは惹かれました。そのふたつを融合する形でブランドコンセプトが生まれたんです。
お互いの得意で不得意を補い合えるからこそ、タッグを組んだ
― では、ここからはキャリアの原点について教えてください。おふたりは東京都立工芸高等学校の同級生だそうですね。高校進学でこの学校を選んだということは、ものづくりが昔から好き・得意だったのですか。
大西:僕は親がおもちゃメーカー出身で、今は独立してデザイン会社をやっているような人なので、ものづくりは小さな頃から身近。職場に遊びに行っては仕事道具を借りて何かを創作しているような子どもでした。
武内:自分も絵や工作が得意で、親の影響で『ドラゴンボール』にハマってからは漫画に熱中していた時期もありました。オリジナルの漫画を描いて友達に見せたらみんながすごい喜んでくれて。早く続きを読みたいって言ってくれるから、ストーリーを考えるのが楽しかったのを覚えています。
― 工芸高校での出会いから、今こうやってビジネスパートナーになるほど仲良くなれたのはどうしてですか。
武内:入学式の時点で藍ちゃんは目立っていたんですよ。髪はオレンジ色だったし、型にはまろうとしないスタンスを持っている印象だった。同じバスケットボール部の仲間でもあったし、「カッコいいと感じるもの」の感性も似ていて……。お互いの興味があるものや、ネットで仕入れた海外のトレンド情報などをLINEで送り合いながら、「これはヤバいね」なんて言い合ううちに、大親友になっていったんです。
大西:僕は武内のことを親友であると同時に、一緒にビジネスをやる相手として密かに狙ってました。親の影響もあっていつかは自分で商売をしたいと考えていたんですけど、自分はオールマイティ―に何でもできるタイプではなく、得意不得意がはっきりしていて、ひとりでは無理だろうと思っていて。だから、自分のできないことを補ってくれる人を探していたら、まさしくそれが武内だった。来るべきときが来たら誘おうと、高校時代からずっと目をつけてたんです。

― 大西さんから見て、武内さんは何が得意な人なのですか。
大西:武内は、どんな人の懐にもスッと入っていけるところがすごい。「goyemon」の活動においても、外部とのネットワークや信頼関係のつくり方がめちゃくちゃ上手いんですよ。また、ブランドのコンセプトメイキングをはじめ、ストーリーを紡ぐ力がある。自分は言語化が凄く苦手なので、そこは素直に尊敬しますね。
― では武内さんから見た大西さんは?
武内:藍ちゃんは世の中の動向に敏感で、感性が鋭い人。でも、割と感覚的なところがあって言葉ではなかなか説明してくれないんですよ。だから、自分が「それってどういうこと?」と紐解いていくことで、僕たちはバランスが取れているのかもしれない。そんな風にお互い得意なことは違うけれど、好き嫌いの価値観は同じだし、藍ちゃんとだったら上手くいきそうな気がして、誘いに乗ったのが「goyemon」の始まりでした。
― 一方で、社会人3年目の会社員だった当時、新たなチャレンジができたのはなぜなのでしょうか。
武内:僕たちはいきなり独立をしたわけではなく、最初は会社員をしながら副業的にはじめたんですよ。会社員は組織の一員として“やらねばならない仕事”もあるけれど、藍ちゃんとの活動は自分たちが“やりたいこと”を思い切りやれそうだった。それが面白そうでチャレンジしたんです。
実際に始めてみると、クラウドファンディングでめちゃくちゃ反響をいただけた。試しにやってみたことで手応えを感じられたからこそ心は決まりました。自分が本当にやりたいことを本業にしよう。もし仮に失敗したとしても藍ちゃんとなら後悔はないし、その経験も人生の財産になるなと思ったから、独立に踏み切れた気がします。
ストーリーがあるチームには、お客様も仲間も集まってくれる
― ブランドの立ち上げから約6年が経ちましたが、当初から変わらない「goyemon」らしさがあるとすれば、どんなことでしょうか。
武内:僕たちは、“ものを売る”のではなく“ストーリーを売る”というスタンスで活動していて、それは昔から変わっていないですね。単に日本の伝統製品をモダンにデザインし直すだけのブランドにはしない。その伝統製品がどのような時代背景で生まれたのか、当時の人々はどのように使っていたいのか……といったところまで深掘りをして、そのストーリーをプロダクトに組み込むことにこだわってきました。
例えば、「unda-雲駄-」のもととなった雪駄は、一般的な靴とは違って左足用・右足用がなく、左右同形の履物です。これは、定期的に左右を入れ替えて履き、特定の箇所だけがすり減ることを避ける意味がある。つまり、ものをできるだけ長く使おうという“もったいない”文化から生まれたデザイン。だからこそ、僕たちが開発した「unda-雲駄-」も、このストーリーが伝わるプロダクトにこだわったんですよ。

― 逆にこの6年の間で進化したことはありますか。
大西:仲間が増え、チームとして大きく進化したことですね。僕たちふたりのプロダクトデザインユニットとしてはじめた「goyemon」ですが、今は6人のクリエイティブチームになりました。生産工程こそ外部にもご協力いただいているものの、商品企画~デザインまわりのクリエイティブに関しては外注せずブランドの価値観やコンセプトを深く理解しているチームの中でやり切る体制にしています。メンバーを迎えるときに意識しているのは、僕らが持っていない強みを持つ人を採用すること。例えるなら漫画『ワンピース』で、異なる能力を持つ仲間が一人また一人と船に乗り込んでくるような状態をイメージしていますね。
― その発想は、大西さんが「自分にはない強みを持つ人」として武内さんを誘ったのと同じですね。
大西:言われてみればそうですね。去年は3Dモデリングが得意な技術者に入ってもらいましたし、武内の会社員時代の後輩で「goyemon」に参加するために家族を伴って大阪から東京に来てくれたメンバーもいる。様々なバックグラウンドを持つ仲間が増えてきたことが、自分たちも面白いです。
常に挑戦を続ける集団として、世の中から憧れられるチームでありたい
― これからのことについても教えてください。どんなチャレンジを予定していますか。
大西:今チャレンジしたいのは海外展開ですね。現在でも渋谷の店舗に来るお客様の6割が訪日外国人。「goyemon」のコンセプトが海外にウケる素地はありそう。僕たちとしても、日本の伝統文化を海外にも積極的に発信していきたいです。とはいえ、むやみに拡大したいわけではないですよ。気持ちとしては“買ってほしい”というより、“応援してほしい”。最初にクラファンをやったときからそうなんですけど、僕たちにとっては金額や販売個数よりも「goyemon」のコンセプトに共感してくれる人が増える方が嬉しい。売上は後からついてくるものだと捉えています。
武内:その意味では、チームとしても唯一無二の存在として応援してもらえるようになりたい。「めっちゃ良い商品をたくさん出しているし、傍から見るとすげえ楽しそうに仕事しているけど、『goyemon』って一体どんなチームなの?」って興味を持ってもらえるような集団になることが僕の個人的な目標です。

― そうした活動を通して、おふたりは世の中にどんな価値を届けたいですか。
武内:僕たちの会社名は、ブランド名と統一する意味で今年1月に「株式会社goyemon」へと名称を変更しましたが、もともとの社名は「NEWBASIC株式会社」。固定観念を解体し、新しい常識をつくっていこうという思いで誕生した会社です。自分たちの活動に共感し応援してくれる人が増えることで、枠にはまらずチャレンジをする動きが世の中にもっと広がったら良いなと思います。
― とはいえ、チャレンジにはリスクもつきものですよね。失敗が怖くて動けない人もたくさんいると思うのですが、おふたりはなぜ挑戦できたと思いますか。
大西:時代のおかげもかなりあったと思うんです。クラファンのおかげで資金面のハードルを低くできたし、手軽にマーケティングができた。だから踏み出せた部分も大きいです。もっとリスクなくやろうと思えば、SNSで発信することからはじめたって良かった。そこで火がついて仕事になることも珍しくなくなってきているし、今ってチャレンジはしやすい時代だと思っています。
武内:とはいえ、僕は失敗が怖いという気持ち、めちゃくちゃ分かりますよ。実は、昔は失敗=“恥をかく”ことだと思っていて……。失敗ってゼロやマイナスになることだと思っていたからです。でも、僕たちだって上手くいかなかったことは何度もあるけど、実際に経験してみるとゼロにもマイナスにもならなかった。それどころか、「こうやったら失敗する」という学びが得られて、むしろプラスになったんです。
― 傍から見ると順調に見えるおふたりも、いろんな失敗を重ねているんですね。
大西:僕も色々と失敗してきましたよ。社会人になってからバーをやってみたり、メディアを立ち上げてみたり。と、面白そうだと思うものに色々と挑戦したんですけど、なかなか上手くいかなかったんですよね。けれど、その度に教訓が得られ、遂にいい感じかな?と思える事業が「goyemon」だったんです。
多くの人は、チャレンジの結果は失敗と成功の二択で、一度失敗したらそこで道が途絶えているようなイメージを持つと思うのですが、実際は失敗の先に成功はあるんです。だったら、成功するまでやれば良いだけ。失敗は成功するためのプロセスだと思えば、なにも怖くないですよ。

プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 大西 藍(おおにし・あい)
-
株式会社goyemon 代表取締役CEO、クリエイティブディレクター。1993年10月生まれ。都立工芸高校マシンクラフト科卒業後、日本大学芸術学部デザイン学科へ進学、家業であるデザイン企画会社で企画・製造・販売に携わる。2018年に高校時代の友人である武内とデザインユニット「goyemon」の活動を開始し、現在に至る。
- 武内賢太(たけうち・けんた)
-
株式会社goyemon COO、コンセプター。1993年11月生まれ。都立工芸高校マシンクラフト科を卒業後、東京工芸大学芸術学部へ進学。卒業後はコイズミ照明株式会社 商品部にて、企画・デザインを携わる。同社在籍中に、高校時代の友人である大西とデザインユニット「goyemon」の活動を開始し、現在に至る。