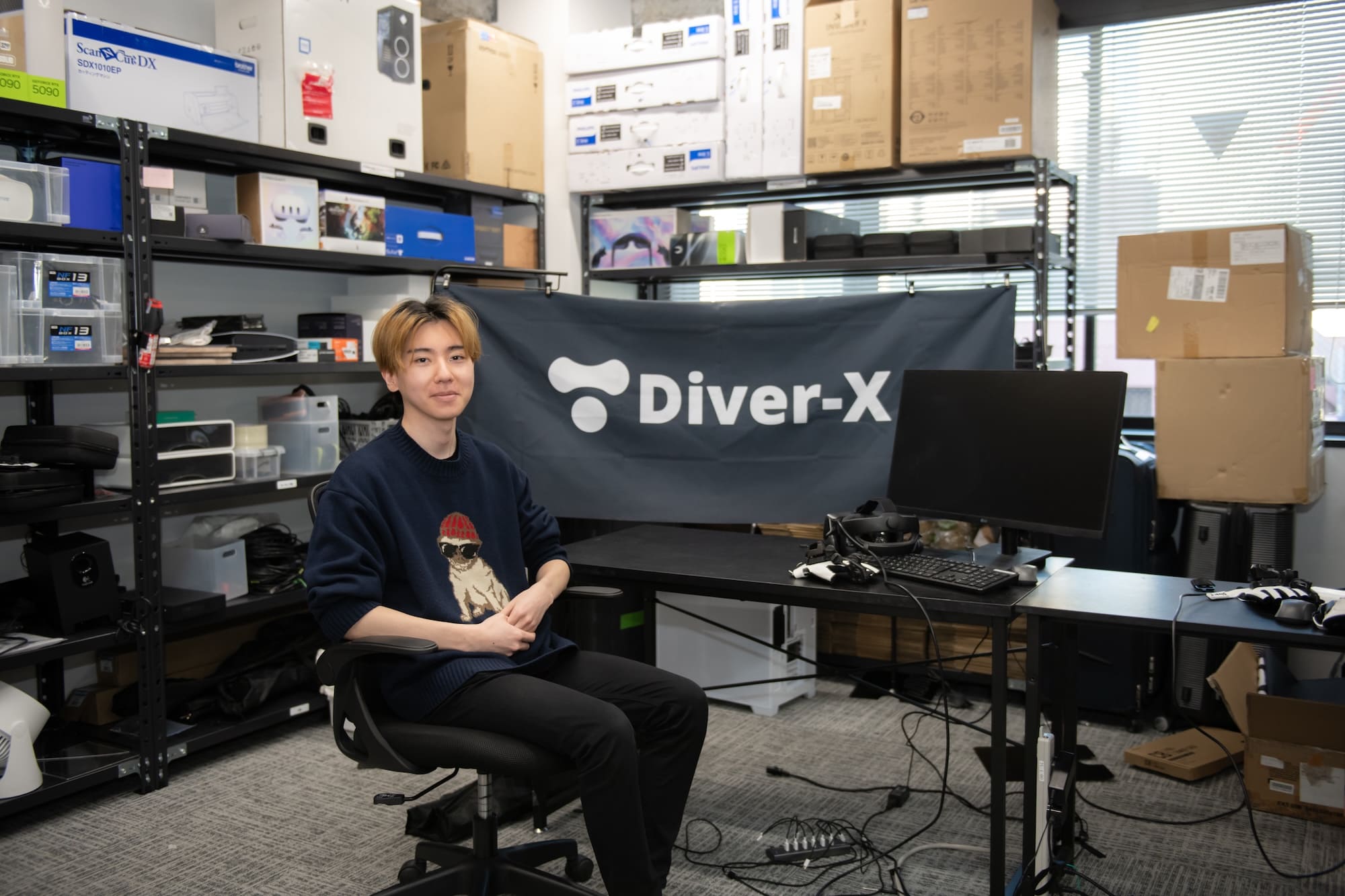150人の執筆者と一冊の本を作り上げた編集者に学ぶ、協創型ものづくりに必要な視点

執筆に参加した150人のうち、ほとんどが書籍制作未経験。『東京の生活史』を手掛けた、筑摩書房編集部 柴山浩紀さんの体験から、「一般参加型商品・サービス開発」成功のヒントを探る
150人が語り、150人が聞く。前代未聞の形式でつくられた書籍が2021年9月に刊行された。その名も『東京の生活史』。聞き手は広く一般に募集された中から選ばれており、その多くはインタビューや執筆を生業としている人ではない。さまざまなバックグラウンドを持つ人々が参加し、東京に生きる人々の話をフラットに並べたこの本は、まるで「#東京」で無作為にまとめられたSNSのタイムラインを眺めているようでもある。
この一大プロジェクトを担当したのが、筑摩書房の編集者、柴山浩紀さんだ。「一冊の本をつくる」という意味では、通常の制作プロセスよりも遥かに手間がかかるこの仕事を、柴山さんはどのような想いで受け止め、完成に導いたのだろうか。一般のビジネスシーンにおいても、ユーザー参加型商品開発や他社との協働プロジェクトなどが増えつつある今、多くの人を巻き込む仕事の体現者である柴山さんに、そのヒントを聞いた。
業界の常識や当たり前が通用しない難しさ。その先にある価値
『東京の生活史』は、社会学者であり作家の岸政彦さんの企画発案で生まれたインタビュー集。東京に生きる150人の語りを一冊に収録しており、1216ページ、150万字というかつてないボリュームも話題だ。以前から岸さんと親交があった柴山さんは、この原案となる構想を3年ほど前には知っていたという。しかし、まさか自分が担当するとは思っていなかった。
「岸さんがTwitterでつぶやいているのを見たんです。読み物として興味はあったけれど、作るとなれば相当苦労するのも想像できました。他の出版社から手が挙がるだろうとも思ったし、自分がやるとは考えてもいませんでした。それがある日、岸さんからメッセンジャーで相談されて。どう転ぶか未知数だったのですが、岸さんのお誘いを断りたくなかったし、『具体的なことは進めながら考えよう』くらいの感覚でスタートしました」
柴山さんが苦労しそうだと感じた理由の一つは、インタビューの聞き手(原稿の書き手)に関して。これまで、上間陽子さんの『裸足で逃げる』や朴沙羅さんの『家(チベ)の歴史を書く』のように、生活史の手法を使って書かれた本を担当したことはあったが、聞き手はその道の経験者が担っていた。しかし今回は、聞き手を広く一般に公募することにこだわったプロジェクト。さらに、語り手の人選を作為的なものにしないために、編集者は人選に関わらず聞き手自身が聞きたい人に話を聞く形式をとっている。誰が誰の話を書く本なのかさえ全く見えない状態で企画をはじめなければならなかった。

「一般的な書籍であれば、著者さんの過去の作品からある程度方向性を想定できますし、本を出したことのない新人作家さんなら、先に一部だけ原稿を書いてもらうこともあります。けれど今回はそうした方法が通用しない。岸さんが監修するとはいえ、応募者のみなさんが果たしてきちんと原稿を書き切れるのか、不安もありました」
実際に聞き手募集の告知をすると、想定を大きく上回る500名近くの応募が殺到。当初、80名~100名程度を予定していたが、最終的に150名に聞き手として参加してもらうことになった。インタビューや執筆を生業とする人もいたが、大部分は経験のない人々で、バックグラウンドもさまざま。しかし、制作を進めるうちにこの仕組みによって良いものが生まれる手応えを感じていく。
「最初に上がってきた数人の原稿を読んで、岸さんがやりたかったのはこういうことかと実感できました。語り手を募集するのではなく聞き手を募集するという仕組みが決定的でした。話したい人が話すのではなく、聞き手自身が語り手を見つけている。それが面白さにつながったんだと思います。聞き取りにあたってオンライン研修会を開き、岸さんが聞き取りの方法や原稿の書き方についてレクチャーしています。ここで強調していたのが、話してもらった言葉を忠実に、そのまま原稿に起こしていくことでした。この方法であれば、書くことに慣れていない人でも原稿にまとめやすいですし、言い方が難しいんですが、この方法が内容のおもしろさを担保してもいたんです」
また、オンライン研修会では協力していただく語り手のみなさんの尊厳を守るために最低限守ってほしいことなど、プロジェクトとしてのルールも伝えていった。しかし、ここまで準備しても彼らとプロジェクトを進める中では、普段は経験しない出来事に直面する。
「例えば、連絡事項のメールを送ると、『これってどういう意味ですか?』と見慣れない質問が返って来る。無意識に、業界内でしか通じないような専門用語や表現を使ってしまっていたんです。自分の中の当たり前でコミュニケーションをとるのではなく、どうすれば相手に十分に伝わるのか考えるさせられることが多かったですね。
一方で、目次に並んだタイトルを眺めると、普段の書籍制作ではなかなか出ない文字列に出会うこともあって。例えば、僕が好きな文章はこれです。
“私のあずかり知る東京はだいたいこのへんがすべてなんですけど。中央線がすべてなんですよね”
一瞬何を言っているのかよくわからないんですけど、おもしろいですよね。タイトルは、語り手の台詞から抜き出してくるルールなので、これ以上説明できないんです。結果的に、150人の声が飛び交うような目次になりました。目次を公開しただけで大きな反響があったので、びっくりしましたね」
1対150ではなく、1対1を150回
もうひとつ、150人もの人々を巻き込んだプロジェクトならではの出来事に、柴山さんはスケジュールを挙げる。多くの人が締め切りを過ぎても原稿を送ってくれなかったそうだ。当初、柴山さんは大半の人々が期日までに提出してくれるものだと思っていた。見事に当てが外れた格好だが、そこに多数の参加者が集うプロジェクトならではの落とし穴があったと言える。
「あくまでも僕の仮説ですが、『誰かに依頼された仕事ではなく、自分の意思で参加しているから』だと感じました。本業もあるし、モチベーションには波があって当然。みなさんがおかれている状況を理解して、プロジェクトに向き合う意欲を高められるようなフォローをすべきだったのかもしれません」
そうした気づきから、柴山さんは現在の入稿本数などを随時発信し、全体の進捗状況や原稿未提出の状況を分かってもらうような工夫をするようになったという。また、もうひとつ柴山さんが実践したことがある。1対150ではなく、一人ひとりの聞き手との1対1のコミュニケーションだ。

「それぞれが違う人の話を書いていますし、単純に個別対応しかできないからなのが一番の理由です。ただ、これは個人的な話ですが、もともと僕は大勢で何かするのが苦手で、少ない人数で何かを作りたくて編集者になったんです。そう考えると『東京の生活史』は初心とはかなり矛盾している。でも、僕自身は150人の著者と150の仕事をした感覚。そのスタンスで臨んだからやり切れたのかもしれません。時間はかかりましたし、大変だったのは間違いないですけど」
意思決定のプロセスに責任を持ち、透明性高く公開する
『東京の生活史』プロジェクトでは、本が完成するまでの制作プロセスを公開していた。これも、通常の書籍制作ではなかなか見られない形式だ。公式サイト上で「担当編集者制作日誌」の発信を続けていた柴山さんは、その意図をこう語る。
「いくつかの理由があります。通常では考えられないやり方でつくっている本なので、社内の人たちにも理解してもらいたかったのがひとつ。編集者の仕事や本づくりに関わる仕事を一般に伝えたかったのも理由ですね。僕たちの実態は世間のイメージより地味だと思うんですけど、細かいところの意思決定を重ねながら一つの本をつくっている。どんなプロセスで、何を根拠に決めていったのか。それがきちんと見えるようにしたかったんです」

こうした透明性は、現在あらゆる商品・サービスにおいて重視され、消費者からの信頼を獲得するために避けては通れない事柄になりつつある。また、制作日誌は書籍を手に取る読者に向けたメッセージでもあるとともに、150人の聞き手や、その周辺にいる人たちのためでもあったそうだ。
「150人もいれば、様々な考えや想いがあって当然です。もちろん、いただくご意見は可能な限り岸さんと協議してきましたが、すべてを実現するのは難しく、どこかで結論は出さなければいけない。最終判断は岸さんと僕とでやらざるを得ないからこそ、僕たちがどんな考えでどう判断したのかをお伝えしていく責任があると思いました。また、今回は、予想を越えた応募があったおかげで、やむなく300人以上の人たちをお断りしています。彼らにも選考の過程をお伝えする責任を感じましたし、せっかく興味を持ってくれた人たちに引き続き応援いただくためにも、制作プロセスをお届けしたかったんです」
現代では、インターネットを通しレビューや批判が飛び交うのも当たり前になった。それが消費者からの信頼を測る基準として機能している側面もあるが、誰もが簡単に発信できる分、心ない声を目にすることも少なくない。制作日誌はこの課題に対しても意味を持つのか?そう問いかけると、柴山さんは、制作プロセスを知ることで人々はその作品を尊重できるようになるかもしれないと語る。
「直接のお答えになるかわかりませんが、かつては、出版社が著者を守る役割を担ってもいて、読者と著者がここまでダイレクトにつながることはありませんでした。ものをつくるのはそれなりに大変で、著者の覚悟や苦労は一言で言えないものがあります。だからといって過剰に著者を持ち上げる必要もないですが、最低限の敬意を持ってほしいというか、それを軽々しい言葉で否定してほしくはないと思うんです。
今回は特殊な本の作り方をしていますが、著者が一人の本であっても、一冊の本ができるまでのプロセスが必ずあります。どの本も、一冊つくるのはけっこう大変なんです。なので、世の中に議事録を出すというか、こういうプロセスを経て作られたものだと知ってもらえれば、あるいは、本の読まれ方もすこし変わるかもしれません」
これは出版業界だけの話ではなく、あらゆる商品・サービスにもつながる話だ。制作者と消費者がダイレクトにつながれる現代。かつてよりも両者の距離が縮まったことは、制作者に多大な影響を与えている。これもある種の協創だといえるだろう。
実際の制作過程に参加してもらうか否かに関わらず、作り手の理論だけでものづくりを進めることはもはや不可能に近い。だからこそ、『東京の生活史』プロジェクトのように、多様な意見を尊重しながら一人ひとりに向き合うことや、意思決定のプロセスをオープンにしておくことは、これからの時代のすべての商品・サービス開発に求められることなのかもしれない。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 柴山浩紀(しばやま・ひろき)
-
1986年生まれ。2010年に太田出版入社、2016年から思想誌「atプラス」編集長を務める。2017年より筑摩書房。担当書籍は上間陽子『海をあげる』、朴沙羅『家(チベ)の歴史を書く』、岡啓輔『バベる!』、植本一子『家族最後の日』、白井聡『永続敗戦論』など。