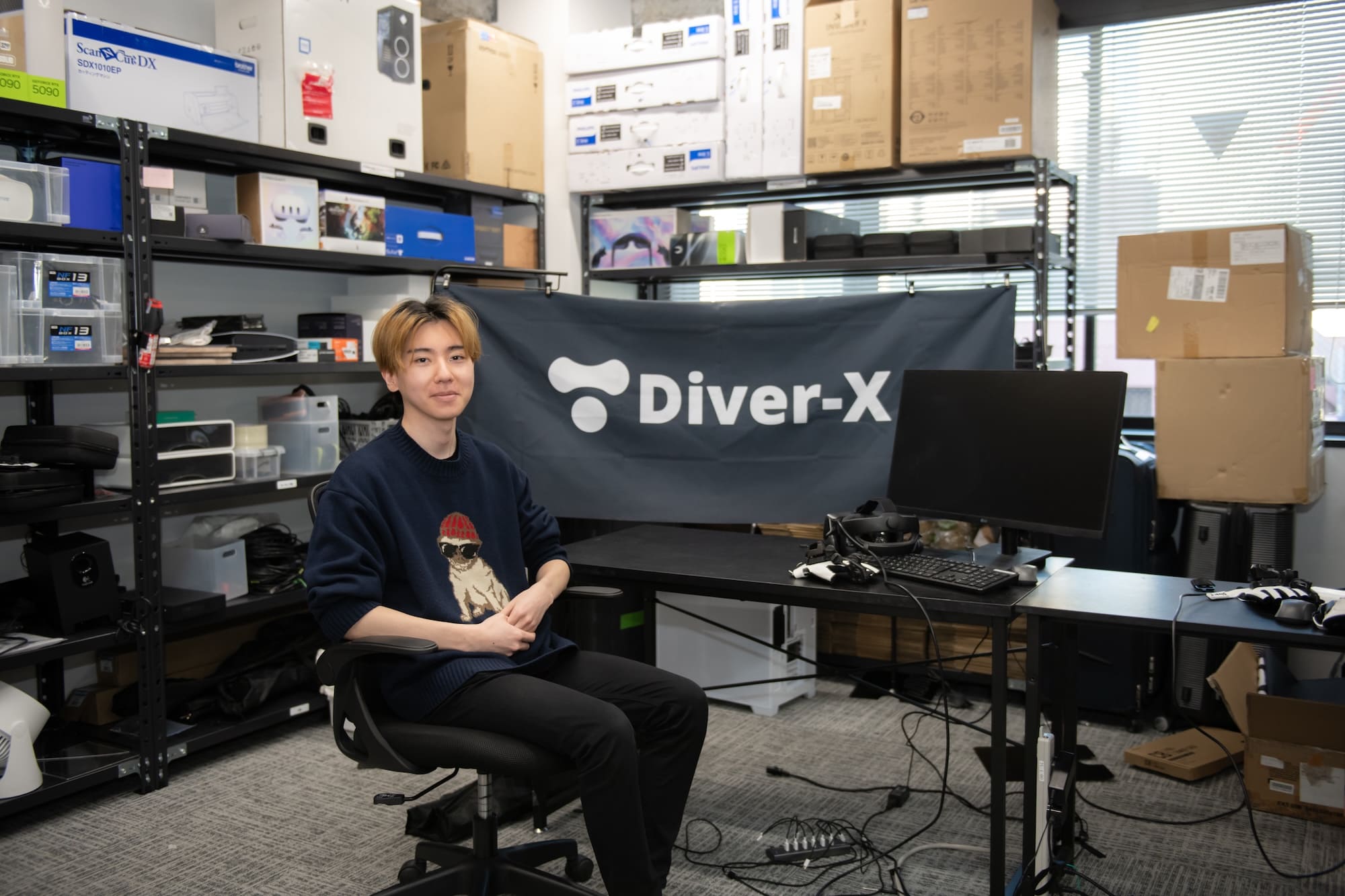対立を飛び越えて問題を転換する。平和研究から学ぶコミュニケーションの姿勢

意見の対立を「妥協」ではなく「トランセンド(超越)」していく。平和のための紛争研究から、コミュニケーションと相互理解のヒントを得る。
誰かと意見が衝突したとき、あなたはどのように対立をおさめて、物事を前に進めるだろうか。表現方法を変えたり、妥協点を探したり、根回しをしたり、さまざまな工夫があるはずだ。
対立や衝突が生まれるのは、個人同士や組織内だけではない。組織外、地域、人種、国と、規模が大きくなれば、そのエネルギーは増し「戦争」という形にもなりえてしまう。
こうした争いを不幸なかたちに帰結させぬようどう乗り越えるかを、学問として分析・研究しているのが「平和研究」だ。平和研究を専門とする明治学院大学国際学部教授の高原孝生(たかはら・たかお)先生は、対立や衝突は、むしろ相互理解を促すきっかけや、対立構造を超えて望ましい道を見つける手助けになるという。
平和のために争いや暴力を研究してきた平和研究から、日常的なコミュニケーションを円滑にするヒントを探る。
「争いがない=平和な状態」とは限らない
── 「平和研究」とはなんでしょうか。
平和を求めてなされる研究のことです。平和の条件を探る研究とも言えるでしょう。平和は、人間にとって、大事な価値。文化や言語の違いを超えて、人は平和を求め、平和を愛し、平和でない状態を何とかしようとします。平和の反対は何だと思いますか?
── 「平和」の反対…「戦争」でしょうか。
「戦争」は、平和の対立概念として、多くの人がすぐ思い浮かべるものですね。平和研究という学問領域が姿を現したのは、第二次世界大戦の後、冷戦と呼ばれた時代です。そこでは、諸国に戦争をさせないこと、とりわけ米ソ超大国に核戦争を起こさせないことが、研究の目的でした。次に世界戦争が起きたら、人類が絶滅するかもしれないという脅威は、今よりもいっそう深刻に感じられていたのです。
この「東西冷戦」に加えて、とくに1960年代から顕著になってくるのが「南北問題」です。主に地球上の北側に位置する先進工業国と南側に位置する開発途上国の間の構造的な経済格差問題のことを言います。
世界戦争、核戦争が起きていないとしても、日々、飢えや貧困で人々が早死にしていくなら、それは平和な状態なのだろうか。戦争さえなければ平和だと言えるか。格差を生み出している世界のありようそのものが、平和を奪っているのではないか。「南」側の研究者から実際にそのような問いを突きつけられ、国際平和研究学会では「平和」の定義を考え直しました。
そのときに「構造的暴力」という新しい概念も生まれました。直接的に暴力を振るわれるわけではないけれども、やられる側からすれば、暴力としかいいようのないような事態をさします。およそ50年前のことです。

── 東西冷戦や南北問題と言われると、歴史上の出来事という感覚が強く、日常とは少し遠い話のように感じます。
いや、そうでもないのです。気をつけないと戦争は今も起こりえますし、身近なところに引きつけて考えても、平和とは言えないという現実にきっと気づくはずです。たとえ家族が兵隊にとられたり、爆弾が落ちてくることに怯えたりということがないとしても、いまこのときを平和だと感じることができずにいる人は、決して少なくありません。
あらためて、最初の問いに戻りましょう。平和を脅かすものは何か。それは「暴力」です。こんにちの平和研究では暴力を、「人の本来の可能性を妨げるもの」と定義します。その極めつけは、人の将来、いのちそのものを奪ってしまう殺人です。人を傷つけることも、それが相手を本来できるはずのことができない状態に陥れてしまうから、暴力なのです。この暴力をふるわれたり、脅かされたりするとき、人は平和を奪われていると平和研究ではとらえます。
── 暴力を減らすために、平和研究ではどのようなアプローチをとられているのでしょうか?
大きくふたつあります。これは平和研究の特徴としてもあげられているものです。
ひとつは「未来志向」で考えること。今このときの満足でなく、すこし先、さらに先の状態を想像する。そのために、今何をなすべきかを考えるのです。子どもたち、孫たちのために、どんな世界を残したいかを考えるということにも近いでしょう。
未来志向で考えるためには、過去に学ぶことも必要になってきます。「地獄への道は善意で敷き詰められている」という西洋のことわざがあるとおり、よかれと思ってなすことが、必ずしもよい結果をもたらすとは限りません。戦争を避けたいなら、これまで起きた戦争にいたった過程、戦争を回避した事例、対立を解決してきた仕組みなどを、ちゃんと検討・分析することが大事です。
── 未来を先取りして、今の行動を考えるということですね。もうひとつは何ですか?
もうひとつは「価値志向」で考えること。平和研究では平和を最も重視し希求するのですが、広く人間全体からみると、「平和」もひとつの「価値」にすぎません。誰もが平和を望んでいると安易に言われがちですが、必ずしもそうとは言えない。歴史を振り返れば、敵を殺すこと、戦士をたたえることは、古今東西でみられたことです。日本も平和を唱えるのは「ひ弱」で、戦争を称揚していた時代からまだ百年も経っていません。
なぜ戦争がなくならないのかという問いにシンプルに答えるならば、領土や資源、国としての名誉など「戦争をしてでも得たい価値があるから」です。豊かさや名誉といった価値のために平和が犠牲になることは、むしろ常態と言っていいでしょう。
「忠臣蔵」が今なお人気である背景には「仇討ち」を肯定する文化があるのだと思います。「決闘」で人を傷つけることは、欧米でも百年くらい前には社会的に認められていました。また、言うまでもなく刑法で罰せられると知りながらも、殺人や傷害事件は後を絶ちません。
こうした暴力を組み込んだ人間社会のこれまでのありかたを根底から変えようと、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は「暴力の文化から平和の文化へ」の転換を唱えています。逆に言うと、平和の文化を意識的に追求しなくては、暴力的な社会に退歩してしまうということでもあります。

妥協することは本当に解決方法なのか?見方を変え、対立を飛び越えて転換していく
── わたしたちの日常生活にも、暴力と言えるような行為があると思います。自分が得たい価値のために、相手の意見を遮ってしまったり、自分の考えを無理に通そうとしたり。平和研究の考え方を日常生活に置き換えたとき、わたしたちはどんなことが学べるでしょうか。
人間が人間の社会で生きているかぎり、暴力につながりかねない対立や衝突がつきものです。人間はそれぞれ違う考えを持っていますから、お互いの意見や行動はどうしてもぶつかり合ってしまう。そのこと自体は、とても普通なことなのです。
このとき、多くの場合「妥協点」を探ろうとしますよね。妥協とは、どちらかが、もしくは双方が求めていたものを諦めることを意味しています。そうすると表面上は納得しているように見えても、しこりが残る。それが後の対立や衝突につながることもあります。
ここで別の考え方を提示するのが、ノルウェーの平和学者ヨハン=ガルトゥングです。彼は「超越する」という意味を持つ「トランセンド」という方法を提唱しています。双方の間に妥協点を探すのではなく、衝突をもたらした問題自体を組み替えることで、対立を転換していこうという考え方です。イメージとしては、和解のためのカウンセリングのノウハウに似ています。
例えば、とある新商品のキャッチコピーがなかなか決まらないとします。プロジェクトのキーパーソンであるAさんとBさんの意見が、いつものように折り合わないのです。このとき、目の前の「キャッチコピーをどうするか」からいったん離れてみる。Aさんに一対一で話を聞くと「日頃から、Bさんのわがままが気に食わない」と思っていることを吐露してくれました。
ここまではよくある話ですね。さらにふたりと継続的にコミュニケーションをとっていくことしました。丁寧に話を聞いていくことでわかったことは、Aさんにはどうやら小さい頃から確執のあるお兄さんがいて、そのお兄さんの言動がBさんと似ているようなのです。小さい頃から、お兄さんと似た側面のある人とずっとうまく関係が築けなかったこともわかりました。
問題は、キャッチコピーの方向性や良し悪しではなく、AさんとBさんの不仲でもなく、Aさんの家庭にあったわけです。Aさんは、自分の家族との隠されたコンフリクトに気づき、まずは実家に兄弟みんなが集まって食事を取ることから始めてみると言います。
衝突があると、妥協や諦めによる「解決」に走ってしまいがちですが、少しでも余裕があるなら、一歩下がってみることが有効でしょう。そこで周りの人が建設的な役割を果たすこともある。相手のことをよく知れば、こちらがイラつく言動にも相手なりの理由がありそうだと気づいたり、この場合のAさんのように、自分自身の抱える問題を新たに発見したり、といったことがたいてい始まります。Bさんにも似たようなことがあるかもしれません。そのようなプロセスが進めばしめたものです。
── 確かにその通りだと思いますが、どうしても怒りが湧いてしまう瞬間があったりします。
そんなときは、後で悔やむようなことをしてしまわないよう、怒りの爆発を賢く避けることが大事です。心理学の知見をもとにした「アンガーコントロール」では、例えば急に怒りが沸き起こったとき、6秒胸に手を当てて待つことで衝動的な憤怒を押さえられると言われています。
街で誰かと肩がぶつかったとします。お互いに何も言わずに立ち去れば「なんだ、あいつ」という負の感情がたまりますね。しかし「すみません、失礼しました」と一言謝れば、相手も「この人は悪気がなかったのだな」と考えて「こちらこそ、失礼しました」と気持ちよく別れることができる。ちょっとした行動ひとつで、感情をコントロールできる部分もあるわけです。
対話を通じて、相手を「わかり」、「変わる」
── お互いに考えていることをきちんと言葉にし、理解してもらえるように努める。ビジネスシーンでも必要なことだと思います。しかし現状は、対立を避けようと黙ってしまうことが多い。
日本社会の特徴として、そもそも対話が少ないですよね。トラブルが起きないようにお互いに意見を言わずに丸く収めようとする。しかし、そういうやりかたを選ぶことで、失われている豊かさがあるかもしれない。表面的なコミュニケーションで「これでOK」と安易に決めない。よく相手の話を聞くことで、思ってもいなかった打開の道に気づくことがあります。その「気づき」によって、事態は変わっていくものです。
「わかる」とは何か。自分が「変わる」ことです。以前の「わかっていなかった自分」から変わっていないなら、わかったことにはならない。この「変わる」ことにはエネルギーが必要です。人間がだんだん学ぼうとしなくなり、保守的になるのはそのためです。できるなら、これまでのやり方のままでいきたいですよね、楽ですから。
18世紀の哲学者イマヌエル・カントは、「未成年状態」を脱することが、当時の大多数の人にとっての課題だと言いました。未成年状態というのは、自立した大人になれていないということ。ちゃんと物事を考えるのは他の誰かに任せて、自分は世間が許す枠の中で「分を守って」生きる。そして自分がそんな成長半ばの状態であると気づくこともなく死んでいく。それではもったいない、人間として生まれた以上、本来なれるはずの自立した大人になろう、それが自然なあり方のはずだから、とカントは呼びかけています。

── わかろうとしない、変わろうとしない未成年状態を脱するには、どうすればよいのでしょうか。
カントは当時の人々の様子を見て、楽な方へと流れる「怠惰」に加え、「怯懦(きょうだ/すぐに怖がったりためらったりすること)」が、人が大人になるのを妨げていると指摘しています。その時代、庶民は「自ら考え行動する」などということは、身分をわきまえないだいそれたことだと感じさせられていた。人々が臆病になっているのは、まさに自由が奪われているからだとカントは考えました。だから古い抑圧的な社会体制をくつがえしたフランス革命にも理解を示していた。つまり、自由は普通の人にとってこそ大事なんです。
日常の話に引き戻してまとめましょう。相手としっかり言葉を交わし、あるいは第三者の助けも借りて、お互いの求めているものをよりよく知ることです。そうすると大抵の場合、わかっていなかったものが見えてきて、視界があらたまる。歩き出せそうな道筋が開け、現在の対立や衝突が、「転換」されていくのです。
対話が大事だ、なんて記事の結論としてはつまらないかもしれません。しかし、ちゃんとコミュニケーションを取ろうともせず、お互いを理解せぬまま衝突していることが、外交関係から身の回りにいたるまで、本当に多いのです。実は「ヤマアラシのジレンマ」といって、愛し合おうとして近づきすぎるとかえって傷つく、という問題も人間にはあったりします。ただ、たいていの現実は、はるかそれ以前の段階ですから。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 高原孝生(たかはら・たかお)
- 明治学院大学国際学部教授、同大学国際平和研究所長
-
東京大学法学部助手(国際政治学)、川崎地方自治研究センター、立教大学を経て 1985 年、明治学院大学に着任、翌1986 年発足の「国際学部」創立メンバーの一員となり、2007 年同学部教授。コーネル大学平和研究プログラム、メリーランド大学一般軍縮プログラム、ヘルシンキ大学政治学部、モントレー不拡散研究センターで、客員研究員を歴任。1993 年よりパグウォッシュ会議に参加、2011 年より 2013 年まで国際評議員。現在、Peace History Society 国際評議員、NPO 法人ピースデポ副代表、第五福竜丸平和協会理事、日本平和学会理事。