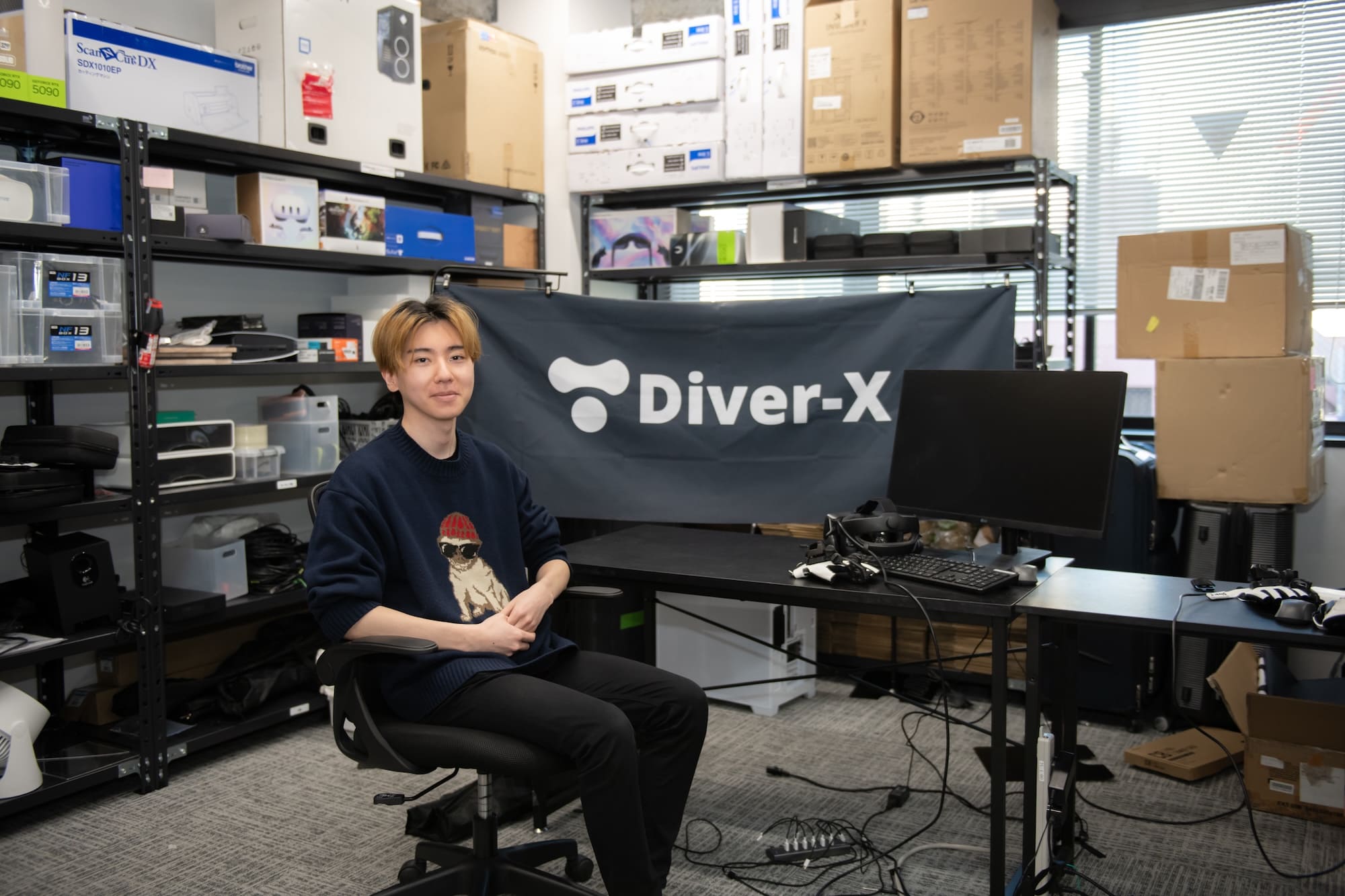世界最年少のマスターソムリエ高松亨が北海道でワイン生産者を目指す理由

世界最難関と評される資格「マスターソムリエ」を日本人初、世界最年少で取得したあと、北海道・余市のワイナリーで修行中の高松亨さんは、「自分の適性に冷静に向き合う」ことで可能性を切り拓く。
自分はいかなる特性を持ち、どのような環境にいると楽しいのか。この問いにピュアに向き合い、大胆な意思決定をしたり、環境を変えられる人は決して多くないだろう。
1995年生まれのソムリエ 高松亨(たかまつ・とおる)さんは、この問いにピュアに向き合い続けてきた人物だ。世界最難関と評される資格「マスターソムリエ」を日本人初、かつ世界最年少の24歳で取得。現在は「余市町地域おこし協力隊」として活動する中、北海道余市町のワイナリー「ドメーヌ タカヒコ」で研修している。
生まれ育ったのはオーストラリア・シドニー。15歳でカフェで働きはじめてバリスタという職業に夢中になったが、19歳でワインに出会って、21歳の時にソムリエを志す。その後イギリスに渡り、24歳でマスターソムリエの資格を取得。世界中の名だたるレストランで活躍できるほどの資格を持つにもかかわらず、辿り着いたのは日本。しかも、次はワインの「生産者」という道を選んだ。その一つ一つの選択の背景にあった想いとキャリア観を伺った。
足元の現実を見ながら、得意なことで勝負を仕掛ける
── 高松さんが持つ、ワインやコーヒーなど食への興味はどこから生まれたのでしょうか。
料理人の父の影響は大きいと思います。欲しい物をなんでも買ってもらえるような家庭ではありませんでしたが、食べ物に関しては本当に美味しいものを食べさせてくれたんです。その結果発達した「味覚」は自分の強みになりました。15歳のころには料理や食の仕事が向いていると思うようになり、オーストラリアの生活ではとても身近な存在である街なかのカフェでバリスタとして働き始めました。
実はその頃、ITにも興味があったんです。独学でプログラミングをしていたのですが、すぐに自分には才能がないと悟りました(笑)。同世代が競争しても、プログラミングで自分が上にいくのは難しいとはっきり感じたんです。ITよりも、料理や食の仕事をする人生を選んだ方が楽しくなるだろうと思いました。
── 食以外の選択肢も考えていたのですね。食を選び、その興味がコーヒーからワインへと変わったのはいつ頃だったのでしょうか?
お酒が飲める年齢になってすぐですね。オーストラリアの法律では18歳以上から飲酒が認められているんです。ワインと出会ってわりとすぐに、コーヒーの道を極めて「バリスタ」になるより、「ソムリエ」を目指す方が自分には向いていると感じました。バリスタはキャリアが進んでいくと、店舗の現場責任者や豆の焙煎、買い付けなどを担うのが一般的。ですが、正直、僕はそれらに興味を持てなかったんです。コーヒーを淹れる仕事は好きでいつまでも探求したいと思えたのですが、店舗でのマネジメント的な要素を極めていくモチベーションはありませんでした。
一方、ソムリエは基本的にはワインと向き合う専門家という仕事。かつ、世界共通の「資格」があります。 資格さえあれば“専門家”として国を跨ぐキャリアも描きやすい。「国に縛られず、自分の働きたい場所で仕事したい」と思っていたので、その点でもソムリエはぴったりでした。「どこでも生きていける」という期待もあり、ワインの道を選びました。
── 10代の頃から堅実にキャリアを重ねて来ている印象を受けました。高松さんがキャリアを選ぶ時に大事にしていることはなんですか。
自分に合う条件は何か、で選ぶこともありますが、大事にし続けているのは、シンプルに「自分自身が楽しいと思えること」です。ただ、生活的に厳しくならないかはいつもシビアに考えている気がします。どれだけ失敗しても、世界のどこでも仕事ができるソムリエの資格があるからこそ、今も生産者というまったく新しい領域に挑戦できている。好きなように生きていると思われるかもしれませんが、意外と足元の現実を見ながら、未来の可能性に賭けていくようにしていますね。
「向き不向き」を自覚し、どうせやるなら極める
── 現実を冷静に見つつも、「これだ!」というものを見つけると、一気に突き進むタイプなのでしょうか?
そうだと思います。どうせやるなら極めたいといいますか。中途半端にやるのであればいっそやらなくていいかな、と思ってしまうんです。仕事にこそしませんでしたが、実はゲームにも相当熱中しました。好きなことにはとことん没頭するタイプなんだと思います。
マスターソムリエの資格も同じような思いではじめましたね。挑戦すると決めたらすぐにワーキングホリデー制度を使い、ワイン流通の中心地であるロンドンに移住。ワインにアクセスしやすい環境を整えました。その上で、ありとあらゆるワインを知る努力をしました。マスターソムリエの試験は、さまざまな地方、年代、価格帯から生産者の違いまで、繊細な味わいの違いを説明することが求められるので。生活費もできる限り削り、好き嫌いに関係なく本当にさまざまなワインを飲み、知識を蓄積していきました。
とはいえ、「自分自身が楽しいと思えること」は大前提なので、あくまで苦なくできる範囲で勉強していました。

── お聞きしていると、高松さんはご自身の「向き不向き」にかなり自覚的ですよね。
自分に向いているかどうかは意識していますね。例えば僕は“味覚の記憶力”に関しては、かなり自信をもっています。マスターソムリエは10年かけても取れない人がいるほど難しい資格ですが、「一度口にしたものの味わいを忘れない」という自分の強みを活かして全力で挑めば、可能性はあると思って勉強していました。
好き・嫌いに関しても同様です。僕はワインを説明して知識を広めることが好きです。誰にも負けないワインの知識と良いサービスの提供を大事にして、ソムリエとして仕事をしてきました。
例えば、僕が働いていたロンドンのバーでは、お客様にワイン通の方が多く、60年代のヴィンテージワインの深い説明を求められるような環境でした。そういったワインを愛する人のことを知ること自体とても楽しかったんです。ただ、国やお店が変わると事情も変わります。イギリスから帰国後に働いたオーストラリアのレストランではワインの知識やワインを愛する人への理解より「お客様とフレンドリーに接すること」を大事にしていた。そういった環境は自分に向かないなという感覚がありました。
── そういえば、先ほども「マネジメント的な要素を極めていくモチベーションはなかった」とお話されていました。
はい、バリスタに求められるマネジメント的要素を極めていくのは自分には向かないなと思い、ソムリエを選びました。ただ、考えてみるとソムリエを極めても、レストランという組織の中では、いずれマネジメント的要素も考えなければいけないとわかってきました。
レストランはチームワークがとても大切なんです。例えば、適切なタイミングでソムリエがワインを出すためには、ホールの担当者がそれを逆算してお皿を下げていなければならない。そうした現場オペレーションまで極めようとすると、「人を育成する」という方向にまで発想が向かってしまいます。合理的に考えれば、ワインへの造詣が深く、かつマネジメントに長けているソムリエが上司になるべきだと僕も思うので、当然ではあるんです。
自分の好きなことに純粋に向き合うために
── 「ワインを極めたい」という気持ちが、高松さんが生産者を目指すきっかけに繋がったのでしょうか?
そうですね。ソムリエの仕事をする中で「自分のワインを作りたい」という気持ちはあったのですが、結果的にきっかけになったのはコロナ禍でした。当時勤めていたオーストラリアのレストランでフロアを担当していたスタッフが全員辞めることになってしまい、僕自身「これからどうしようかな」と考える機会になりました。
かつ、先述した理由から、ソムリエとしてキャリアを積むことに違和感を覚えはじめていたことも確かです。世界中を探しても「ワインだけ」と向き合うソムリエの仕事はほとんど存在しませんでした。このままキャリアアップを目指しても、うまく馴染めないのではないかと思ったんです。
それよりも、だんだんと興味を持ち始めた「生産者の道」を追い求めた方が良いかもしれないと思いました。ソムリエの資格では深くは学ばない栽培や醸造の勉強をすることで、よりワインを極めることになるからです。
実際、いま生産者としてワインを小規模に作っていて、やっぱり僕は個が向いているし、人を育てたりマネジメントするよりことよりも「一人でやりとげたい気持ち」が強いんだな、と感じます。だから、この方向性はたぶん間違っていない。今はマスターソムリエの次の目標として、ブドウの栽培から醸造、ワインビジネスまで幅広い知識を問われる世界最難関資格「マスターワイン」の資格取得を目指して勉強しています。

── とはいえ、ソムリエの最高峰の資格を一度取得してから、生産者へと方向性を変えるのは大変なことかと思います。どのようにしてワイナリーで働くに至ったのでしょうか?
せっかく働くのであれば、世界中にあるワイナリーの中でも「自分が将来的にこんな生産者になりたい」と思うところで仕事をしたい。そう考えて連絡したのが、現在勤める日本のワイナリー「ドメーヌ タカヒコ」のオーナーである曽我貴彦さんでした。
この時の曽我さんからの返信が、結果的に僕にとっての転機になったと思っています。「短期や中途半端な受け入れはできません。本当に働くのであれば、2年間しっかりと研修して余市町でワイナリーを開く覚悟を持ってください」と。正直ハードルが高いと思いましたが、これだけ美味しいワインが作れるところは他になかなかない。僕もオーストラリアを出る覚悟を決め、まずは地域おこし協力隊として北海道に移住しました。
実際に栽培や醸造を手を動かして学びはじめてからは、ワインについての考え方に大きな影響を受けています。教科書で学ぶワイン作りは“工業っぽい”イメージがありましたが、小規模にいいものを作っているワイナリーは、もっと人の手がかかっている。例えばラベルが工場で瓶詰めされて勝手に貼られるのではなく、手作業でひとつずつ貼っていたりします。そうした光景を目の当たりにし、一本のワインの背景を想像できるようになりました。
ソムリエと生産者を両立するから生まれる、オリジナルな強み
── 生産者は土地との結びつきが強い仕事ですよね。ソムリエを目指していた頃の「国に縛られず、自分の働きたい場所で仕事したい」という高松さんの思想とは乖離しているようにも思えるのですが。
いままで僕はソムリエとしてあちこちの国を渡り歩いてきましたが、今の目標は自分で畑を購入してワイン作りをはじめること。自分がワイナリーという場所を持つことが現実味を帯びてきて、この地域にしっかりと根を張るのだろう、という感覚があります。
とはいえ、まだまだ勉強することは山積み。特に、ワインは年に1回しか作れないので、まだ全体像が見えていません。日々仕事をしながら「自分のワイナリーだったらどうするか」と常に考えていますが、実際に自分で作りはじめるのは良い畑に巡りあった時なので、タイミングは運任せ。とにかく、いまはここで勉強していて楽しいので、日々を悔いなく過ごしたいです。
── ソムリエと生産者、両方を経験している高松さんだからこそ得られた視点はありますか?
ソムリエは「どうすれば一番美味しいワインを届けられるか、いかにサービスするのがベストか」だけを考えます。そこでさらに生産者の視点を得ると、ワインの品質のばらつきに着目し「なぜ品質が下がってしまったのか」と考えたり、別の飲み方を提案したりできるようになりました。
それは“正統な”ソムリエがするべきことではないとも思います。サーブをする側が生産者の事情にまで踏み込みすぎると、客観的に見れなくなりますから。「生産者はこう飲んでほしいと思って作ったはず」「しかし、自分はこう飲むのが美味しいと思う」と、ソムリエか生産者か、どちらを優先すべきか葛藤が生まれてしまいます。ソムリエだけでもなく、生産者だけでもない。それは正統なソムリエには持ちえない、僕独自の強みになるんじゃないかと思っています。

プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 高松亨(たかまつ・とおる)
-
1995年生まれ、オーストラリア出身。15歳からバリスタとして飲食店に勤務したのち、ワインと出逢う。2019年には、世界のソムリエ業界の頂点に立つマスター・ソムリエの試験に合格。日本人初で、現在は世界最年少の有資格者。2021年5月、余市町地域おこし協力隊 ワイン産業支援員に着任。