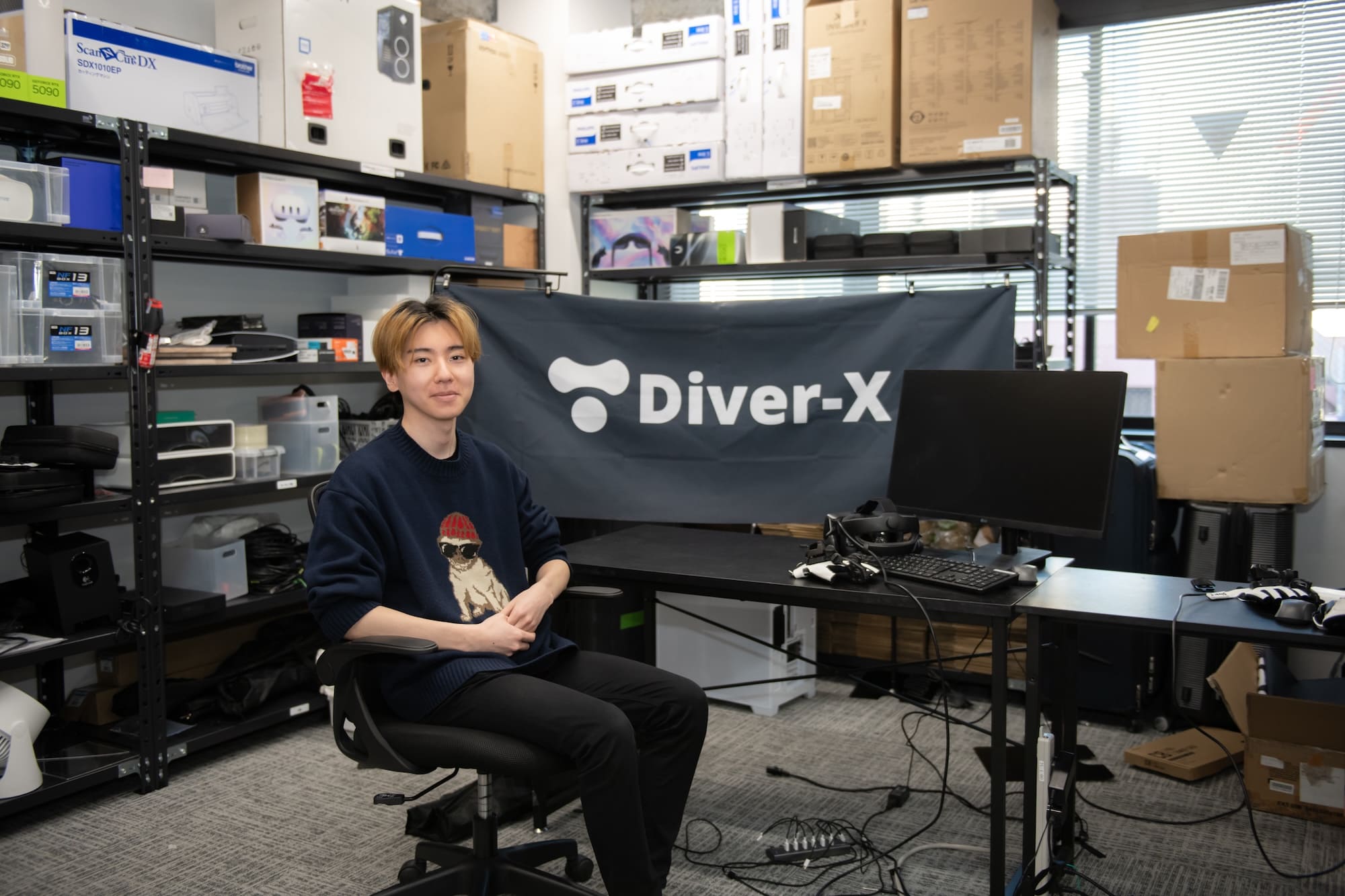新たな挑戦に年齢は関係ない。日欧で活動してきたアーティスト雨宮庸介と考える、越境的キャリア

“溶けた林檎”をモチーフにした彫刻作品《Apple》などで注目されるアーティストの雨宮庸介さん。日本→オランダ→ドイツ→再び日本で活動する雨宮さんは、国境を越えることで何を獲得してきたのか
彫刻、映像、パフォーマンスなど、様々な手法を用いて私たちが生きるこの世界を表現し、世界や物事の境界線に揺さぶりをかけるアーティスト、雨宮庸介さん。1975年生まれの雨宮さんは、多摩美術大学を卒業後の約10年間を日本で活動し、2011年に渡欧。オランダのサンドベルグインスティテュート大学院で学んだ後は、ドイツのベルリンに拠点を移して様々な作品を発表してきた。2022年に帰国し、現在は日本を拠点に活動中。10年スパンで日本、ヨーロッパ、再び日本…と環境を変えてきたことは、キャリアや生き方、価値観にどのような影響を与えているのだろうか。雨宮さんのこれまでの人生を紐解きながら、すべての人に通じる普遍のヒントを探った。
アートなら、「人の決めた正解からはみ出すこと」がチャンスになる
── 雨宮さんはなにをきっかけに美術の道を目指したんですか。
はじまりはシンプルで、生まれ育った水戸市の中では群を抜いて絵が上手かったんです。もともとはサッカー少年で市の選抜チームにも入っていたのですが、高校最後の試合で敗退すると急にやることがなくなってしまい。これからの進路を考えた結果が、自分の得意なことを活かして美大に進むことでした。
── もともと絵が得意とはいえ、サッカーから美術への転向は大きな変化ですね。
自分の中ではそうでもないんですよ。水戸市には、日本や世界でトップレベルのアーティストの作品が観られる「水戸芸術館」がありますが、少年時代に開館したこの施設は、市の選抜チームが練習していた小学校の移転跡地に建設されているんです。だから、全く違う世界に飛び込んだ気もしなくて、慣れ親しんだ場所でアートに触れられたのも良かった気がします。

── 美大で本格的に学ぶ前に「水戸芸術館」で現代アートを間近に見ていたことも、影響されているのではないですか。
そうですね。水戸芸術館は高校時代に通っていた美術予備校と国道を挟んだ場所にあったんです。それもあって、自分が受験対策として取り組んでいた「石膏デッサン」と、一流アーティストの作品にギャップを感じさせられました。石膏デッサンは、言ってしまえば大理石像のコピーである石膏像を更に絵として平面に"コピー"する行為なわけです。自分がやっていることは果たしてアートなんだろうか、そもそもアートとはなにか…と考えるようになりました。
── 形式にとらわれない現代アートを志向するようになったのも、この頃なのでしょうか。
当時出会ったいろんな作家の影響があったと思いますが、少年時代の私が一番衝撃を受けたのは、水戸芸術館で開催されたジョン・ケージによる企画展「ローリーホーリーオーバーサーカス」です。偶然性に委ねて展示作品や展示場所をどんどん変化させていく仕掛けになっており、観に行くたびに全く違う体験になることが印象的で、ジョン・ケージの他の作品にも興味を持つように。自分が表現したいことはこういうことなのかもしれないと思い始めたきっかけでした。
── その後、アーティストとして生きていこうと決断したのはいつ頃ですか。
「決断した」という感覚はなくて、美大進学のために絵をはじめて以来、道を変える決断をしていないだけですね。大学を卒業するときも、3月31日までやってきた創作活動を4月1日からも継続していただけ。ただ、若いころにアルバイトをしていた植木屋の仕事は結構好きで、このまま庭師になろうかと思ったこともありますよ。
でも、最終的にやらなかったのはデザインとアートの違い。造園はクライアントのオーダーにあわせて岩や草木の配置をデザインする仕事なので、相手の正解の中に収めることが必要ですよね。それに対して、アートの場合は正解の箱が極めて曖昧。むしろ意欲的に枠をはみ出し、アート自体を再定義するような挑戦も歓迎されていることにチャンスを感じたんです。
30代半ばでの渡欧は、もう一度苦労や葛藤から学びを得る機会だった
── 雨宮さんは日本で実績を積んだあとにアムステルダムの大学院へ留学をしています。これはどのような意図なのでしょうか。
実は、それ以前にも学部を卒業するタイミングでオランダに来ないかとお誘いをいただいていたんです。コンテンポラリーアートは西洋の歴史との結びつきが強いので、日本国内だけで学ぶのは限界も感じていました。でも、20代の僕はまだ実績に乏しく自分に自信が持てなかった。今の環境を飛び出す前にまずは自分を確立させたいと考え、10年は日本で制作をすると決めていました。
ただ、いま留学を迷っている若い人にアドバイスするなら、すぐに行くことをおすすめしますね。僕がヨーロッパに渡ったのは30代半ば。まだ自分の価値観を確立する前の10代~20代で留学した友人とは違って、「価値観がひっくり返るような衝撃的な体験」をしたわけではないんです。また、語学は若いうちに学んだ方が習得のスピードは早いはずで、コミュニケーションにはとても苦労しました。
── とはいえ、オランダでの大学院生活とドイツでの創作活動で計10年超はヨーロッパを拠点にしています。日本とは異なる環境にチャレンジして得られたものもあるのではないでしょうか。
30代中盤で環境を変えて良かったなと思うのは、自分が通用しない経験をもう一度できたこと。これくらいの年齢になってくると、少なくとも自分の領域なら経験も知識もあるから、大抵のことには対応できるじゃないですか。それなのに、ヨーロッパに来たら言葉や習慣の壁が立ちはだかった。そもそもオランダやドイツは自分の考えを言葉にして表明することが求められる環境です。はじめのうちは意見を求められてもまったく言葉が出てこないし、ディスカッションが中心の授業にもついていけなかった。そんな悔しさをあの年齢でもう一度味わうことができたのは、自分にとって大きな刺激になりました。

── 海外生活を通して感じたことや、日本を離れたからこそ見えたものもありませんか。
よく言われることですが、自分は思ったよりも日本のことを知らないんだと自覚しました。現地で知り合った人、特にアートに造詣の深い人たちには日本に詳しい人が多く、彼らが好きだという日本の漫画や映画の話に全然ついていけなかったんです。外から日本の魅力に気づかされた部分も大いにありますし、そうやって興味を持ってくれているのに僕が彼らと同じくらいの熱量で他国の文化に接していないことが申し訳なくて。自分の文化レベルを見つめ直す機会でした。
── 作品や作風にも影響しているのでしょうか。
ヨーロッパの文化や環境自体が作品に影響しているかどうかは分からないです。僕が渡欧したのは2011年のこと。ちょうど東日本大震災と時期が重なっており、故郷の茨城も影響が大きかったため、僕にとっては震災のインパクトの方が強いんです。
でも、震災後の時期を海外で暮らしたことで、物理的な距離が遠くなるほど被災地に対する想像力や当事者性が薄まっていくのを感じたのは少なからず影響している気がします。というのも、その後世界を襲ったコロナ禍は震災とは対照的だった。世界のあちこちで同時多発的に感染が広がったことで、みんながパンデミックの当事者になり、距離が離れていても相手を想像し思いやることができましたよね。そうしたことに考えを巡らせながら作品制作に向き合うようになったのは、自分が日本と距離のある海外に身を置いていたからかもしれません。
年齢や経験を重ねるうちに、自分の“資源”は変わっていくもの
── 約10年の海外生活を経て、2022年に日本へ拠点を移されたのはなぜですか。
これは家庭の事情によるところが大きいのですが、もともと海外に行くならそれくらいはいようと思って飛び出したので、偶然にもちょうど良いタイミングで戻ってきた形ですね。
── 日本に戻ったことで、改めてオランダ・ドイツと違いを感じることはありませんか。
ものごと全般に対しての受け取り方・リアクションの仕方に違いを感じます。例えば同じ芸術作品を見せたとして、日本の人たちは目の前の作品をまず黙って受け止めようとする。「しんみりと、沁み入るように観ている」感じがあります。ヨーロッパの人たちは、とりあえず手を挙げて自分が感じたことを素直に述べる。意見の良し悪しは関係なく、手を挙げることが正しいからやっているという印象ですね。
ただ、僕はどちらのリアクションも好きですよ。もちろん、社会構造や言語構造など細部の違いを挙げればキリがないのですが、同じ人間として根本は一緒。たとえば、誰だって自分のために良かれと思ってしてもらえたことは嬉しいじゃないですか。渡欧前は分かりあえない、通じ合えないこともあるのかと思っていたのですが、異なる環境で様々な人と接したことで、人としての普遍性を感じました。
── 10年ぶりに日本で暮らすと、どんな変化を感じますか。
僕は美大生との接点が多いのであくまでもその範囲での意見ですが、今の若い人たちは昔よりも総じて優秀だなと思います。昔に比べて芸術に触れられる機会も豊富だし、情報にアクセスしやすいからこそ勉強家が多い。絶えまなくいろんな情報が入ってくるからか、読解能力が高いと感じますね。
外国語習得のためのツールも充実しているし、僕の渡欧当時のように言葉に不自由してコンプレックスを感じることなく、人生を楽しめる人が多いのではないでしょうか。今はひとつの会社や仕事に縛られることが正しい時代でもないし、自分の興味や好奇心にあわせて生き方を何度も変化させながら、楽しく人生を送れる人も増えそうな予感がしています。

── 雨宮さんはご自身に変化を感じますか。
アーティストとして表現していることは、渡欧前から変わっていないんです。僕は人々にとって当たり前に存在するこの現実の世界自体がとてつもなく面白いと思っていて。その当たり前や普遍性に揺さぶりをかけるような作品を制作してきました。たとえば、溶けた林檎の彫刻作品をつくったのは、これを見た人がスーパーの売り場に並ぶ普通の林檎を見た時に「あれ?林檎ってこんな形だったっけ?」と違和感を覚えるような体験をしてほしかったからです。
ただ、表現手段は時代とともに変化していますね。ちょうどベルリンにいたころは、身体表現を用いたパフォーマンス作品が多かったです。それが最近は「テキスト」にフォーカスするようになりました。これはそもそも日本語でも人前で話すことが苦手だった自分が、言語の壁を乗り越えて相手とコミュニケーションを取れるようになった過程にも呼応しています。また、年齢と共に身体能力は衰える反面、言語表現は豊かになっていることも影響していますね。それはつまり、自分の中に蓄えられている“資源”が変化しているということ。今の自分が持つ資源を正しくとらえ、作品制作に反映させていきたいです。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 雨宮 庸介(あめみや・ようすけ)
-
1975年茨城県生まれ。山梨県在住。第15回グラフィックアート『ひとつぼ展』グランプリ。現 公益財団法人江副記念リクルート財団の奨学生として2011年に渡欧し、2013年Sandberg Institute(アムステルダム、オランダ)修了。2014年度文化庁新進芸術家海外研修員(アムステルダム、オランダ)。以降、ベルリンに拠点を構え、2022年に帰国。現在、日本を拠点に活動。
主な個展に『H&T. A,S&H. B&W. (Heel&Toe. Apple,Stone&Human. Black&White.)』SNOW Contemporary、東京(2021)、主なグループ展に『土とともに 美術にみる〈農〉の世界―ミレー、ゴッホ、浅井忠から現代のアーティストまで―』茨城県立近代美術館(2023)、『Reborn-Art Festival 2021-22』日和山公園 旧レストランかしま、石巻(2021)、『りんご宇宙―Apple Cycle/Cosmic Seed』弘前れんが倉庫美術館、青森(2021)など。