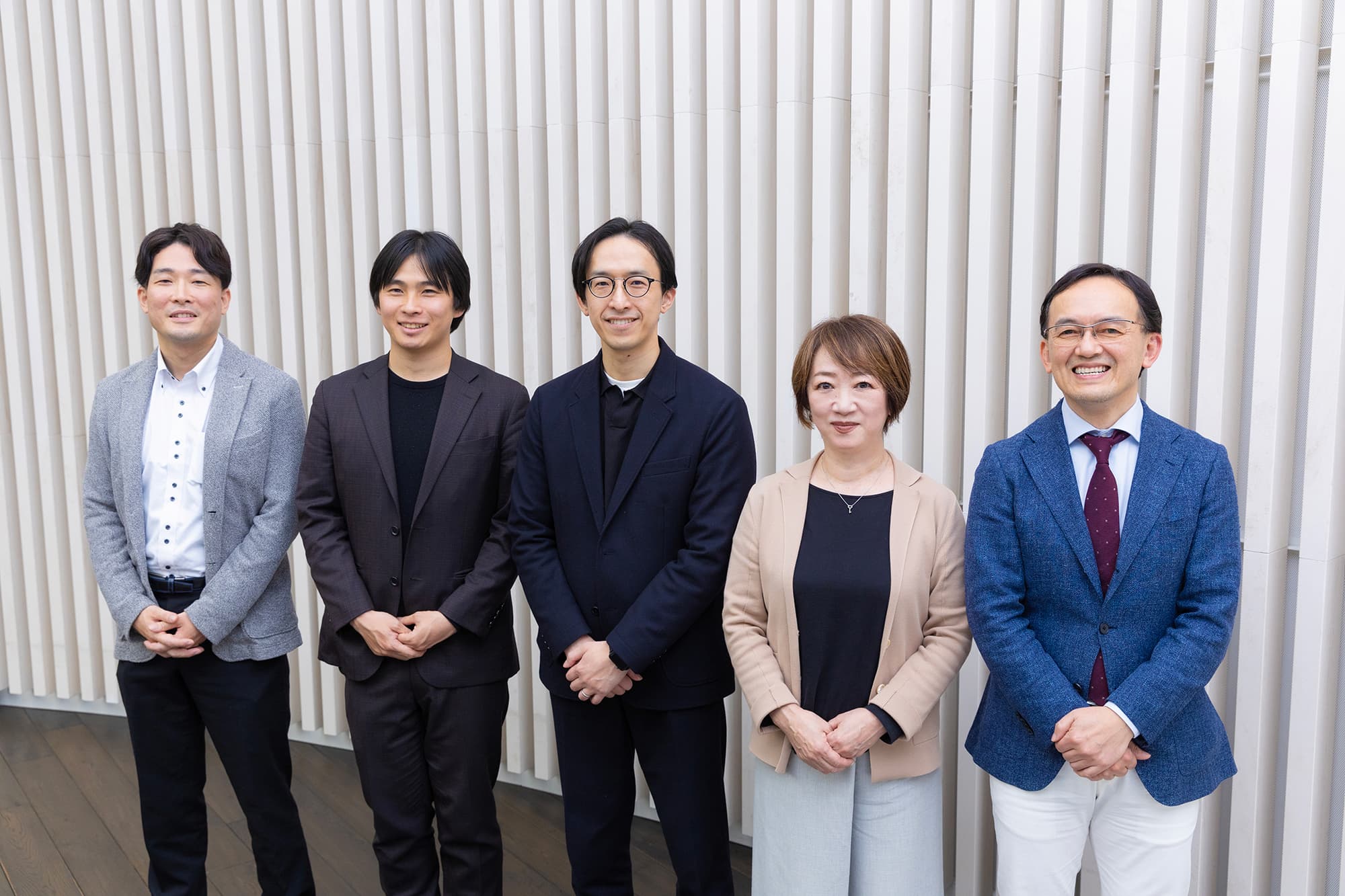メンマが地域を救う!? LOCAL BAMBOO代表 江原太郎に学ぶ、地域課題解決の突破口

地域の生態系に悪影響を及ぼす放置竹林から生まれた商品「延岡メンマ」。国際線ファーストクラスの機内食にも採用されたこの商品の生みの親、江原太郎さんの活動から、地域課題解決の糸口を探る
少子高齢化が進む日本。特に地方は都市部よりもその傾向が強く、過疎地域では「後継者不足による地場産業の衰退」「山林の管理が行き届かないことによる自然災害・害獣被害」といった新たな問題が全国各地で取り沙汰されている。そんな今、宮崎県延岡市の放置竹林問題に取り組んでいるのが、LOCAL BAMBOO INC. 代表の江原太郎(えばら・たろう)さんだ。江原さんは、たけのことして収穫されずに成長した “幼竹”を加工して、ラーメンの具材として知られるメンマを製造。日本で消費されるメンマの99%が中国産というマーケットに国産品の「延岡メンマ」を投入し、ANA国際線ファーストクラスの機内食にも採用されるなど、ご当地ヒット商品をつくりだしている。
地域の“厄介もの”を商品に加工して価値に転換すること自体は、他にも全国で事例が見られる手法だ。そのなかで、江原さんが手掛ける「延岡メンマ」がメディア等で注目されているのはなぜなのだろうか。商品誕生の背景や現在までの道のりを伺いながら、地域課題解決のヒントを探った。
自分がワクワクするやり方で、地域に貢献したかった
― はじめに、これまでのキャリアの変遷について聞かせてください。江原さんは東京農業大学出身で、20代は東京の農業ベンチャーに勤務するなど、農業が興味の中心だったように感じられます。農業との出会いはいつ、どんなきっかけなのですか。
家族の影響ですね。僕の両親は揃って小学校の先生をしていたものの、祖父母が農業をやっていまして。生まれたときは祖父母の家からは離れた延岡市内の中心部で暮らしていたのですが、小学生の途中で祖父母が暮らす山間部に引っ越すことに。そこで、畑仕事が身近になったのがはじまりでした。
― 畑の手伝いをするうちに好きになった、ということでしょうか。
それも農業を志した理由の半分なのですが、もう半分の理由は日本の過疎地域の現実を目の当たりにしたことです。引っ越す前に通っていた中心部の小学校は1学年6クラスだったのですが、転校先は1学年1クラス。人の少なさ、何より子どもの少なさに驚きました。
また、農業の担い手は高齢者が中心。跡を継ぐ下の世代は、少なくとも私の周りでは多くありませんでした。じゃあ、うちの祖父母の畑は今後どうなるんだろうと子どもながらに考えてみると、親は教師の仕事があるから無理だし、姉2人もいずれ家を出るのかなと当時の僕はぼんやりと思った。だったら長男である自分がやらなきゃいけない、なんとかしたいと思ったんです。

― その後大学進学のために上京していますが、卒業後すぐに地元へ戻ろうとは思わなかったんですか。
すぐに宮崎へ帰る気持ちもあったんですよ。ただ、親としては地元に戻って自分たちのように公務員になってほしかったみたいで。もちろん、自治体に就職して農業課や土木課で学んだ知識を活かす道もあったと思います。僕の周りの地方出身者の多くが憧れるキャリアでもあったし、親の気持ちも理解はできました。でも、僕はそれにワクワクしなかったんですよね。自分にしかできないやり方で地域に貢献したい。そのためには事業家を目指した方が自由に動きやすそうだと感じ、ビジネスの現場で農業を学べる、東京の農業ベンチャーに就職しました。
― 就職先で「屋上農園の農園長」を3年務め、その後はインドネシアでの人材事業や環境省との有機農業の普及啓発事業など、多様な経験を積んでいますね。
僕が農場長をやっていた農園はお台場のビルの屋上にあり、そのご縁でフジテレビの企画・イベントに関わらせてもらうなど農業以外のことも学べたのが良かったです。その後、グループ会社に転籍してインドネシアに赴任することに。まったく希望していなかったのですが、「農業ど真ん中から一度離れて、人事や経営などの幅広い経験を積むのも良いな」と思って飛び込んでみることにしました。
帰国後は、小さな規模で良いから自分の責任で何でもやってみたいと、フリーランスに。当時は農業を専門にした若手のフリーランスが珍しく、ありがたいことに複数のプロジェクトに参加する機会をいただいたんです。有機農業の普及啓発事業などを通して広告代理店の方々と一緒に仕事をすることが多く、ブランディングやマーケティングのことを一通り学ばせてもらいました。
自分の体験を個人的な問題で済ませず、地域全体の課題と接続
― 幅広い経験を積んだうえで、30歳を目前にした2019年末に宮崎県延岡市へUターンされました。これは、今の事業(「延岡メンマ」)をやる前提での決断だったのでしょうか。
いえ、その時点ではメンマのことも竹林の問題も頭にはありませんでした。もともと30歳までには地元へ帰ろうと考えていて、このときは東京で携わっていたコンサルティングの仕事を半分宮崎に持ち帰って継続する前提で戻ったんです。地元に貢献する事業を新たに立ち上げたい思いはありましたが、具体的な構想はありませんでした。
― では、なぜ放置竹林に注目したのでしょうか。
かつて祖父母が管理していた畑で有機農業をはじめようと思って現地を確認しに行ったら、畑や山の様子が一変していたんです。山道に竹がびっしりと生えて通れなくなっていたし、畑のすぐ近くまで竹林が浸食していた。伐採するにしても、竹は雑草と違って切るのも運ぶのも大変で非常に厄介でした。
そこで、「この邪魔な存在を処理するにはどうしたら良いだろうか」と、あくまでも自分の畑のために竹のことを調べてみた。すると、僕の困りごとの背景には予想以上に大きな問題が潜んでいると分かってきたんです。竹は、最成長期には1日に1メートル前後も伸びるほど非常に成長が早い植物であること。加えて、軽くて丈夫なことから古来より建材や道具の素材として重宝されてきたこと。しかし、プラスチックなどの新素材の登場により竹の産業は衰退。需要が減り、商売として竹を伐採する機会が大きく減ったこと。追い打ちをかけるように山間部で過疎が進み、山を管理する人がいなくなってしまったこと…。
竹林を放置すると他の植物の成長を阻害してしまい、生態系のバランスが崩れる結果、自然災害や害獣被害のリスクが高まります。また、CO2吸収効率の良い木々の成長が阻害されるため、地球環境にも良くありません。調べれば調べるほど、市内の80%が山林を占める延岡市にとっては無視できない問題だと分かってきた。また、放置竹林は日本全国で増えており、これは社会全体の問題なんだと理解しました。

― 江原さん自身が感じた“厄介ごと”を自分だけの問題で済ませず、地域全体で解決が必要な問題だと捉え直したわけですね。そこから、どうやってメンマに加工して販売するというアイデアに辿り着いたのでしょうか。
前提として、問題を問題のまま処理するのではなく、資源に変えて地域にお金が落ちる仕組みをつくりたいと考えていました。ただ、最初は竹の若芽である「たけのこ」のうちに収穫することを考えていたんですよ。ところが、たけのこ掘りができる時期は1年のうち非常に短く、地中に埋まっている状態ゆえに残さず収穫するのがかなり難しい。おまけにあく抜きなど加工が大変なため、「竹林を管理するため」という目的に照らし合わせると、手間がかかりすぎると断念しました。
そんなとき、福岡で国産のメンマをつくっている会社があることを知ったんです。実は恥ずかしながら、そのときまでメンマの原材料が何か分かっていなかったのですが、たけのこの収穫期を過ぎて地中から伸びてきた「幼竹」を加工してつくっていると知り、これだと思いました。地上に出ている状態で収穫するのなら、土を掘るよりも手間がかからず、効率的に伐採ができます。また、たけのこ農家にとっては、収穫し損ねてたけのことしては出荷できない幼竹をお金に換えることができる。地域のみなさんに恩恵のある形で一緒に課題解決できそうな仕組みが見えました。
しかも、日本のメンマ市場で流通している99%は中国産や台湾産。年間120億円とも言われる市場で、国産メンマのシェアはわずか1%です。国産の存在感がほとんどないからこそ、逆に言えば僕たちにもチャンスがあると思いました。
素材もつくり手も魅力はある。足りないのは営業力やマーケティング
― 「延岡メンマ」は、地域の農家から幼竹を買い取り、製造・加工は延岡市内の事業者に委託。味付けには地元の素材を使うなど、地域一体となってつくられています。ステークホルダーのみなさんとはどうやって協力体制を築いたのですか。
はじめのうちは割と苦労しました。例えば、幼竹の仕入れ。地域のたけのこ生産者の集まりに顔を出して、「規格外のたけのこ(幼竹)を買い取りたい」と説明しても、みなさんは半信半疑。売れないものを買うのだから、農家さんたちにとってはメリットしかないはずなのに、反応は良くありませんでした。「東京から帰ってきた若者が何か不思議なことを言っている」と遠巻きに見られていたようです。
― 新しい取り組みに対して地域の皆さんの腰が重かった、と。
そうですね、地域のみなさんをどう巻き込むかが初期の課題でした。だからこそ僕がこだわったのは、地域に認めてもらえる実績をつくるためのマーケティング活動やブランディングです。
単にラーメン用やおつまみ用のメンマとして販売するのでは価格で海外産に負けてしまうし、差別化ができず市場で埋もれてしまいます。やるべきことは新たな顧客の創造。そこで、放置竹林の問題や国産メンマの価値、食べる意義に関心を持ってもらえそうな人を販売ターゲットに設定することに。「エシカルで丁寧な暮らしをしたい、都会に住む20~30代」に狙いを絞ってEC販売をスタートしました。

「延岡メンマ」のブランドサイトでは、放置竹林の問題を紹介し、「メンマを食べることで延岡の森が育つ」とメッセージを発信。また、メンマ=ラーメンの具という世間のイメージを変えるために、パスタの具材にしたり、トーストやアイスに乗せて食べたりといった、食べ方の提案をしていったんです。
そうやって販売を開始したところ、実際の購買層は狙い通り都会の人たち。新しいものに敏感なメディアの方々にも注目をいただき、テレビ・ラジオなどに登場する機会が早々に訪れました。すると、これまで遠巻きに見ていた地域のみなさんが「テレビに出てたの、観たよ」と次々に声をかけてくれ、「延岡メンマ」に興味を持ってくれるようになった。一気に協力を得やすくなり、生産体制が強化できたんです。
― そこまでのシナリオを想定してマーケティングやブランディングに注力していたんですか。
そうですね、マスメディアの影響は絶大です。「延岡発の取り組みがテレビやラジオで紹介された」となれば、地域のみなさんの認知度は各段に上がるはず。どうやったら番組で取り上げてもらえるかを意識しながら、戦略的に広報活動をしていました。
また、「延岡メンマ」がどれだけ地域や環境に良い商品でも、消費者に欲しいと思ってもらえなければ売れません。“つくりたいもの”と“売れるもの”は必ずしも同じではない。これは一般論ですが、地方は品質の良い資源が豊富だし、長年培ってきた生産のノウハウもあるので、モノ自体は良いのに、それを買ってもらうための営業力が不足していることが多いように感じます。その意味で、僕は東京時代にマーケティングやブランディングに触れてきたことが大いに役立った。「延岡メンマ」をANAの国際線ファーストクラスの機内食に採用いただいたのも、ブランディングの一環で戦略的に売り込んだ結果なんです。
日本中の地域課題を、一次産業で解決したい
― 今現在、「延岡メンマ」はどのような展開をしているのですか。
地域の認知度が上がり、協力の輪が広がったことで、生産体制を拡大。延岡のご当地食品として市民のみなさんに受け入れてもらえるようになった結果、最近はお土産品やギフトとしての販売が売上の中心になってきました。また、延岡市内の学校給食にも提供しており、食を通して子どもたちに延岡や日本の社会課題を伝える機会もいただいています。

― これまでの歩みを振り返ってみて、「延岡メンマ」が成功した秘訣は何だと思いますか。
先ほど話した営業力や地域を巻き込むことに加えて、「失敗しても諦めず続けること」が大事なんだと思っています。小さな失敗なんて数えたらキリがないんですよ。農家さんへのアプローチも最初は断られていますし、初めてメンマづくりにトライしたときは発酵に失敗して廃棄しましたしね。あと、海外展開を狙ってパリに売り込みにいったときも大苦戦。ラーメンブームで絶対に需要があるはずだと思っていたのに、日本産メンマの品質を分かってくれると思って売り込んだ日系のお店では反応が良くなかったんです。でも、このままでは帰れないと他のラーメン店もまわったところ、あるフランス人オーナーが「日本が大好きだからこそ、食材はできるだけ日本産にこだわりたい」と話してくれて。この経験から「日本好き現地オーナー」を海外展開のターゲットに変更。今はドイツのお店にもメンマを卸しています。
― 江原さんは「延岡メンマ」(食品事業)のほか、古民家を改装した民泊事業や、放置竹林に悩む他の地域の活動を支援するコンサルティング事業も手掛けられています。それらをまとめると、江原さんは自分を何屋だと思っているんですか。
僕は放置竹林の問題に出会うまで農業を軸にしてきたんですけど、実は竹って「特用林産物」に分類されるので、竹林に向き合うことは農業ではなくて林業なんです。ただ、その違いは僕の中ではあまり関係なくて。本質的にやりたいことは地域のステークホルダーのみなさんと一緒に一次産業を通じて地域課題を解決していくこと。農業や林業といった一次産業は地方の主要産業でもあるからこそ、この産業を軸に地域の多くの事業者とWin-Winになれる仕組みをつくり、地域に還元していくことが僕の目標です。

プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 江原 太郎(えばら・たろう)
-
宮崎県延岡市生まれ。東京農業大学を卒業後、都内最大級屋上貸し菜園「都会の農園」にて農園長を経験。インドネシアの人材事業、環境省との有機農業の普及啓発事業、BBQ事業を経て2019年に宮崎に拠点を移し"食べもの付き情報誌"の宮崎ひなた食べる通信をスタート。現在は延岡メンマの他、複数の事業を手掛ける