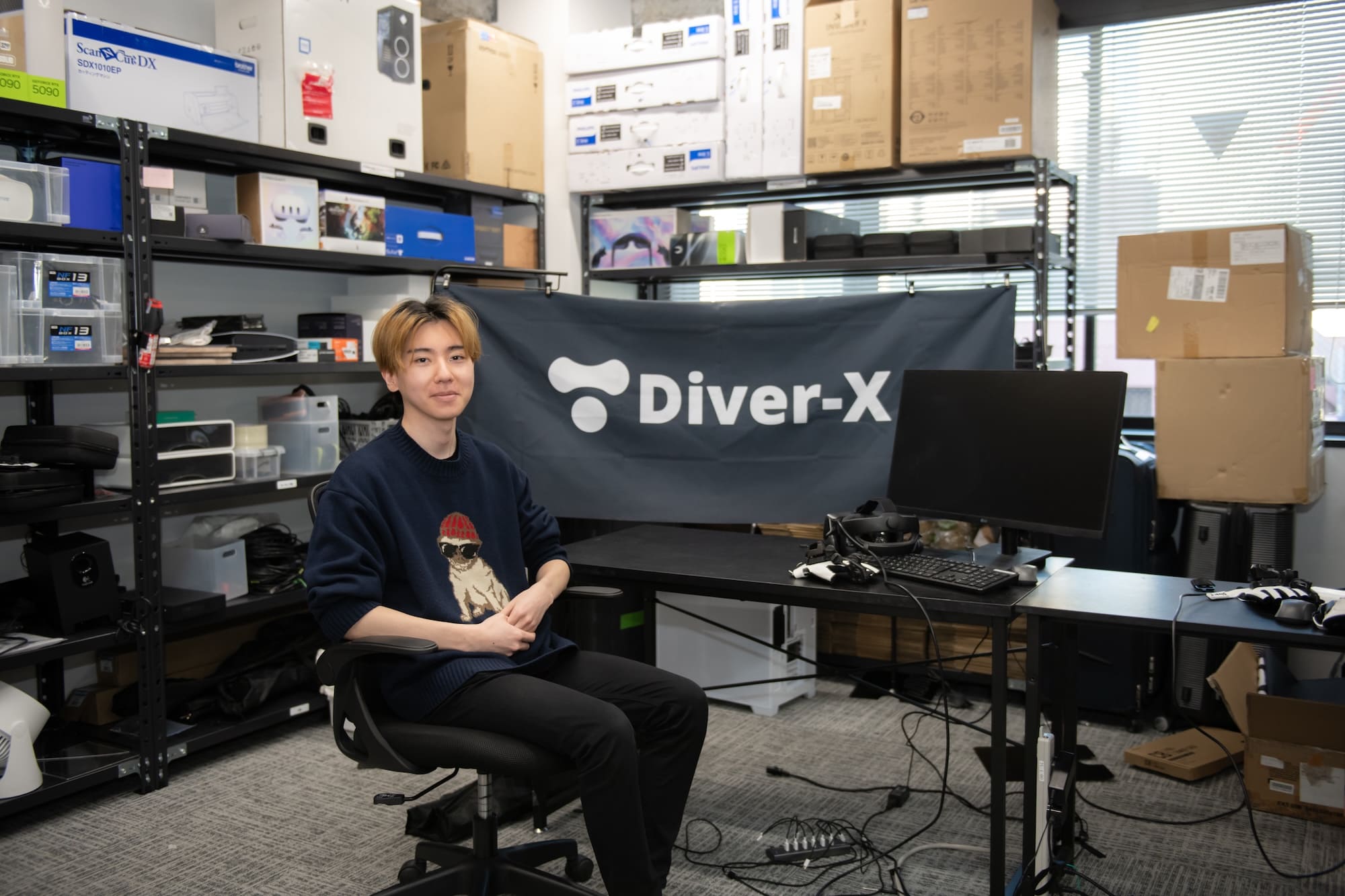都市の微生物にも多様性が必要だ。BIOTA代表 伊藤光平が“今の興味”を積み重ねて辿り着いた、微生物の世界

コンピューターが大好きだった少年は、なぜ都市の微生物多様性を高める研究事業者になったのか。株式会社BIOTA代表の伊藤光平さんが歩んできた道のりから、現代らしいキャリアのあり方を考える
人間の身体には、38兆個もの微生物が生息しているという。その一つひとつを肉眼で見ることはできないが、近年の研究によって人体に様々な影響を与えていることが解明されつつある。私たちは微生物と共に生きているといっても過言ではないだろう。
そんな微生物を、「都市における微生物多様性」というテーマで研究し、事業として展開しているのが、株式会社BIOTA 代表の伊藤光平さん。1996年生まれの27歳だ。人体や自然界に存在するものと比べて、未解明のことが多いという都市の微生物。そのテーマに伊藤さんがあえて切り込んでいるのはなぜなのだろうか。伊藤さんの過去の進路選択やこれまでの活動を振り返りながら、自らの意思でキャリアを切り拓く秘訣を探った。
「やりたい/やりたくない」に素直でいたら、微生物に出会った
─ 伊藤さんはどんな少年時代を過ごしていましたか。
小学校に上がるまでは建築物に興味があって、積み木で建物や街をつくっては壊し、つくっては壊しを無限にやっているような子どもでしたね。その後、小学生になってからはコンピューターにハマっていきました。僕は第一にメカとしてのパソコンの格好良さに惹かれたんです。加えて、インターネットで世界中のいろんな情報にアクセスできることにも面白みを感じました。
だから、どうしても自分専用のマシンが欲しくなって、お小遣いやお年玉を貯めて購入することを決意した。調べてみると、当時流通していたネットブック(インターネット利用に特化し、他の性能を削った安価なパソコン)なら4万円くらいで買えそうだと分かり、比較サイトを徹底的に調べ、半年くらい検討を重ねて購入したんです。
当時の僕が好きだったのは、コンピューターが計算処理をする様子を観察すること。容量の大きなデータの処理を実行させて負荷をかけると、内部で「シュー、シュー」と音が鳴っていることが面白かったんです。そこからハードウェアに興味を持ち出し、中学生になるとパソコンを自作するように。ネットブックよりもスペックの高いマシンが欲しかったけれど、さすがに何十万円もする既製品を買うお金はないし、親も許してくれない。それなら自分でつくるしかないと、CPUやRAMなどちょっとずつPCに必要なパーツを買い揃えていって、2年がかりで完成させました。

─ 中学生までの伊藤さんの様子からは、理工系や情報系の進路に進むように感じられるのですが、そこからなぜ微生物を研究するようになったのでしょうか。
僕の地元、山形県鶴岡市には、慶應義塾大学の先端生命科学研究所という施設があって、中学生のときに見学に行く機会があったんです。でも、その時点ではサイエンスに興味があったわけではないし、実験を行うラボを見ても特に面白いとは思わなかったんですよ。正直に言えば、「なんだかよく分からないところだな」と思ったくらいだったのですが、当時所長を務めていた冨田勝教授の話が、科学に足を踏み入れるきっかけになりました。
実は当時の僕は何のために学校で勉強をしてテストで良い点数を取らなければならないのか、納得いっていなかった。それよりも、家でコンピューターに向き合うことに没頭したかったから、あんまり学校には行っていなかったんです。だから、高校進学にも前向きではなかったんですが、そんなときに富田先生から「勉強は手段。大学に入るための勉強じゃなくて、自分のやりたいことのために勉強があるんだよ」と言われて、たしかにそうだなと考えが少し変わりました。
でも、頭では理解できても積極的には学校に行きたくないわけです。そこで目をつけたのが、研究所で高校生を対象に“特別研究生”を公募していたこと。最初は居心地の悪さを感じていた学校を抜け出す理由にもなりそうだと、サイエンスの世界に飛び込みました。
─ このときは「やりたくない」を回避するための手段だった、と。
そうです。後になって自分の興味ともつながっていくのですが、微生物の研究をはじめたのも、たまたま僕のメンターになってくれた方が微生物研究をしていたからなんですよ。
都市における微生物の生態系を解き明かし、その多様性を高めたい
─ 伊藤さんは先端生命科学研究所で皮膚の常在菌について研究し、「アトピーの海水治療の科学的根拠の解明」にも取り組んでいます。その後は慶應義塾大学環境情報学部(SFC)に進学していますが、研究所での活動が縁だったのでしょうか。
研究所での活動を通して大量のデータをコンピューターで解析していくバイオインフォマティクスに出会い、この分野にもっと没頭したいと思うようになりました。富田先生から「研究を続けたいなら大学へ行きなさい」とアドバイスをいただいたものの、当時ほとんどの大学で研究室に入れるのは3年生から。僕は大学進学後すぐにラボに入って研究を続けたかった。それができるところを探したら、必然的に志望校が決まった感覚です。
─ 大学進学後も微生物研究を続けていた伊藤さんが、「都市の微生物」というテーマにたどり着いたのはなぜですか。
大学1年生のときに、米国コーネル大学のクリストファー・メイソン教授が行ったニューヨーク地下鉄のゲノム調査に関する論文を読みました。論文によると、採取できたDNAのうち半分は未知のもの。人工的につくられた都市に、人類が解明できていない存在が半分もいるという事実が、めちゃくちゃ面白いなと思いました。それに、これまでの微生物研究の対象は人の身体や自然環境が中心。都市を対象にした論文はほとんど目にしたことがなくて…。それなら自分がやってみたい、知りたいという気持ちが一番でした。

─ まだ研究が進んでいない未開拓の分野だからこそ、大変な面も多かったのではないですか。
たくさんありました。例えば自分ひとりの力では調査が進まないこと。都市の微生物を調べるにはいろんな場所でDNAを採取しなければならないので、所属していた研究室に協力してもらったり、友人たちを巻き込み「GoSWAB」という学生団体を立ち上げ活動したりしていました。
また、都市という性質上、採取にはその場所・施設の持ち主の許可が必要。でも、研究を始めたばかりの頃は嫌がられることが多かったですね。ハードルになったのは微生物=不衛生というパブリックイメージ。本来、微生物は目に見えないだけで人の生活に身近な存在なのですが、人に有害か無害かに関わらず微生物自体が検出されることを懸念する声も多かった。だからこそ、公共施設の管理者など都市のステークホルダーのみなさんにお会いし、自分たちの活動に共感してもらえるように対話を続けることも必要でした。
─ 伊藤さんが行っているのは、単に都市の微生物を明らかにすることだけでなく、「都市の微生物多様性を高めること」です。都市環境で微生物が多様性に富むと、何が良いのでしょうか。
例えば、「皮膚、腸内、口腔内で、特定の微生物が増殖もしくは減少して多様性が損なわれると、疾患が起きやすくなる」といったように、人体において微生物の多様性が重要であることは広く知られています。それと同じことが都市にも言える。例えば過度に除菌・殺菌された空間に感染症の原因となる菌が入りこむと、その菌の競合となる存在がいないため爆発的に増殖し、集団感染を引き起こすリスクがあります。
逆に、多様な微生物がバランスよく存在する空間では、爆発的な増殖は起こりにくい。多様性の価値って人も微生物も本質は同じなんですよ。今、人間の世界で多様性が推進されているのは、似たもの同士が集まっている集団は考え方が偏りがちで時代錯誤に陥りやすいリスクがあるからですが、都市環境も特定の微生物だけが偏って存在する状態より、多様な微生物が集っている状態の方が健全。感染症やアレルギーの抑制なども期待できるからこそ、微生物多様性には、公衆衛生を向上させる意義があると考えています。
とりあえずやってみる。目的より手段を楽しむ。メタ認知をやめる
─ 大学卒業後、伊藤さんは株式会社BIOTAを始動させました。研究者のキャリアとしては、学部卒業後は大学院で修士過程→博士課程と進むことが一般的なのに対し、なぜ起業という道を選んだのでしょうか。
一番の理由は、自分のやりたい研究を自分の責任で実現するためです。アカデミアの研究者としてそれなりの予算をつけてもらうには、博士号を取って論文で評価されないとなかなか難しい。でも、自分は学部4年の時点で7年研究を続けていたのに、そこから博士課程を修了するまでにはミニマムでもあと5年かかります。それなら僕は、学校を出て自分の力で予算を集めて研究を続けようと思った。都市をクライアントにして、調査・コンサルティング費用をいただいて研究した方が、自分のやりたいことができると考えました。
─ BIOTAでは微生物多様性というテーマを、具体的にどのような事業にひもづけて展開しているのですか。
主に行っているのは、クライアントから依頼を受けて空間の微生物調査をする事業です。他には、生活空間の微生物多様性を高めるための植栽・建築設備などの提案も行っていますし、酒造メーカーなど元来から微生物の力を活かしている事業者の方々との共同研究も行っています。また、微生物との共生、微生物多様性の重要性を啓蒙するべく、ワークショップや講演会も実施。2022年には日本科学未来館の展示「セカイは微生物に満ちている」の監修も務めました。

─ 伊藤さんの現在の活動やここまでの道のりは、伊藤さん自身のどんな行動や価値観によって実現していると思いますか。
これまでの僕の決断には特別深い理由があったわけじゃないんです。いつも、“目先の興味や好奇心”を満たすために行動していた。将来を見据えて行動するのも大切かもしれませんが、今の自分が楽しいかどうかも大切じゃないですか。あれこれ深く考えて悩むくらいなら、とりあえずやってみる。そうやって自分が興味のあることを積み重ねていたら、今の活動にたどりつきました。
もうひとつ大事にしているのは、目的を実現するまでの手段や過程を楽しむこと。目的の達成を優先するあまり手段を選ばないようになると、楽しくないこともやらなければならなくなり、取り組み自体の継続が怪しくなると思うんです。その意味で、今の僕は都市の微生物多様性というテーマに対して、自分が大好きだった、研究・建築・ランドスケープ・アートといった手段でアプローチしています。
─ いずれも楽しめるかを大事にし、楽しめるようなアプローチ・行動を選んで来られた。
あとは「メタ認知」、つまりを客観的に考えようとしすぎるのをやめてみることですね。今の時代は、「人からどう思われているか」といった客観性を必要以上に気にしすぎているように思います。でも、どこまで相手の立場に立って考えても、本当のところは本人にしか分からない。そういった不正確なものに惑わされるくらいなら、自分の主観を信じた方がいいと思うんです。
─ SNSやレビューサイトへの書き込みなど、現代は絶えずいろんな意見が飛び交っている時代ですから、伊藤さんのように他人の評価に振り回されすぎない意識は大切なのかもしれません。
インターネットはフィードバックのスピードを劇的に速め、参考になることも多い一方で、真新しいことをすればすぐにSNSで批判に晒されがちなのが辛いところですよね。でも、少なくとも身近な人たちは、好きなことに熱中してご機嫌でいる自分の様子を見て、悪い気持ちはしないはず。それで十分じゃないですか。知らない誰かの意見に過敏に反応せず、ひとまず“自分の中で発酵させてみる”ことも時には必要だと思います。
─ では、そんな伊藤さんが自身の活動を通して実現したいことを教えてください。
都市の微生物多様性を真の意味で実現するには、都市開発のあり方や人々の意識・行動から変えていく必要があり、10年や20年というレベルで大きく何かが変わるとは思っていないんです。むしろ、短期間で激しい変化を起こそうとすれば、いたずらに生態系のバランスを崩しかねません。ゆっくりと、人々が変化を感じないくらいのスピードで変えていくことが理想。僕が生きている間には理想の都市環境にはまだ届いていないかもしれませんが、自分の活動がその変化の一助になれたらいいなと思っています。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 伊藤 光平(いとう・こうへい)
-
慶應義塾大学先端生命科学研究所にてマイクロバイオームを対象としたバイオインフォマティクス研究に従事。ヒトだけでなく都市や建築物における環境マイクロバイオームも対象とした。大学卒業後、株式会社 BIOTA を創業