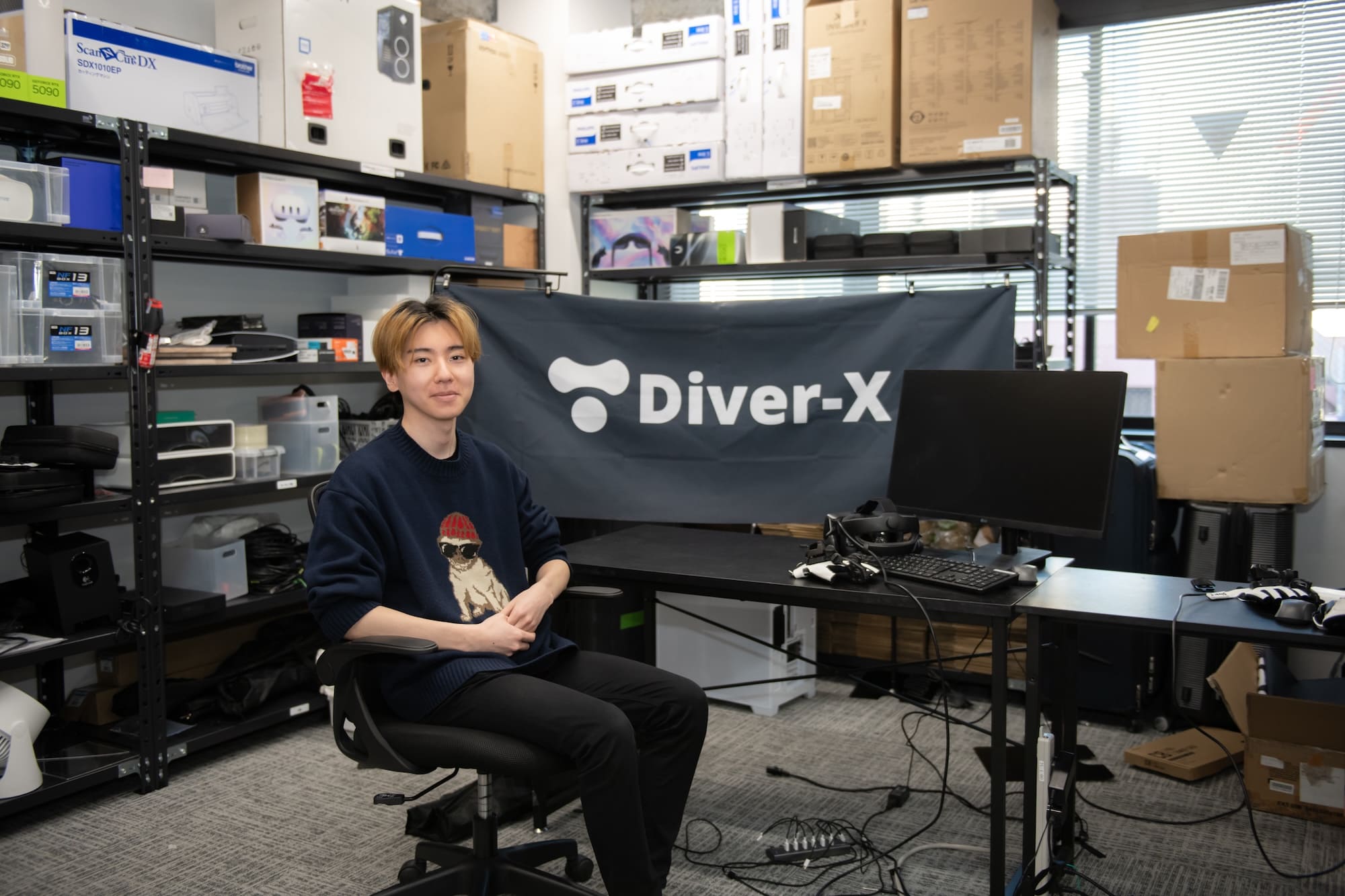「言葉にならないこと」を映像で伝えてきたアーティスト 小林颯が再考する「おしゃべり」の価値

ベルリン在住のアーティスト・映像作家、小林颯さん。近作では“言語”や“語り”をテーマにしている小林さんと、言葉やコミュニケーションが多様性社会を生きる私たちにもたらす影響を考える
2020年に第24回文化庁メディア芸術祭アート部門新人賞を受賞。翌年にはForbes 30 Under 30 Asia 2022 The Arts に選出されるなど、各界から注目を集めているアーティスト、小林颯(こばやし・はやて)さん。1995年生まれの小林さんは、“装置と映像”を創作活動のフィールドとしながら、近年は「言葉」や「対話」について再考する作品を発表している。
2021年のコロナ禍にドイツのベルリンへ渡り、現在もドイツを拠点に活動する小林さんが、言葉やコミュニケーションを題材にした作品に注力しているのはなぜなのだろうか。2024年6月より東京で開催する個展「ポリパロール」にあわせて来日中の小林さんに、活動の源泉や背景にある思いを聞いた。
頭の中のイメージをより正確に表現するための、映像という手段
─ はじめに、小林さんの創作活動の原点を教えてください。
きょうだいの影響もあって、もともと美術には興味があったんです。自分は4人きょうだいの末っ子で、他の3人も現在はWebデザイナー、アパレルデザイナー、エンジニアをしているような、クリエイティブ志向。そんな家庭環境のおかげか、小学生の頃から漠然と美大に行きたいと思っていました。
でも、当時美大に通っていた年の離れた兄に「“同級生の中で一番絵が上手い”くらいのレベルじゃないと入学できないよ」と言われて……。絵を描くのが特別上手いわけではなかった自分が、この道に進むのは厳しいのかなと思っていました。
─ 芸術の道を諦めかけていた小林さんが、映像という手法にたどり着いたのはどんなきっかけなのですか。
小学6年生のときにNHKで放送していた「デジタル・スタジアム」という番組を偶然観たのが、メディアアートとの出会いになりました。番組は、一般公募されたデジタルアートをプロの作家が批評するというもの。登場する映像作品を眺めるうちに、絵が上手くなくてもデジタル技術を使えば自分も作品が作れるかもしれないと思い、見よう見まねで撮影と編集をしてみたのがはじまりです。
最初につくったのは、“コマ撮り”の映像でした。家にあったデジタルカメラを使い、布団の上でみかんを少しずつ動かしながら撮影。その静止画を編集ソフトでつなぎあわせて、「みかんがサッカーをしている様子」を表現しました。
─ そこから映像制作に熱中していったのはどうしてなのでしょうか。
ひとつは、純粋に表現手段として好きになったこと。撮影と編集次第で現実には見られないようなヘンテコな映像がつくれることが面白いと思いました。また、そうやって自由自在につくれるからこそ、自分の頭の中にあるイメージを、限りなく近い形で表現できるのも映像にハマっていった理由。夢の世界のような抽象的なイメージを、言葉にして正確に相手に伝えるのは難しいじゃないですか。でも、映像なら上手く言葉にできない造形や動きも表現することができる。そこに面白さを感じました。
─ その情熱は消えることなく、大学では慶応義塾大学 環境情報学部でメディアアートを専攻。その後東京藝術大学 大学院に進学しています。小林さんはこの時期に、映像を作るだけでなく様々な“装置”を映像に登場させるという作風を確立していますが、これはどんな意図があるのですか。
新しい映像表現を探求するなかでたどりつきました。発端は、映像を映すプロジェクター自体も動かしたいと思ったこと。制作した映像の内容とプロジェクターの動きをリンクさせて、作品の世界を拡張させたかったんです。
あとは、“VRへの反抗心”もありましたね。自分は普段メガネをかけているから、VRのヘッドマウントディスプレイが上手く装着できなくて……。かつ、VRで表現されるスマートな仮想現実よりも、ちょっと不器用に動く装置の方が自分はリアルに感じられた。より現実味のある映像体験を模索して、装置をつくるようになったんです。
日本でもドイツでも、常に抱えていた「よそ者」の感覚が作品に
─ 小林さんは東京藝術大学 大学院を修了後、2020年にはベルリン芸術大学 大学院に留学しています。ドイツに渡ったのはなぜですか。
興味のある分野を学びながら、自分が表現したいことを見つけるためです。ベルリンには以前旅行で訪れたことがあったのですが、ZINE(自主出版の冊子)をたくさん扱う個人経営の書店があるなど、個人が尊重される形で社会とつながっている雰囲気が心地よかった。ここでなら自分がアートを通して探求したいテーマが見つかる気がしました。
また、これは個人的なことですが、クィア(編注:既存の性のカテゴリに当てはまらない、当てはめられたくない人々の総称)である自分が受け入れられる場所に行きたかったんですよね。自分は日本に暮らしていた頃、いつ・どこにいても“よそ者”の感覚があった。その原因はひとつではないけれど、自分の中にあるクィアネスがもたらす疎外感も確実にあったんです。同性婚が認められたドイツなら何かが変わるかも、という期待がありました。

─ 実際はどうだったのでしょうか。
行ってみると、自分が移民として扱われるようになり、これまでとは違う意味で“よそ者”の感覚を味わいました。それは空港に降り立ったときからさっそく感じたこと。非EU圏のパスポートを持つ人用の入国審査のレーンに長蛇の列ができてうんざりしていると、隣でEU圏の人たちがさらっと通過していて、自分がよそ者である事実を突きつけられたようでした。また、残念ながら街を歩けばアジア人差別を受けることもある。そういう出来事が積み重なるうち、防衛本能のように自然と「ひとりごと」が増えていきました。
このひとりごとは、一般に想像するような小さなつぶやきが口から洩れるレベルではなく、街を歩きながら結構な声量で日本語をしゃべるというもの。どうせ誰も分からないからと、「今日の夕飯はポトフにしようかな」といった周囲の人にはまったく意味のない言葉をベルリンの街中で話すことにハマっていきました。
─ まさしく、異なる言語環境に飛び込んだ“よそ者”にしかできないことですね。
そうなんです。こうしたことを繰り返しているうちに関心を持ったのが、言語そのものや、母語とは異なる言語環境に身を置くことが、人のアイデンティティに与える影響について。例えば、ドイツ語を話しているときの自分は日本語を話すときよりも、少し気性が荒くなる感覚があります。それは、ドイツ語特有の濁音が多用される感じや、堅い響きの音節が連なっている単語が多いことも関係していそう。そうした体験がもととなって、「エクソフォニー(母語の外に出た状態)」や「移民」をテーマにした作品をつくるようになりました。
「おしゃべり」は、分からないものを分からないまま受け入れてくれる
─ 2024年6月26日より東京で行われる個展のタイトル「ポリパロール」は、小林さんの造語だと聞きました。これはどういった意味なのでしょうか。
ポリ(poly-)は「複数の」、パロール(parole)は「個人が特定の場で行う発話行為」という意味です。自分がドイツでつくってきた作品たちを改めて見返してみると、言語の違いを起点にした作品や、複数の人が発話しあう“おしゃべり”を作品に昇華させたものばかりだなと思い、このタイトルをつけました。
例えば、2020年から22年にかけてつくってきた《dailylog》は、身の回りに起きた日々の出来事を自分がただつらつら話す映像群。ちょうどその頃はコロナの影響で自由に国の行き来ができず、自分も留学初期は日本からオンラインで授業に参加していたんです。そうした状況に苛立ちを感じつつも、しばらくしたら学生ビザというカード1枚を持っているだけで国を越えられたのが、なんとも奇妙でおかしくて。そういった、ドイツで暮らす移民としての自分のつぶやきを記録していきました。
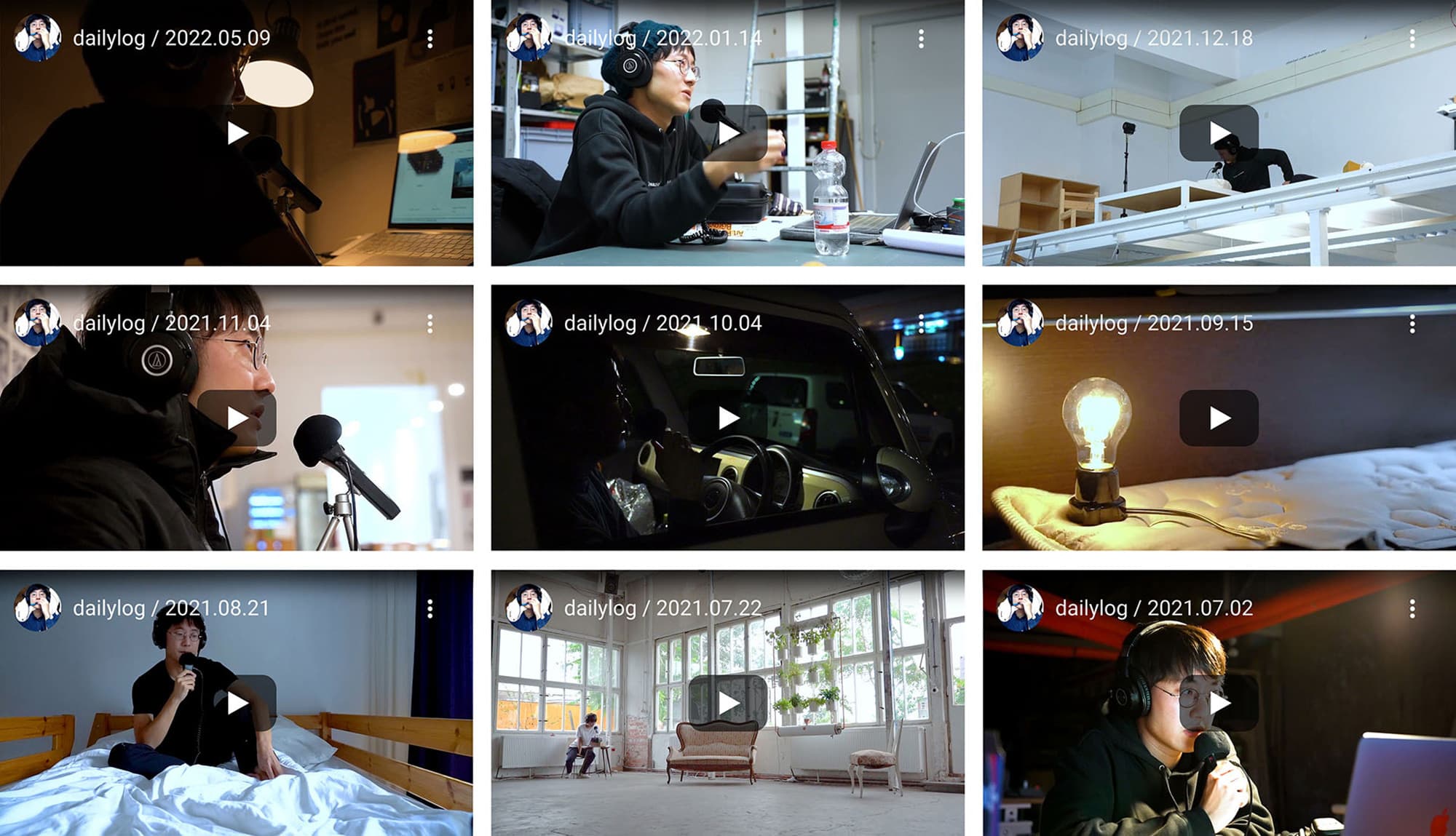
また、《つぎはぎの言語》という作品は、ベルリンに亡命した中国四川省出身の詩人、廖亦武(Liao Yiwu)さんへのインタビューをもとにした作品。廖さんは中国語しか話せないので、通訳を介しての対話だったのですが、廖さんから出てくる言葉を聞いていると、自分は全く中国語が分からないのに、なんとなく話している意味が分かる気がしたんですよ。
それは同じ移民として共感できたからかもしれない一方で、留学生の自分と亡命者の廖さんでは国境を越えた背景が違いすぎて、安易に分かったつもりになるのも失礼な気がした。そんな風におしゃべりという行為から湧き出てくる発想を作品に発展させています。
─ 振り返ってみると、小林さんの創作活動の原点にあるのは、「言葉にならないものを伝えていくための手段」としての映像制作でしたよね。それが現在は、むしろ言葉を探求しているように感じられます。Podcastなど、映像という手法を飛び出した音声作品も制作されている。この変化はなぜなんですか。
たしかに子どもの頃はどちらかというとコミュニケーションは苦手な方で、今でも得意とは言えません。ドイツの友人からも「お前はめちゃくちゃシャイだな」と言われています。ただ、ドイツ語や英語など様々な言語に触れるうちに、イメージと言葉の関係性に興味を持ちはじめたんですよね。
例えば同じ物でも、言語によって全く呼び名が違うこと。日本ではただの「木の板」がドイツのホームセンターでは「飛行機板(Flugzeugsperrholz)」という名前で売られていました。きっと飛行機の翼をイメージしてつけた言葉が一般化したんだと思います。日本では木の板を見ていきなり飛行機を連想する人の方が稀じゃないですか。そうした違いが面白いなと。
─ 言葉だけでなく、「おしゃべり」という行為にも小林さんのこだわりを感じます。
コミュニケーションをもっとカジュアルにしたい気持ちはありますね。自分はアーティストにつきまとう、ある種の高尚さや排他的な雰囲気に抵抗したい意図もあって。そういう空間での会話は、自分が分からない内容が出ても分かっているふりを装ってしまいがちじゃないですか。「おしゃべり」はその真逆に位置するコミュニケーションのスタイルだと思うんです。分からないことを分かんないよと言える場、自分が思っていることを素直に吐露できて、受け入れてくれるのが「おしゃべり」なのかもしれないと思って、作品のモチーフにしています。
─ 小林さんが作品を通して世に発信していることも、主張というより「おしゃべり」くらい感覚なのですか。
たまに強めに主張しているものもありますよ(笑)。ただ、基本的にはおしゃべりのトーンですね。人の「不安定さ」や「弱さ」をそのまま肯定してくれるのがおしゃべりの魅力。他愛もない会話を聞いたり、話したりすることが自分に気づきを与えてくれるからこそ、自分は対話や議論ではなく、おしゃべりを大切にしたいです。

プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 小林 颯(こばやし・はやて)
-
1995年北海道生まれ。ドイツ・ベルリン在住。東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。公益財団法人江副記念リクルート財団 アート部門 リクルートスカラシップにより渡独。2024年にベルリン芸術大学大学院アートアンドメディア科修了。器として映像を捉え、自作の装置から新たな語りの形を探る。近作は、翻訳とアイデンティティの観点から、装置、映像、詩作を通じて、エクソフォニーと語りについて再考している。2020年制作の《灯すための装置》が第24回文化庁メディア芸術祭アート部門新人賞を受賞。Forbes 30 Under 30 Asia 2022 The Arts に選出された。