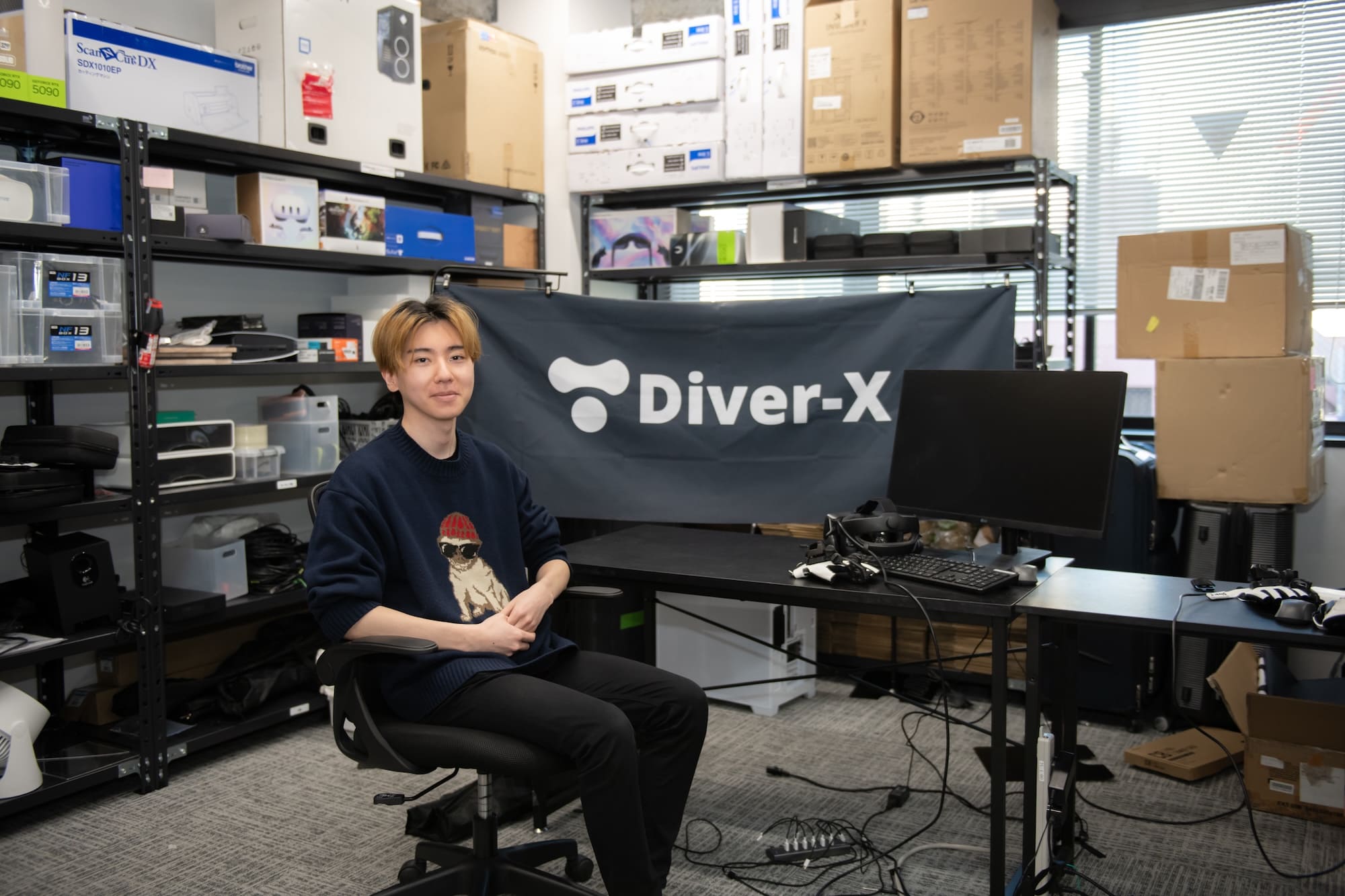リクルートを新卒2年目で退職。20代で出戻ったキャリア観とは?

リクルートでは、「アルムナイ」という言葉が一般的でなかった時代から、出戻り従業員(再入社者)はごく自然にいました。 2021年からは会社を「公園(通称:CO-EN)」のような「出入り自由」な場にしたいと標榜し、実際に2022年度には約30人の再入社者を迎えています。
リクルートに新卒入社後、20代のうちに複数社を経験し、出戻った従業員のキャリア観とは? 現在、プロダクト事業本部で「Air ビジネスツールズ」のプロダクトデザインに従事する郭 桐、同じプロダクトでマネジャーを務める横井 悠のふたりに話を聞きました。
なぜリクルートに戻ってきたのか
― おふたりはリクルートに新卒入社後、20代のうちに出戻ったと聞きました。経緯を教えてもらえますか?
横井 悠(以下横井):2016年にリクルートに新卒入社し、プロダクト企画職としてサロン向け予約顧客管理システム『SALON BOARD』、「Air ビジネスツールズ」のUXデザインに従事した後、2017年に退職しました。その後、PdM(プロダクトマネージャー)として、スタートアップ企業2社で、toCのアプリ立ち上げや、フィンテック領域でSMB(中堅・中小企業)向け業務支援SaaSに携わるなど、プロダクト開発に取り組んできました。
出戻りのきっかけは、3社目にいる時。ちょうどコロナ禍で市場が大きく変化し、プロダクトの生存競争が厳しさを増すなか、自分のキャリアを改めて考えていました。その時、リクルートの元上司から「『Air ビジネスツールズ』のプロダクトを、toC・toBともに増やすフェーズ」と聞いて。まさに自身の経験を活かしながら新しい挑戦ができるタイミングだと考え、2021年に選考を受け、出戻ることを決めました。
※1:“Business to Consumer”の略称。企業が一般消費者を対象に行うビジネス形態のこと
※2:“Business to Business”の略称。企業相手に事業や商取引を行うビジネス形態のこと
― リクルートの事業の方向性に、自分の経験が活かせるタイミングだったんですね。もし状況が違っていたら、それでも出戻っていたと思いますか?
横井:その場合は戻っていなかったかも…。元々、リクルートにはカルチャーフィットを感じていたので、いつか戻りたいと思う可能性はあったものの、一番の判断基準は「自分のWill(実現したいこと)・Can(できること)と合致しているか?」ということでした。
スタートアップ企業では、少ない人数でさまざまな職種機能を全方位的にカバーする必要があります。私はキャリアの早い段階から、プロダクトのデザイン、マーケティング、営業など、さまざまな機能を経験してきた自負があったので、当時のタイミングであれば、経験を活かした挑戦ができると思いました。

― 郭さんが、出戻りを決めた経緯も教えてください。
郭 桐(以下郭):私は海外の大学で金融工学を専攻した後、2019年10月に海外採用枠で新卒入社し、人事としてエンジニア職の新卒採用を担当しました。入社2年目の2021年に退職し、外資系金融事業会社の香港支社に転職し、トレーダーとして勤務しました。
戻ったきっかけは、金融市場の俯瞰視点から事業会社の立ち位置を捉え直したことで、改めて取り組んでみたいことが出てきたから、です。
― 取り組んでみたいこととは?
郭:金融市場では、例えば日本の株式の取引だけでもおおよそ1日で3兆円〜5兆円が動きます。そのダイナミズムを感じられる仕事はもちろん面白かったのですが、構造を紐解いていくうちに、その経済活動を支えている一つひとつの企業の事業を活性化することに改めて興味が湧いてきました。
― ふたりとも、退職後数年で出戻りしています。正直、すぐ出戻って気まずくはなかったのでしょうか?
横井:いえ、当時の上司や同僚に自己開示しきっていて、自分の性格は知り尽くされていたので、実家に戻ってきたような不思議な感覚です(笑)。
特に上司のことは当時からずっと尊敬していて、PdMとしてキャリアに影響を与えてくれた人でした。クライアントへのヒアリングの際は先入観を一切持たず、先方の弟子になったつもりで全てメモを取りながら聞いているような、とにかく現場接点を大事にする姿が印象的で。退職時にも挑戦を後押ししてもらいましたし、その後も近況報告をかねて、よくご飯に付き合ってもらいました。出戻り時も自身のやりたいこと、これまでの経験が今のリクルートで活かせると双方で腹落ちできていました。
郭:私も元上司と定期的に連絡を取っていて、胸襟を開いて話せる関係だったのは同じです。ただ、私の場合は「1年で出戻るなんて、考えが甘い」と真正面からフィードバックを受けて…。そのフィードバックも理解しましたが、自分のなかで戻りたい理由が明確にあったので、選考のなかで真摯に話して、認めてもらった形でした。

そもそも、なぜ入社2年目でリクルートを辞めたのか
― ふたりとも、新卒入社2年で退職ってなかなか早いですよね。なぜ辞めたのか気になります。
横井:当時手伝っていた友人のスタートアップで資金調達が決まったんです。大手がまだ参入していない領域だったこともあり、思い切って挑戦するなら今だ、と思いました。
あと、当時はよりスピード感が求められる開発をやってみたいと純粋に思っていました。今振り返ると他にも大事なことがあると思うんですが …(笑)。「5年、10年経てば、社会はテクノロジーの力で何もかもが変わってしまう。ならば、とにかく先回りしてプロダクトを創らなければ… 」なんて焦りもありました。
リクルートのプロダクトは、大規模ゆえにメンバー視点では計画上既に決まっていることも多く、その打ち手として何か機能を開発するにしても、さまざまな社内関係者のレビューを通しながら連携を取っていく仕事の進め方です。正直自分の思い描いていた理想とのギャップを感じる時もありました。
― そのギャップは、スタートアップに転職したことで払拭されたのでしょうか?
横井:いいえ、むしろ長い時間軸で構えて戦略構築や開発を行うことが、理に適っている側面もあると納得しました。というのも、その転職1社目では、AR技術を使った to Cアプリを開発していたのですが、プロダクトの開発スピードと、市場や事業が拡大するスピードは必ずしも比例しない、と身を以て実感したんです。
当時、新技術だったARへの期待値は高く、一般カスタマーに「ARグラス」が普及し、日常で「現実を拡張した世界を楽しむ」光景は、数年のうちに訪れるのではないか、と考えられていました。ですが、実際のプロダクト化にあたっては技術的障壁が高く、ビジネスの市場として成熟するにも時間がかかる。瞬発力が全てではないんですよね。
郭:なんだか共感します…。若手の時に「テクノロジーで社会が急速に変化する」と期待値が高いのは、よくある感覚だと思うんですよね。でも、実はプロダクトをリリースし、価値提供することだけで出せるインパクトは限定的。
横井:インパクトが大きいプロダクトを創るために、一定は長い時間軸で戦略を考える必要があるのは、どの事業会社でも同じこと。リクルートのITプロダクトは、市場で後発のものもありながら、多くのクライアントやカスタマーにご利用いただけるものを創り続けています。スタートアップを経験した分、このプロセスから学ぶものも大きい気がします。
― ところで、郭さんの退職経緯は何だったのでしょうか?
郭:元々大学で金融工学を学んでいましたが、新卒では「専門を活かすより、まずはキャリアの選択肢を広げることを優先したい」という理由でリクルートに入社しました。
ファーストキャリアとしては期待通りの環境でしたが、となると欲張って「金融工学を考えるのも好きだったな」と思い出すようになって…。
次第に「自分の大事な専門性を、直接活かさないままで良いのか?」と迷いが出てきた時、偶然、証券会社の海外支社立ち上げメンバーとして働くオファーをいただいたので、「第二新卒の今が最後のチャンス…」と思って飛び込むことにしました。

出戻りを経て、どんなキャリアを歩みたいか
― 郭さんは、好奇心に突き動かされて転職をした印象ですが、出戻りを経てご自身のキャリア観はどう変わりましたか?
郭:今振り返ると、最初の転職に関して好奇心はもちろんのこと、「経験や強みを活かさなければ」という焦りもあったのかなと…。
― 焦りとは?
郭:当時社会人2年目で「自分の強みを活かして、早く成果を出したい」ということばかりに目が向いていて。でも、転職後に好奇心をど真ん中に据えた仕事をやっていくうちに、自分へのベクトルが消えて、目の前のことに向き合い、純粋に面白がれるようになりました。すると、次の好奇心が湧いてきて、出戻りも然りですが、おのずと次のキャリアにつながっていくものなんだな…と体感しています。
― 横井さんは、出戻り後にキャリア観はどう変化しましたか?
横井:再入社後は3年、「Air ビジネスツールズ」のプロダクトのグロースに取り組んできました。そのなかでひとりでできることに限界を感じ、自然と「マネジャーとして組織を率いてもっと大きな価値を出せるようになりたい」と考えるようになり、2024年からはグループマネジャーを引き受けています。
組織を率いるという意味では、プロダクトを創るメンバーの採用や育成にも積極的に関わりたいという気持ちが芽生えてきました。というのも、自分も若手のうちにいろいろと悩んで辞めたたちなので、メンバーには自分なりの意義を持って楽しく働いて欲しい。
自分も一度出て体感しましたが、キャリアは自分が思っているより意外と選択肢があるもの。「ここにいなきゃいけない」なんて絶対的な理由はないという前提を持っていれば、気が楽になったり、自分にとって内発的な挑戦をしやすくなると思うんです。

― キャリアへの焦りが落ち着いて、心に余裕ができた今、挑戦したいことは何ですか?
郭:やっぱり私は経済活動を分析するのが好きなので…(笑)。今の資本主義の理論では、お金の総量が増え、流通する速度が高まるほど、人が幸せになるという前提に立っています。では、多くのお店の決済を扱うリクルートが、今後、よりクライアントの幸せに貢献するには、どんなアプローチを志向するとよいか? 自分の担当プロダクト、『Airペイ』でできることは何か? を考えています。
― 面白いですね。詳しく聞かせて下さい。
郭:ここからは私の妄想ですが。例えば、海外の業務支援SaaS業界では、「1クリックで、1週間後にはタイムリーに給与支払いが行われ、手元で資産化できる」トレンドが生まれています。でも、雇用慣習が異なる日本で同じことをやっても、個人の消費活動の促進にはつながらないと思うんです。
日本で必要なのは、中長期的な資産の期待値が見えることなのでは、と。例えば、飲食店の方が原材料のインフレのために一時的に借金をしたとすると、本来は赤字経営ではないのに、短期的な財務上はそうなっているように見えることもあります。それをいかに解消し、将来的な財務状況の予測を立てられるかが、個人の消費を促進する手助けになるのではないかと思っています。
リクルートには個人のこうした想像から生まれてきたプロダクトがたくさんあります。今はまだ私の妄想レベルですが、リクルートの事業の方向性と合致できれば、私にとって面白いシナジーが生まれるのでは、なんて企んでいます(笑)。
― 楽しみですね。最後に改めての質問です。今リクルートを選んでいる理由は?
横井:自身のキャリアで中長期的にやりたいことを、好きな人たちと働きながら実現できるからです。
これまでのキャリアでは、より多くの人に役立てるようなプロダクト機能を設計し、開発する経験をたくさん積んできました。しかし、それをビジネスとして成立させるスキルはまだまだです。誰かの「不」を解消することを根源的な価値としたプロダクトで、その腕を磨きたいと思っています。
郭:国内でこれだけ多くの方にご利用いただいているプロダクトの基盤があるので、さらに新しい価値を創りたいと志向する時、リクルートは「何かできる」会社。相当レバレッジが効く環境であり、純粋にワクワクできる会社だからです。
登壇者プロフィール
※プロフィールは取材当時のものです
- 横井 悠(よこい・ゆう)
- 株式会社リクルート プロダクト統括本部 プロダクトデザイン・マーケティング統括室 プロダクトデザイン室 SaaS領域プロダクトデザインユニット SaaS領域プロダクトデザイン2部 HR SaaSプロダクトデザイングループ
-
大学卒業後、2016年リクルートに新卒入社し、美容・飲食領域の業務支援SaaSにてUI/UXデザインに従事。2017年に退職し、2社のスタートアップでの経験を経て、2021年リクルートに出戻りで再入社。現在は、HR SaaSプロダクトデザイン領域のグループマネジャーを務める。趣味はコーヒーの焙煎
- 郭 桐(かく・きり)
- 株式会社リクルート プロダクト統括本部 プロダクトデザイン・マーケティング統括室 プロダクトデザイン室 SaaS領域プロダクトデザインユニット SaaS領域プロダクトデザイン1部 決済プロダクトデザイン3グループ
-
ボストン大学にて金融学を専攻した後、2019年リクルートに新卒秋入社し、人事組織にてエンジニアの新卒採用を担当。2021年に退職し、香港の証券会社でトレーダーとして1年働いた後、2022年リクルートに出戻りで再入社。現在は『Airペイ』の新規サービス開発に従事。趣味はゲーム実況を見ること