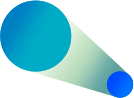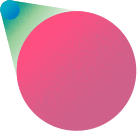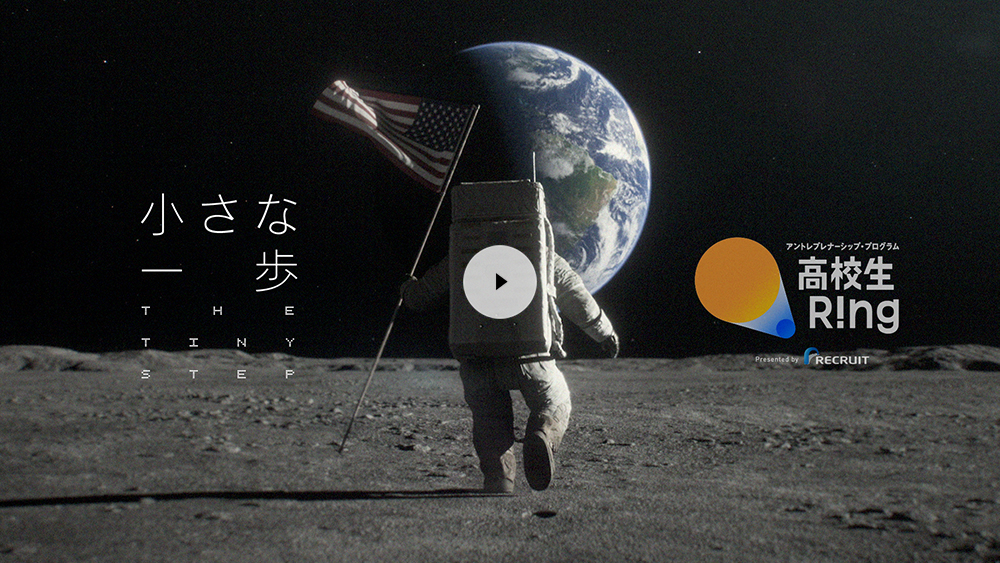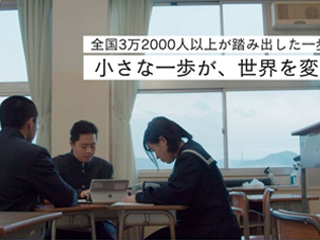セミファイナリスト選出高校の先生に聞く。
『高校生Ring』への挑戦が生徒にもたらしたもの
セミファイナリスト選出高校の先生に聞く。
『高校生Ring』への挑戦が生徒にもたらしたもの
アントレプレナーシップを学ぶための高校生向け教育プログラム『高校生Ring』。2024年度のプログラムに参加した学校では、この機会をどのように活用しているのでしょうか。今回紹介するのは、山口県立周防大島高等学校。同校の生徒がエントリーしたあるビジネスプランは、24年度のセミファイナリスト30組にも選ばれています。
山口県立周防大島高等学校では、生徒がどのように取り組み、先生方はどのようなサポートをしていたのでしょうか。探究の授業を担当しており『高校生Ring』の学内運営にも携わられた、山本百華先生と、山本芽以先生のおふたりに話を聞きました。
半径5mの身近な興味が切り口だから、内発的動機付けのきっかけにも
── まずは、山口県立周防大島高等学校の探究学習について教えてください。普段はどのようなテーマに取り組んでいるのでしょうか。
山本百華先生(以下、百華先生):山口県立周防大島高等学校は、山口県南東部の屋代島に位置する学校です。この地域特性を活かし、探究学習では「島じゅうキャンパス」というコンセプトのもと、島にあるさまざまな文化・資源を活かしながら地域をどう活性化させるかをテーマに学ぶのが特色になっています。
── そのようなカリキュラムがある中で、『高校生Ring』をどのように活用しているのでしょうか。
山本芽以先生(以下、芽以先生):最終的には地域課題を解決するための力を身につけてもらいたいのですが、生徒には課題解決の手段として事業のつくり方も学んでほしい。その機会として『高校生Ring』を活用しています。普段取り組んでいる「島」というテーマからあえて離れることで、多様な視点やアイデアに触れる機会にもなると考えました。
── 実際に『高校生Ring』に参加した生徒たちは、どう取り組んでくれましたか。
百華先生:「半径5m」という題材が、生徒たちの好奇心をくすぐっているようです。『高校生Ring』では生徒それぞれが自分の身の回りの出来事や体験をアイデアの出発点にするので、誰もが「自分事」として取り組めるのが非常に良かったポイント。序盤の「問いを立てる」ステップはみんな無邪気にアイデアを出していましたね。車が好きな生徒は車に関するビジネスのアイデアを考えていましたし、なかには恋愛を成就させるためのサービスを考えていた生徒もいたくらい。自由に発想することを楽しんでいる様子でした。
芽以先生:出発点は半径5mの“自分視点”の関心事からスタートするものの、『高校生Ring』では他者視点や社会視点も取り入れながらビジネスアイデアをブラッシュアップしていきますよね。まだ社会との接点が少ない生徒たちにとっては少し難しさもありましたが、こうしたプロセスを踏むことで必然的に社会との関わりが増え、自分の世界を広げたように思います。

どんなアイデアも否定せず、多様な大人との対話を促すような支援を
── 先生方の視点でみると『高校生Ring』のプログラムはどのような印象でしたか。
百華先生:私たち自身はビジネスの専門家ではないので、プログラムの内容を最初に確認したときは、正直に言えば生徒たちの学びを上手くサポートできるか未知数な部分もありました。けれど、私たちもはっきりとした答えを持っているわけではないからこそ、一方的に教えるのではなく、生徒たちそれぞれが主体的に学ぶ道のりを伴走・応援するスタンスに徹することができたと思います。
── 生徒をサポートする上で、大切にしていたことがあれば教えてください。
芽以先生:大人からみれば無茶なアイデアやロジックが破綻しているプランでも、否定しないことですね。生徒が自分の力で考えアウトプットしてみたことを尊重し、「いいね!」と褒める。その上で、「本当に実現可能か詳しく調査してみようか」「もう少し具体的にプランを磨いてみようか」と次のアクションを促すようにしていました。「良い悪い」をジャッジするのではなく「なぜ」を問いかけるような対話を重視。私たちはあくまでも伴走に徹し、生徒自身の意思で決断・選択してほしかったんです。
百華先生:もう一つ重視したことは、複数の大人がアドバイスをすること。教師がひとりでサポートしても視点が偏ってしまう懸念があったからこそ、普段の探究の授業でもお世話になっている地域の起業家など、学外の方々にも協力をいただきました。その上で私たちは、「その分野は○○さんが詳しいと思うよ。一度話を聞いてみたら?」といった風に、相談先の橋渡しを意識しています。
自分に自信が持てなかった生徒が、自らの強みに気づくきっかけに
── 山口県立周防大島高等学校からは、2024年度『高校生Ring』のセミファイナリストに選出されたチームも。生徒自身の経験を出発点に社会に潜む課題を設定し、「発達障がい者向けのAIサポートサービス」という解決手段を立案しているのがお見事でした。この生徒さんにとって『高校生Ring』はどのような機会になったとお感じですか。
百華先生:セミファイナリストに選んでいただいたのは、私が顧問を務めるボート部の生徒です。以前の彼は、あまり自信がない印象で、前向きな発言が少ない様子でした。発達障がいを持つ彼は、幼少期からその特性による、自分のネガティブな部分ばかり気にしてしまっていたと聞いています。そんな彼が『高校生Ring』をきっかけに、徐々に学内外の人々との関わりを深めていったことを嬉しく思います。
芽以先生:『高校生Ring』では私が彼のサポートを担当していましたが、実は、はじめのうちは自分のアイデアがあるのに見せたがらない、「どうせ自分なんか…」とマイナス思考になりがちだったんですよね。でも、徐々に私だけでなく他の先生方や外部の方にアイデアを見せるうちに、みんなからの「いいね!」を浴びて少しずつ自信が芽生えてきた様子でした。決定的に彼の印象が変わったのは、学内審査(一次審査)やリクルートによる二次審査を通過したタイミング。アイデアが認められ・選ばれることがモチベーションになり、エントリー後のプレゼンテーションやアイデアのブラッシュアップにも熱心に取り組んでくれた印象です。

── 『高校生Ring』の特にどの要素が成長のきっかけになったと思いますか。
芽以先生:やはり半径5mの出来事から問いを立てるところですね。以前から彼は発達障がいを自覚していましたが、『高校生Ring』をきっかけに改めて自分が長年悩んできたことに向き合い、同じように苦しんでいる人たちの存在や、世の中ではまだまだサポートが十分でないという事実に気づき、社会への問題意識が芽生えたようです。また、そうしたプロセスを通じて自分の特性をフラットに認められたことも彼が大きく成長したポイントだと思います。弱みは受け入れつつ、強みを活かすような思考へと変わったことで、『高校生Ring』以外の日常でもポジティブな発言がとても増えました。
── 具体的にはどのような強みを見出して、どう活かしているのですか。
芽以先生:彼は言葉でコミュニケーションを取ることには苦手意識を持っていますが、昔から絵を描くのは得意。そこで、『高校生Ring』のプレゼンテーションにおいても、自身の得意不得意を踏まえてビジュアル表現を重視した資料にトライしたんです。その結果、一目で意図が伝わるプレゼン資料が完成。自分の得意なやり方で審査を通過していることも大きな自信につながっているように思います。また、苦手と得意は表裏一体の関係にあると気づいたそう。例えば彼には相手を慮れるところも強みだと私は思います。そうした特性を理解し、以前よりも上手く使い込なせているような印象がありますね。
ビジネスプラン立案をきっかけに成長する姿が、同級生や地域にも伝播
── 2024年度の『高校生Ring』は全国から3万2,244名が参加しており、その中からセミファイナリストの30組に選出されたことは、本人だけでなく周囲の生徒にも影響があったのではないでしょうか。
百華先生:同じ学校に通っている仲間が全国で審査を勝ち抜いていることに他の生徒も大きな刺激を受けているようです。彼に秘められた個性が開花しつつあることを周囲がこぞって応援している状態。放課後にみんなで学校に残ってプレゼンの練習に付き合ってくれたり、アドバイスをくれたりと、他の生徒たちにも貴重な機会になっていると感じます。
芽以先生:小さなときから島で一緒に育った同級生からすると、彼のこの1年の変化は目覚ましいものがあるそう。大人たちも地域ぐるみで子どもたちの成長を見守っているような地域ですから、地域のみなさんにも彼の今回のチャレンジを知っていただいたことは大きな意味があると思っています。
── それでは最後に、先生が生徒に届けたい学びについて教えてください。また、その学びを実現する上で『高校生Ring』はどんなお手伝いができそうでしょうか。
芽以先生:私が探究の授業や『高校生Ring』を通じて生徒に伝えたいのは、みんなが思っている以上に世界は広くて、将来の選択肢も無数にあること。生徒たちの日常は基本的に家庭と学校が中心なので、社会との接点は非常に限られています。だからこそ、ビジネスをつくるというチャレンジを通じて普段の日常ではなかなか接点がない職業の人たちと出会い、「世の中にはこんな仕事があるんだ」「ためしにやってみたら案外好きかも?得意かも?」といった発見をたくさんしてほしい。そうした好奇心の入口として『高校生Ring』は良いきっかけになると思っています。とはいえ、教師の私たちだけでビジネスづくりをサポートするのはなかなか大変。生徒たちの自立的な学びをどう支援していくかは、『高校生Ring』をはじめとした外部の知見を活かしながら最適なやり方を模索していきたいです。
百華先生:今、世の中は「はっきりとした正解はない時代」だと言われていますよね。誰も答えを持っていないからこそ、自分の足で幅広く情報を収集し、自分の頭を捻って納得行くまで考えて、最後は自分の意思で「これが私なりの答え」だと決断をしていくしかない。私はそんな力を生徒に身につけてほしいと思っています。でも、この力は教師だけで教えられるものでもありません。多様な大人が生徒たちの学びのプロセスに伴走することで多くの気づきが得られるはずだと思うので、『高校生Ring』もそうした機会の一つにできたらと思います。

高校生Ring最新情報