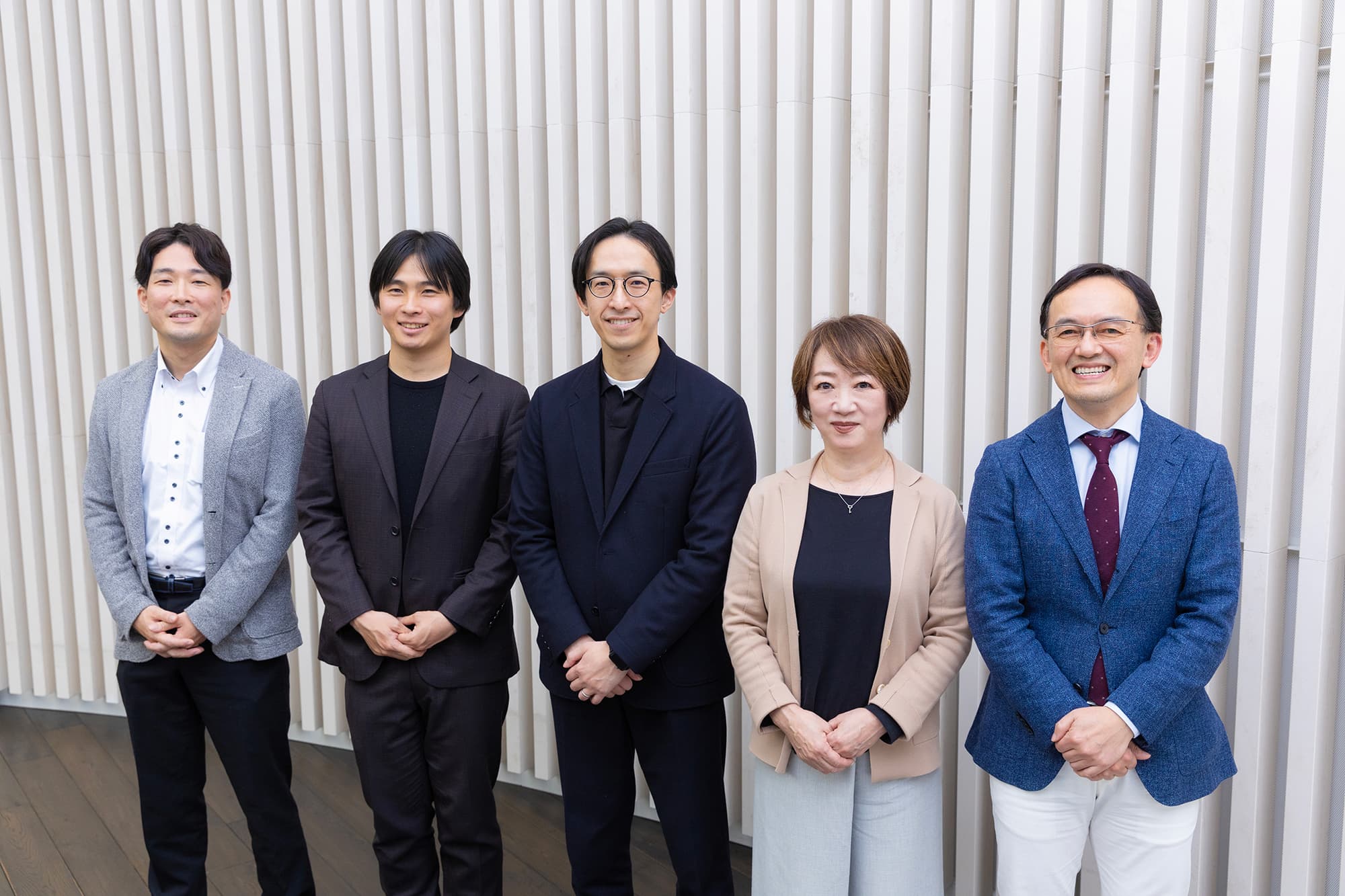「目線を変え、新しい価値観を生む」 西陣織の老舗「細尾」の12代目が語る、生き残り術とは?

文:高山裕美子 写真:下村亮人
時代の流れにあったニーズを考えて、既存のルールや常識を取っ払い、新しい領域を開拓していく、若き後継者の挑戦をフィーチャーする。
細尾は元禄年間に織物業を創業した西陣織の老舗。人間国宝作家の作品や伝統的な技を駆使した帯などの和装品に取り組んできた。しかし、西陣織のマーケットはこの30年でピーク時に比べ10分の1へと縮小。そこで新しい可能性を求めて海外進出を目指し、今ではラグジュアリーなファッションブランドやインテリアメーカー、現代アート作家とのコラボレーションが世界から注目されるように。
そんな細尾の12代目である取締役の細尾真孝さんに、西陣織の新たな挑戦について聞いてみた。
ー 西陣織の歴史について教えてください。
西陣織には1200年もの歴史があります。今でこそ帯の印象が強いですが、そうなったのはここ100年のことなんです。それ以前の主な客層は天皇、貴族、将軍家、豪族など、ドメスティックのアッパー層。そういう方たちの依頼に合わせたお誂えの織物を織り続けてきました。それが西陣織のバックグラウンドです。お金にいとめはつけないから、ひたすら美しいものを作りなさい、というミッションのもとで作っていたんです。
ー 西陣織の特徴は?
先染めの紋織物で、織り上がるまで20もの工程があり、京都の西陣といわれる7キロメートル圏内にそれらの工程を担う職人さんがいます。代々箔を貼る「箔屋」さんは、和紙の上に金箔をのせ、糸に定着させます。それを「カッターさん」と呼ばれる職人さんが、細かく裁断します。そして、それを糸として織物に織り込んでいくのです。今はギロチンのような刃で切っていますが、昔は刀で手切りしていました。20工程それぞれにマスタークラフトマンがいて、職人さんとの連携がなければ西陣織はできません。金糸を使う金襴や、貝殻を細かく切って螺鈿のように織り込む技術など、宝飾的な要素が西陣織にはありますね。昔の人はジュエリーを身にまとう文化はあまりなく、どこで差別化するかというと、着ているものの素材だったんです。また、縦糸が9000本あるのですが、どう縦糸を入れ、どう横糸を入れるか、1本1本をコントロールできますから、特殊な素材のものを織り込むこともできます。西陣織は、建築家が構造計算しながら建築物を作るのに似ています。糸が立体的で、世界でも類をみない複雑な構造体なんです。

ー そういった設計は、現在はコンピュータで行うのでしょうか?
設計図のことを"紋"といいますが、昔はすべて手作業で紙に描いていましたが、今はコンピュータで行っています。コンピュータになったことで、修正がききやすくなりました。織機は機械ですが、オートマティックというわけではありません。各織機に職人がつき、手の延長で機械を使うという感じです。
ー 近年、着物の需要が減っていることが、海外進出のきっかけになったのですか?
着物がなくならないにしても、マーケットが縮小していくにつれ、存続が危ぶまれるような状態でした。職人の高齢化が進み、場合によっては工程が欠ける心配もあった。うちの本業は着物や帯で、それを全国の着物の専門店や百貨店に卸していたんですが、今後はそれだけではだめだと思ったんですね。それで海外に目を向けたんです。最初に出品したのが、2006年のパリのメゾン・エ・オブジェ(世界最高峰のインテリア・デザインの総合見本市)でした。ソファーに西陣織の生地を貼って展示したのですが、そこで問題が生じました。西陣織の幅は基本、32cm。ソファーだと継ぎ目が出ちゃうんですね。翌年は、ヨーロッパの需要と継ぎ目問題を考慮してクッションを出品し、香港のレインクロフォードとロンドンのリバティからオーダーがありました。世界に名だたる高級デパートからの依頼は自信につながりましたが、1軒100万円ほどの売上だと継続していくのが難しく、事業としては成り立なかったのです。
ー 2008年に真孝さんが家業に加わるんですよね?
それまで家を継ぐつもりがなく、高校時代から音楽活動をしていたんです。ただ、音楽だけで食べていくのは厳しくて、自分たちで新しい音楽の分野を作れないかと、ファッションやアートとの融合などを試みていましたね。ただ経営者になるには、マネージメントを学ぶ必要があると感じ、大手ジュエリーメーカーに就職して、生産管理や商品開発などを担当しました。そんな時、父から海外進出を志していると聞き、西陣織を海外に発信していくのはおもしろいかもしれないと思ったんです。
ー 2008年の12月にパリで行われた、ルーブル宮国立装飾美術館の「感性kansei Japan Design Exhibition(日本のデザイン展)」で、西陣織の帯を展示されました。
伝統的な琳派の流れでの紹介だったんですけど、ここでは本業である帯を展示しました。展覧会自体が非常に好評だったため、巡回展になることになり、翌年の5月にはニューヨークで開催されました。展覧会の終了と同時に、世界的な建築家であるピーター・マリノ氏から連絡があったんです。展覧会で帯を見て、西陣織の技術を使ってテキスタイルの開発を依頼したいと。鉄が溶けたような、かなりコンテンポラリーな絵が送られてきて、それをもとに織物を作ってほしいということだったんです。世界中のクリスチャン・ディオールの店舗のリニューアルのタイミングで、上海の旗艦店の壁紙用でした。今まで自分たちはソファーやクッションのような商品にしたり、和柄じゃないと勝負ができないと思ってきたのですが、そうじゃなかった。和柄をとっぱらったときに、建築の内装材やファッションの素材にもなるなど、素材としての西陣織の可能性が広がったんです。
ー 新しいモチーフの西陣織を作るにあたり、苦労はなかったですか?
ソファーを作ったときにもネックになった幅問題ですね。壁紙に使うということは幅が必要です。社内でも意見が分かれたんですが、150cm幅の織機を開発しようということになりました。誰もやったことがない、前例がない、お金もかかる、できるかどうか保証もないと。けれどもやらないと次のステップにいけないことも分かっていました。1年かかりましたが、世界に1台の150cm幅の織物が織れる織機が完成したんです。結果、世界90都市のクリスチャン ディオール店舗の壁面のファブリックを織りました。毎年、織機を1台ずつ増やし、現在では6台になっています。

ー ピーター・マリノ氏は西陣織に何を求めたと思いますか?
彼が求めたのは日本的なものではないんです。単純にラグジュアリーを求めていた。常に彼らは世界中をリサーチし、最高峰のものを探しています。展覧会で私たちの帯を見て、0.5秒で彼らの感性に刺さったんでしょうね。西陣織にラグジュアリーを見い出してくれた。普通の織物は平織りですが、西陣織は細い糸と太い糸を混在させることもできる。より立体的、3D的なんです。また、ピーター氏が言っていたのは、店舗の壁紙に使うということは、その前に商品が並べられる訳ですが、西陣織はラグジュアリーさがありながら、商品を引き立ててくれるということ。そもそも、天皇や貴族が好んで身につけていたという歴史のなかで、品格を保ちながら優雅であるという技術が磨かれてきたのが西陣織なんです。絹なので繊細で切れやすいと思われがちですが、織機で強く織り込んでいるので強度もあります。
ー その後、さまざまなブランドやラグジュアリーホテルの仕事が舞い込んできたんですね。
相次いで、シャネルやルイ・ヴィトンの店舗の壁紙の依頼がきました。また、友人を介して、ファッションデザイナーの三原康裕さんと出会い、2012〜13秋冬のパリ・メンズコレクションで西陣織のファブリックで作ったスーツを発表されました。2013年のミラノサローネ(国際家具見本市)では、音響メーカーのバング&オルフセンとイタリアの高級テーラードメーカーのパルジレリとの3社でコラボレーションをし、スーツとスピーカーを展示しました。ホテルでは、ハイアットリージェンシー京都の内装や、ザ・リッツ・カールトン東京のリニューアルでベッドのヘッドボード用の織物の依頼を受けました。
ー 今までと異なる織物の注文があって、職人さんたちから戸惑いの声があがったりしませんでしたか?
クリスチャン ディオールから依頼がきた時に、それがファッションブランドだということはわかっても、「色はディオール・グレーで」と言われても何のことかわからない。色見本を見て初めて自分たちの言葉に変換できます。ですが、今ではディオールの色、シャネルの色、と職人たちは完璧に使い分けていますね。マーケットが広がることによって、帯が主流だった時代よりも、職人の仕事にスポットが当たったことは良かったと思います。
社内には職人が10人いて、全20工程のうちの10工程はうちの工房で行っています。2人はベテランの職人ですが、残りの8人は20〜30代の若手です。今は職人を募集すると10〜20倍の倍率で全国から集まります。昔はそんなことはありませんでした。芸大でアートをやっていたとか、服飾専門学校を出てアパレルで企画を担当していたという人が入社してきましたね。彼らは西陣織を、クリエイティブ産業として捉えています。
ー 最近ではアートとのコラボレーションも話題ですね。
2014年にはアメリカの現代アート作家、テレジータ・フェルナンデスさんが描いた風景画を金襴緞子で作りました。2015年には現代美術家のスプツニ子!さんに依頼されて、「バイオテクノロジーと西陣織を組み合わせよう」というコンセプトで、クラゲやサンゴの遺伝子を組み込んだ蚕からできる光るシルクを織り込み、グッチのイベントで光るドレスとして発表されました。今度はクモのDNAを使って作ってみようと話しています。スパイダーマンの世界ですね(笑)。可能性は広がっていきます。もしかすると将来的に西陣織で宇宙服を作るかもしれないし、宇宙船の内装を飾るかもしれない。そういう妄想をしては楽しんでいます。

ー 京都の伝統工芸を受け継ぐ若い後継者と一緒に、「GO ON(ゴオン)」というプロジェクトユニットを展開しています。
今まで、京都の伝統工芸の世界は横のつながりがほとんどなかったんですね。ですが、メゾン・エ・オブジェやミラノサローネで知り合って、日本の伝統工芸を盛り上げていかれたらと、2012年に設立しました。自分たちの技や素材を国内外の企業、クリエーターの提供し、今までにない新しいものを生み出していくことを目的としています。自分たちが子どもの頃、サッカー選手に憧れたように、「伝統工芸、かっこいい!」と職人を目指すようになってくれたら最高ですね。
ー 伝統を壊すことと、引き継ぎながら変えていくこととの境界性はなんでしょうか?
引き継いでいくためには壊すことも必要だと思います。頭で考えるよりも一度やってみる。バーンッと壊そうと思っても、そう簡単に壊れないのが伝統です。ビルの10階から飛び降りても変な重力があって、バンジージャンプみたいに引き戻される。だったら伝統を信じて、壊すつもりでやったほうがいい。バイオテクノロジーとのコラボレーションにしても、振り幅があればあるほどおもしろいじゃないですか。
ー 今後、どのようなことに挑戦していきたいですか?
西陣全体はもちろん、織物のマーケットを活性化させたいですね。日本には素晴らしい技術をもった機屋さんがたくさんありますので、ライバルをどんどん作って、お互いに切磋琢磨していきたい。今年のミラノサローネで、京都丹後の機屋さん3社とのコラボレーションブランド「tango tango」をローンチしました。丹後は1300年も前から着物を作り続けており、素晴らしい技術を持っている。目線を世界にむけた時にチャンスがあるんじゃないかと思っています。日本の織物の文化をこの先、200年、300年と続けていきたいですね。
プロフィール/敬称略
- 細尾真孝(ほそお・まさたか)
-
1978年、西陣織老舗 細尾家に生まれる。大学卒業後、音楽活動を経て、大手ジュエリーメーカーに入社。
退社後フィレンッェに留学し、2008年に細尾に入社。09年より新規事業を担当。
西陣織の技術、素材をベースにしたファブリックを海外に向けて展開し、建築家ピーター・マリノ氏が手掛けるクリスチャン ディオール、シャネルの店舗に使用される。
2012年には伝統工芸を担う同世代の若手後継者とのプロジェクトユニット「GO ON(ゴオン)」を始動。