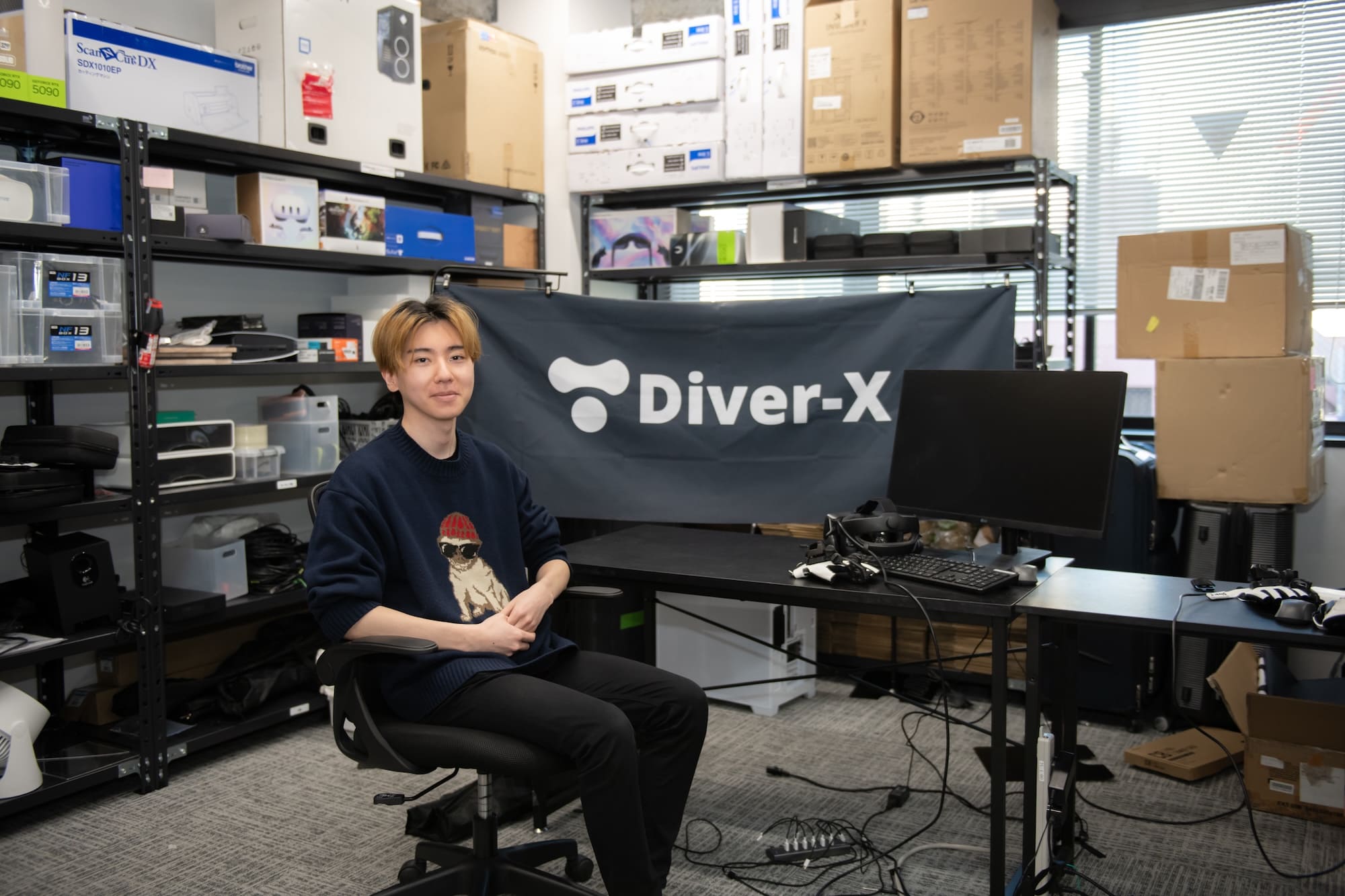アントレプレナーシップは「教わるもの」じゃない――九州大学 五十嵐教授に聞く、現代に必要な学び

現代に生きるすべての人が身に着けるべき力とは。アントレプレナーシップ教育の専門家である九州大学 五十嵐伸吾教授に、いま重視すべき学びを聞く
現代は、世の中の常識やスタンダードが次々と移り変わる、変化の激しい時代。そうした時代において注目を集めているのが、「アントレプレナーシップ教育」だ。政府は、日本でスタートアップ企業を増やす一手という意図も含め、小中高校でのアントレプレナーシップ教育の導入を検討。リクルートでも、2021年から高校生向けのアントレプレナーシップ・プログラム『高校生Ring』に取り組んでいる。
そこで今回登場いただいたのが、九州大学 ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター 副センター長の五十嵐伸吾教授。国内外の取り組みに精通する五十嵐先生にアントレプレナーシップ教育の本質を伺った。
アントレプレナーシップ=起業家精神にあらず
── 五十嵐先生は「アントレプレナーシップ」をどのようにとらえていますか。
最初に、日本でよくある誤解を解いておきたいです。日本では、“起業家精神”という日本語訳の印象が先行して、経営者や起業を志す人に必要な力として広まっています。しかし、アントレプレナーシップとはそうした一部の人だけが学べば良いものではありません。
1980年代に欧米でアントレプレナーシップ研究がはじまった目的は、社会にイノベーションを起こすこと。これまでにない価値観やアイデアを持ち込み、創造的な破壊で社会を進化させる担い手を育成することが目的でした。つまり、アントレプレナーシップの本質は、「起業・経営に求められる力」というより、「既存の常識に縛られず革新的なアイデアや価値を生み出す力」のこと。役割や職種に関係なく誰もが持っておくべきものだと言えます。
また、誤解を生んだのはアントレプレナーシップの研究対象として最初に注目されたのが、若き起業家たちだったことも影響しているでしょう。大企業では既存事業を守るために新規事業が生まれにくくなる、いわゆる「イノベーションのジレンマ」が生じやすいことが指摘されていました。そのため、スタートアップ企業の経営者の特徴を分析することで、イノベーターの条件を解明しようとしたのです。
しかし、研究の結果見えてきたのは、「人としての資質は関係ない」。イノベーターは何も特別な人だけがなれるのではなく、誰でもなりえるというものでした。そこで現在では、オポチュニティ(=機会)こそがアントレプレナーシップの起点であると定義されています。当たり前を疑い、自ら問いを立て、その解決に向けて主体的に行動していくような機会の追及をたくさん経験すること。それがアントレプレナーシップを養うと考えられていますね。

── 五十嵐先生はなぜアントレプレナーシップを専門分野にされているのでしょうか。
私は大学卒業後に銀行へ就職したのですが、そのキャリアの大半はスタートアップ企業の支援をしていました。今後の日本を牽引するようなイノベーティブな技術・アイデアを支援し、ビジネスとして成長させることが私のなすべきこと。銀行からは、「きみのミッションは将来のホンダ、ソニーを探し育てることだ」と言われていましたね。
今でいうベンチャーキャピタルのような仕事に専心し、経営者と一緒に汗をかきながら企業を成長させていくのが、私は大好きでした。でも、スタートアップの難しさも痛いほど味わったんです。在籍期間中、3,000件以上の事業アイデアに目を通して、可能性を感じた310社を支援。それでも、110社ほどは事業が行き詰まり潰れてしまいました。決して誰かが手を抜いていたわけでもない。みんなが真剣に、必死に事業立ち上げに邁進して、それでも上手くいかないことの方が多い。スタートアップが大成するのはセンミツ(1,000に3つの確率)と言いますが、いかに厳しい世界かを目の当たりにしました。
しかし、このままイノベーションを諦めたら日本は沈んでいくだけ。たくさんの失敗を重ねるかもしれないけれど、その中から成功するプレイヤーが生まれて、次の時代のスタンダードをつくってほしい。そう願っているからこそ、私はイノベーションを支援する立場としてアントレプレナーシップ教育の道に進みました。
型通りのプログラムでは、アントレプレナーシップは芽生えない
── 先生は日本におけるアントレプレナーシップ教育の現状をどうお感じですか。
冒頭に申し上げたように、起業家育成講座のことをアントレプレナーシップ教育と呼ぶのは本質ではありません。経営学部など起業を目指す人が多い一部の層に向けた“ビジネスプランの書き方教室”が大半になってしまっているのが残念です。たしかに、そうしたテクニックを学べば会社をつくることはできるでしょう。しかし、社会にイノベーションを起こすためには、単に頭数を増やすだけでは意味がありません。ただでさえ失敗することが多いのですから、中身が伴わない起業では上手くいくはずもない。より価値の高いアイデアを生むために、主体的に考える力を鍛えていくことが大切でしょう。
── 海外ではアントレプレナーシップ教育にどう取り組んでいるのですか。
国によっても事情は違いますが、私が特に注目しているのは「同じ国でも都市・地域単位でアントレプレナーシップ教育を必要とする事情が異なる」ということです。例えば、アメリカ。東海岸のボストン周辺や西海岸のシリコンバレーでアントレプレナーシップを学ぶ移民や海外学生の場合、イノベーションの実現やグローバルで競争力のある企業をつくることを目指しています。
一方、私が知り合った南部のアントレプレナーシップの大学教員の黒人女性は、全く別のモチベーションを持っていた。「黒人女性は白人よりも黒人男性に抑圧されて生きてきた。私は黒人女性が自立して男性と対等に生きられるために、黒人女性が手に職を持つようなアントレプレナーシップ教育を広めたい」と語ってくれた。そんな風に地域によってまるで意味合いが変わってくるんですよ。
貧富の差が激しい国では、こうした違いがさらに顕著です。貧困地域で育ち、その苦境から抜け出すために身近なもので商売をしたい人と、教育水準が高い地域で育ち、グローバルで活躍する例えばICT(情報化学)分野の起業家になりたい人では、同じアントレプレナーシップでもアプローチが変わってくるのは当然でしょう。
このように、同じ国でも地域によってアントレプレナーシップを学ぶ動機が異なります。日本のアントレプレナーシップが海外よりも遅れているのは、目立ったイノベーションが生まれていないという意味で事実かもしれませんが、だからといってどこかの国を参考にして全国一律で、画一的なやり方を真似するのは得策ではないと思います。

── 「アントレプレナーシップ教育自体に正解はなく、それぞれが主体的にあり方を考えることが大切」ということでしょうか。
日本っていまだに「シリコンバレー」を礼賛するじゃないですか。でも、世界を見渡してみてください。たしかに、いろんな国でシリコンバレーがお手本にされた時期はありましたが、単にコピーを目指す試みはことごとく失敗しています。各地域の特性にあった教育システムをつくることが必要なのではないでしょうか。
例えば私が所属する九州大学がある福岡市。近年スタートアップが盛んな地域として注目されていますが、実は福岡市はシリコンバレーや東京をベンチマークしていません。都市の人口規模や地域の環境・産業などを考慮し、参考にしているのはフィンランドのヘルシンキや米国のシアトルなどです。
そんな風に地域ごとに適した教育システムを検討しなければ、人々がアントレプレナーシップを意欲的に学ぼうとはしないでしょう。そもそもアントレプレナーシップとは自ら問いを立て考えることです。汎用的に用意されたカリキュラムを一方的に教えるだけでは、主体的な学びの機会とは言えず、イノベーションの原動力となるような内発的動機は芽生えにくいと思います。
“KY”大歓迎。好奇心の赴くままに発言・行動する機会をつくろう
── リクルートでは、高校生向けのアントレプレナーシップ・プログラム『高校生Ring』に取り組んでいます。五十嵐先生は今の10代にどんな学びが必要だとお考えですか。
教科書に書いていないことを実体験から学ぶ。そんな機会をたくさん経験することですね。例えば「レモネードを売る」という就業実習をするとしたら、教育者は売り方を教えるのではなく、「どうやったら売れるのか」を学生が自ら考える機会にしてほしいです。
繰り返しになりますが、別にすべての人が起業家になる必要はありません。でも、自ら考えて行動をしていく力は、これからの時代を生きていく上でも必要な力。まずは多くの子どもたちにアントレプレナーシップ教育の入り口を経験してもらい、もっとアントレプレナーシップを学びたいかどうかを自分自身で考えてみてほしいです。
──『高校生Ring』では、“半径5mの日常”からアイデアの種を見つけてもらうプロセスを大切にしています。このような学び方を先生はどうお感じですか。
アントレプレナーシップを育む最初のステップとしてはとても良いと思います。ただ、“ユニークネス(独自性)”を育むための体験も意識してほしいです。人と違う“尖ったアイデア”を発想するには日常に留まっているだけではなかなか新しい視点が身に付きません。次のステップとして、半径5mから飛び出していくようなアクションがあるとよいですね。

── どうやったら日常や常識の枠から飛び出していけるでしょうか。
人との違いに注目することですね。例えばグループワークをするときに、グループとしての意見をまとめようとしすぎると、共通点にばかり目が行きがちです。妥協点を探すような思考のプロセスになり、尖った部分が削られ中庸なアウトプットになってしまう。グループでディスカッションする際は、同じことに注目するのではなく、それぞれのアイデアの違いを面白がりましょう。周囲で見守っている大人たちは、非現実的な案や過激な案でも「その発想、面白いね」と褒めてあげる。そうやって、子どもたちを無意識のとらわれから解放していくことも大切です。
あとは失敗を許容すること。無難に見えるアイデアでも、奇抜なだけに見えるアイデアでも構いません。論理が破綻していたって、仲間と喧嘩したって良いじゃないですか。もし私の授業だったら、空気を読まない“KY”な人やアイデア、ウエルカムです。むしろ失敗を恐れず自分を解き放つ経験をしてほしい。教室の中で考えず、自らの好奇心に従ってどんどん外に飛び出して確かめてほしいです。
── 子どもたちだけでなく、ビジネスパーソンがこれからアントレプレナーシップを養うにはどうしたら良いでしょうか。
会社と個人、それぞれにアドバイスをしたいです。まず会社には、個人のやりたいことが自由に発言できるカルチャーをつくってほしい。上司から言われたことに従うだけの組織では、個人の問題意識が育ちません。まずは発言できること。さらに言えば個人の希望と会社の利益を接続させながら、実現の道を模索していくことが必要だと思います。
一方の個人も、意見が言えない、言うべきではないと思い込んでいませんか。日本の組織に所属している人は空気を読む能力に長けており、それがアントレプレナーシップを阻害する要因にもなっていると感じます。そして、高校生へのアドバイスと同じようにどんどん外へ飛び出してほしいです。例えば社会人のみなさんにも、大学・大学院で学生と一緒にアントレプレナーシップを学ぶのも一つの手段でしょう。みなさんにとって普段は得られない刺激になるとともに、学生たちにとっても実社会の様々な課題を知る人との交流は貴重な経験になります。
何より、一度社会に出てから必要だと思って主体的に大学に戻ってくる人たちの内発的動機こそ、アントレプレナーシップの源泉です。自分の内から湧きおこる気持ちに従って行動してみることをお勧めします。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 五十嵐 伸吾(いがらし・しんご)
-
1983年小樽商科大学卒、2005年筑波大学大学院ビジネス科学研究科修士課程修了(MBA)。UFJ銀行(現三菱東京UFJ銀行)を経て、2005年九州大学着任。銀行在籍時は、ハイテクスタートアップの発掘、審査、成長支援に携わり、300社強のスタートアップを支援してきた。大学・大学院のための起業家教育推進ネットワーク・アドバイザリーボード委員(経済産業省)などアントレプレナーシップ教育に造詣が深い。現在、日本ベンチャー学会理事