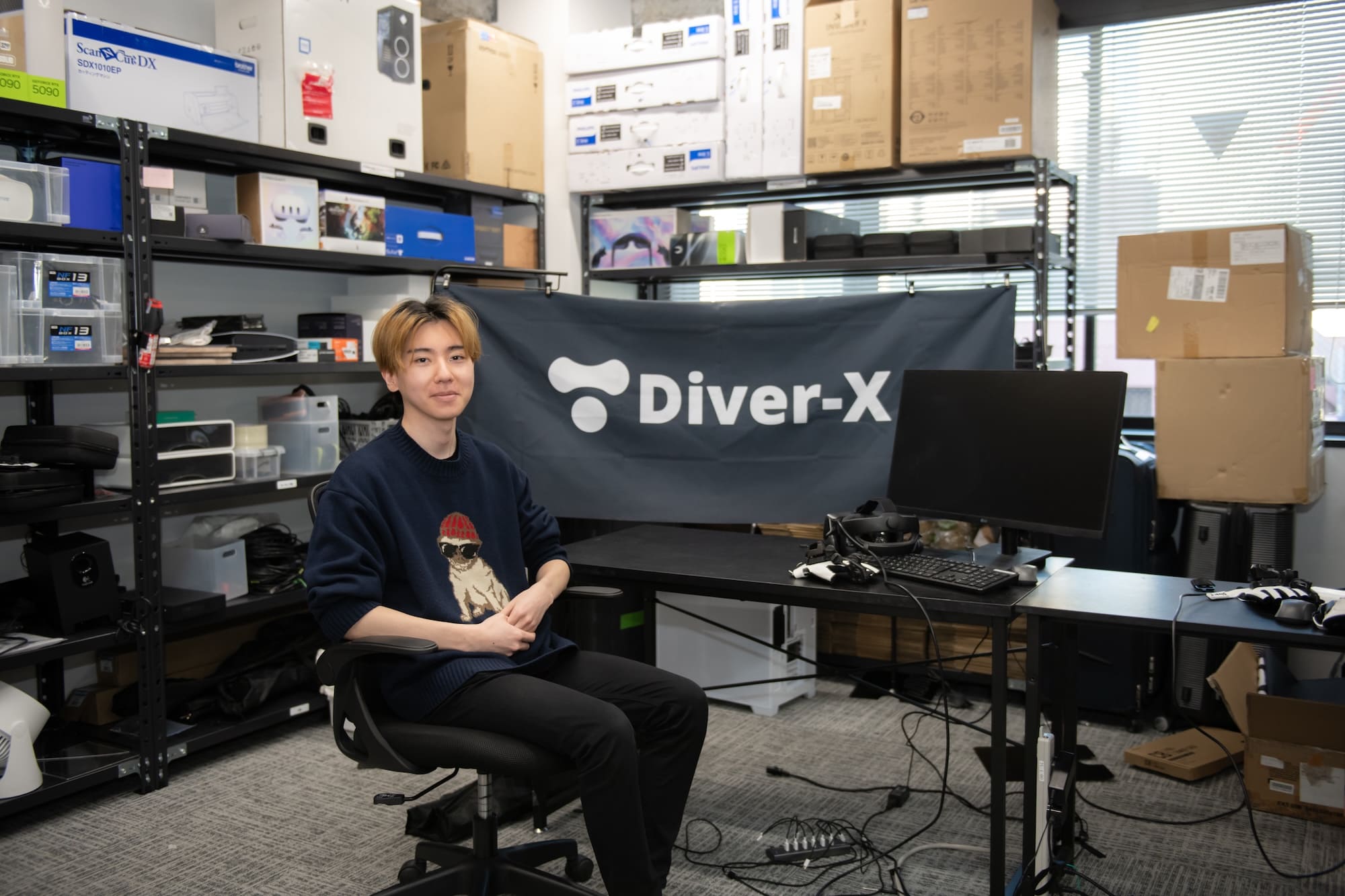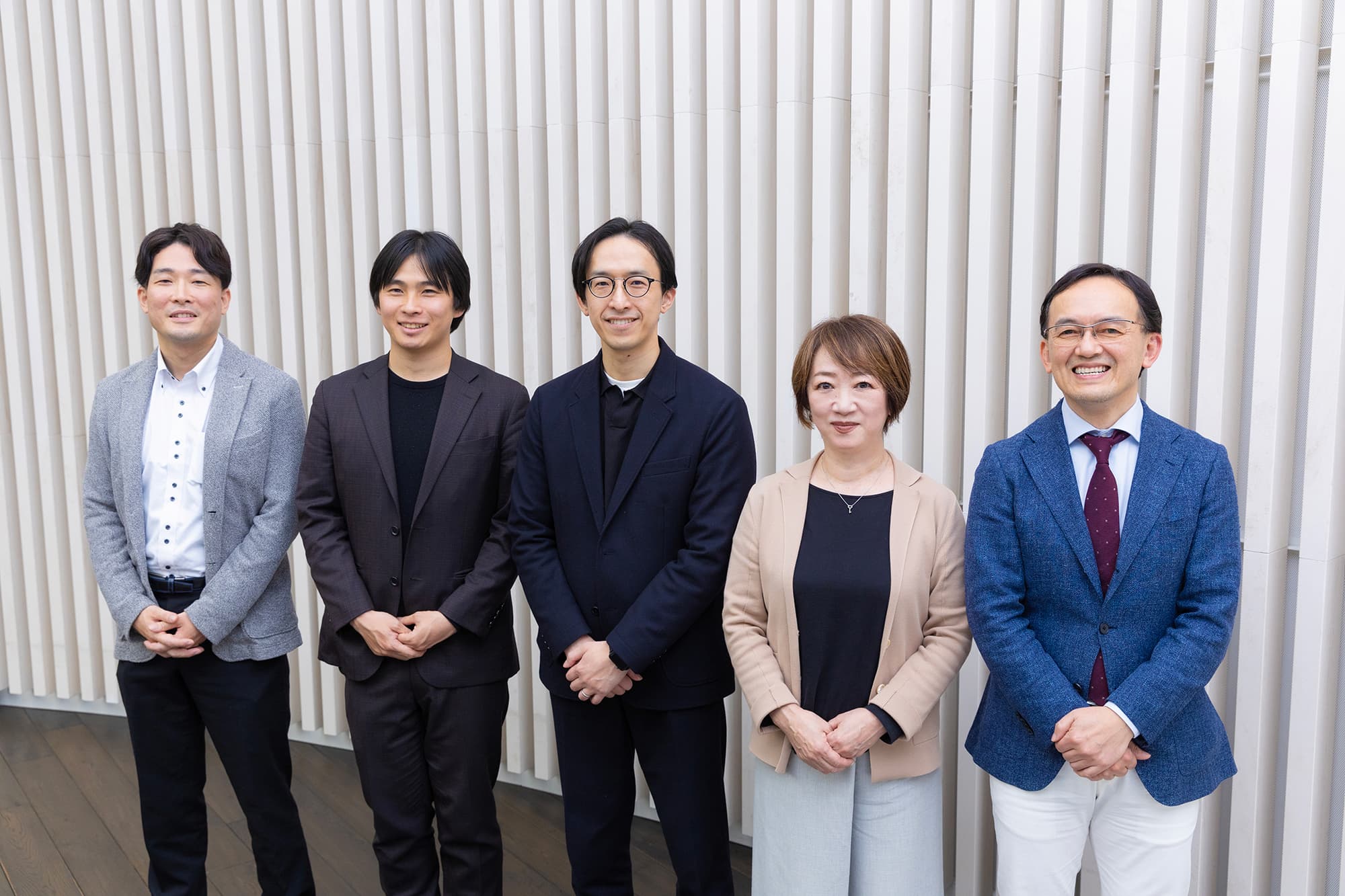生きた会話を大切に――作家・多和田葉子の目に映る日本とグローバリズム

文:西山武志 写真:斉藤有美
ドイツ在住35年以上。母語の外側から文学と向き合ってきた日本人作家は、「言葉」から日本をどう捉えるのか。グローバル化の時代に求められる、姿勢を訊く。
2018年、アメリカで最も権威のある文学賞のひとつ「全米図書賞」の翻訳部門に"The Emissary"という作品が選ばれた。原題は『献灯使』、著者はドイツ在住の日本人作家、多和田葉子さんだ。日本人の受賞は36年ぶりだったことから、その知らせは快挙として、多くのメディアで伝えられた。
多和田さんは「母語の外側に出て、そこで感じるものから創作をしたい」と、大学卒業後すぐに渡独した人だ。若くして自らグローバルな環境に身を投じた多和田さんには、今の日本はどう見えているのだろうか。複雑に多様化する世界で、私たちが見失ってはならないものとは何だろうか。「言語」と「日本」と「グローバル」をキーワードに挙げながら、お話を伺った。
"私"を省略する世界と、そうではない世界がある
人を人たらしめるもの。そのひとつに「言語」があることを、私たちは普段、あまり意識していない。言語があるから、人間は他の動物より高度なコミュニケーションが取れるし、高度に思考できる。言語がなかったら、目に映る光景をどのように把握し、物事をどのように理解するのだろうか。こうした問いも、言語に乗ってやって来る。言語のない世界とは、もはや想像もつかない。
一口に言語と言っても、その種類はさまざまだ。一説には、7,000以上もの"living languages(実際に使用されている言語)"があるとも言われている。それぞれの言語は、使われる人や土地の影響を多分に受け、独自の発展を遂げてきた。人と母語は密接に関わり合っていて、そこには翻訳でくみ取りきれないニュアンスが必ず存在する。
もしかしたら、使う言語が違うと、世界が全然違って見えるのではないか----中学校で英語を習い始めてから、多和田さんはそんな思いをよく巡らすようになった。
「たとえば、日本語だと『僕』とか『私』とか、一人称の種類はいっぱいありますよね。それに、会話では一人称を省略することが多い。一方、英語の一人称はほぼ『I』だけで、基本的に省略されない。そういう文法の違いの一つひとつが、とても不思議で新鮮でした。
誰もが常に『私は~』から話し始める世界は、一体どんな感じなんだろう。いま日本語で考えていることを、すべて別の言語で処理するようになったら、人格まで変わってしまうんじゃないか......とか、あの頃はよく想像をしていましたね」

進学しても、他言語に対する興味が薄れることはなかった。偶然入った都立立川高校は、第二外国語を履修できる珍しい学校だった。多和田さんはそこで多言語に触れながら、母語だけでなく英語やドイツ語での創作にも慣れ親しんだ。大学ではロシア文学を専攻し、ロシア語とドイツ語の授業を選択した。
「大学には『日本人より日本語が上手いんじゃないか』って思えるようなネイティブの先生たちがいて。そこから、なぜ彼らはこんなに日本語が流暢なんだろう、どうやって日本語を覚えたんだろう、どこが難しかったんだろうと、日本語に対する興味も膨らんでいったんです」
異なる言語圏の世界から見える景色を知りたい。母語である日本語を外側から捉え直してみたい。言語と言語の溝に飛び込み、作品を書いてみたい。こうした動機から、多和田さんは大学卒業後すぐにドイツに移住。母語以外でも創作活動を行なう「エクソフォン作家」の道へと歩みを進めた。
「外から人が入って来て自分たちの言葉を使って書いている」という受け止め方が「外国人文学や「移民文学」という言い方に現れているとしたら、「自分を包んでいる(縛っている)母語の外にどうやって出るか? 出たらどうなるか?」という創作の場からの好奇心に溢れた冒険的な発想が「エクソフォン文学」だとわたしは解釈した。
(多和田葉子著『エクソフォニ― 母語の外へ出る旅』より)
日本ならではの、遊び心と言葉遊び
1982年に日本を出てから今日に至るまで、ドイツを拠点に創作活動を続けてきた多和田さん。意識的に母語の外側に立った彼女は、日本語の特徴や面白さを、どのように捉えているのだろうか。
「日本語は、漢字とひらがなとカタカナを混ぜて使っていますよね。漢字もいろんな読み方をするし、英語もカタカナに変換して、もとの語とはほど遠い意味で使ったりする。数十種の文字で何でも書き表せる他言語に比べたら、なんて美しくないゴミ箱みたいな言語なんだろうって(笑)。はじめのうちは結構コンプレックスに感じていたんです。けれども、その雑然さを生かした文学作品を書いているうちに『いろんな言語が入り組んでいるからこその面白みがある。ゴミの島ほど豊かな場所はない』と思うようになっていきました。私は言葉遊びがすごく好きで、よく作中にも取り入れますが、日本語はハチャメチャだからこそ、いろんな形で遊べて楽しいです」
遊びと言えば、と多和田さんは話を広げる。ドイツに移り住んでから再確認したのは、日本の技術力の高さだった。その技術には、ふたつの方向性がある。ひとつは、昨今ではクラフトマンシップと呼ばれるような手仕事の職人技。もうひとつは、オーディオやゲームなどの"遊び"にまつわる技術だ。そして後者のほうが圧倒的に、世界をリードしている事実に驚いた。「日本人は勤勉だと言われることは多いけど、実は真面目なフリをしているだけで、本当はものすごく遊び好きなんですよ、きっと」と、彼女は笑った。
「遊びには、昔から関心があるんです。日本の文学は、明治ごろから『人生とは何か、自己とは何か』を追求するような真面目な分野になってきて、あんまり遊びが表に出てこないんですけど。でも、長い歴史を見れば、和歌の掛詞だってシャレのようなものだし、文豪たちの作品にも所々に言葉遊びが隠れています。
生きている人間たちの生活には"言葉を使うことの喜び"が常にあるんです。言葉遊びはその表出でもあるし、時には大きな存在に対する軽やかな批判、抵抗として力を発揮することもありますよね」
ほぐすことのできない単語に矛盾する形容詞を付けてみると、脳の一部がほぐれる感覚がある。(中略)閉鎖的開国、国民無視の民主主義、病的健康、敗け組の勝利、窮屈な自由、できるダメ人間、年とった若者、無駄なお金のかかる節約、贅沢な貧しさ、手間のかかる即席、安物の高級品、危険な安全保障。こうして集めてみると、これは単なる遊びではなく、社会を透かし見るのに必要不可欠なレトリックだという気さえしてくる。
(多和田葉子著『言葉と歩く日記』より)
その協調は誰がために
言語は人間と密接な関係にあると同時に、社会とも互いに影響し合うものだ。社会と言語の関係について、多和田さんはドイツと日本との間に、大きな違いがあると感じている。
「ドイツだと、たとえば政府を批判していても、すごく楽しいんですよ。『そんなの良くないよね』と言えば言うほど気分がよくなって、皆も笑顔になっていく(笑)。これが日本だと、そうもいかない。ネガティブなことを発言すると、自分も、周りの人たちも悲しくなってしまいがちです。日本人は言葉と身体、自分と社会の繋がりが太いのかなと感じます。そこにはいい面もあるけれども、もう少し切り離して考えないと、困ることが多そうですよね」

日本人は協調的で、集団の規範を重んじる傾向が強い----これは昔から、比較文化学や心理学、社会学などの領域でよく指摘されてきたことだ。多和田さんも、その実感はあると言う。日本に帰ってくる度、電車を待つ人々の整然とした列、車内での静かさには感心するそうだ。「他人様に迷惑をかけない」という意識を、私たちは非常に強く持っている。
「ドイツでは順番そっちのけで電車に乗ろうとする人も多いし、車内でもうるさいです。見方によっては、思いやりに欠けるように感じるかもしれませんね。けど、駅のそばでうずくまっている人やホームレスがいたりすると、みんなで『どうしたの、どうしたの?』と声をかけるんですよ」
日本ではどうですかと聞かれて、のどがキュッと締まった。立ち止まらない理由を考える。いつもの光景だから、酔いつぶれているのは自業自得だから、自分が声をかけたところで役にも立たないだろうからと、言い訳がましい言葉ばかりが浮かんだ。
「ルールを守らないと、都会の生活は快適じゃなくなる。それは本来、人間のためにあるはずなのに、守るためにむしろ、人間らしい心をシャットダウンしているように感じる瞬間があります。実態のない他人様や社会を気にするあまり、目の前の一人ひとりに対する想像力が欠けてはいないかと、時折立ち止まってみることも必要ですね」
「......君たちは、悪いことをしていないのに謝ってはいけないよ。」
「でも迷惑かけてるよね。」
「迷惑は死語だ。よく覚えておいてほしい。昔、文明が充分に発達していなかった時代には、役にたつ人間と役にたたない人間という区別があった。君たちはそういう考え方を引き継いではいけないよ。」
(多和田葉子著『献灯使』より)
大きな流れに同化されないための、主体的な選択
多和田さんが日本の外側に飛び出した当時は、まだ"飛び出す"必要があった頃だった。今やこちらから出向かずとも、人もモノも情報も、海の向こうから絶え間なく入ってくる時代だ。現在進行形で生きる私たちは、興味関心の有無を問わず、グローバル化する社会に向き合わざるを得ない。
「たとえば、海外の企業が京都のホテルを買って、立派に建て直したりしているのも、グローバル化と言えますよね。ただ、街づくりに関わることについては、その土地に暮らす人たちの意思を無視してはいけないし、グローバルよりもローカルが大切だと思います。
お金儲けばかりを優先する経済活動は、いろんな国の国境を超えて、いろんなものを買い占めて、自分のものにしてしまう。資本の力で、周りに"assimilation(同化)"を迫ります。この意味でのグローバル化はぜひ止めてほしいし、それに食い荒らされるくらいなら、私は鎖国の方がよっぽどマシだと思ってしまうのです」
インターネットの発達によって「世界は開かれた」と語る人々がいる。一方で、開かれすぎた情報源、その雑然さのストレスから逃れるように、自ら進んで周りとの"同化"の道を歩んではいまいかと、不安に思うことがある。押し寄せてくる大きな流れに飲み込まれないためには、グローバル化する社会、外から入ってくる大量の思想や言葉と、どのように向き合っていけばよいのだろうか。
「やっぱり一番大切なのは、本や音楽、映画、芝居など、ジャンルを問わずいろいろな作品に触れることかな。たくさん触れる中で『自分はどういうものが好きなのか、面白いと感じるか』をはっきりさせて、膨らませていくこと。それこそが『自分が主体的に選択する』という態度に繋がっていくから」
私が私であるために、主体的に選ぶこと。常時インターネットに繋がっている今では、存外難しい行為かもしれない。スマートフォンを覗けば、いつだって向こうが"あなたへのオススメ"を用意してくれている。自分で選んでいるように感じるのは錯覚で、その実は「限られた選択肢の中から、意図的に選ばされている」といった状況に置かれていることも多い。
「1日1時間でもいいから、いつもの繋がりをシャットダウンして、普段とは違う方法で自分が選んだものを吸収する。その繰り返しで視野が広がっていくと、用意された"枠"に敏感になっていくはず。誰かの都合でしかない枠組みを打ち破って自分で選択していくこと、自ら選択肢を見出していくことを、常に考えてほしいです」
母語で得られる情報だけに頼るのは危険だ。外国語を学ぶ理由の一つはそこにあると思う。もし第二次世界大戦中に多くの日本人がアメリカの新聞と日本の新聞を読み比べていたら、戦争はもっと早く終わっていたのではないか。それはアメリカの新聞に書かれていることが正しいという意味ではない。書かれていることがあまりに違うというだけで、自分の頭で考えるしかない、何でも疑ってかかれ、という意識が生まれてくる。そのことが大切なのだと思う。
(『言葉と歩く日記』より)
どこに行っても、いるのは同じ人間だから
グローバル化する世界では、異なる母語、異なる文化を持つ人々と接する機会が、必然的に増えていく。彼らと共によき職場、よき共同体を編んでいくためには、どんな姿勢を持つ必要かと尋ねてみると、シンプルな答えが返ってきた。
「『会話は楽しいんだ』と思ってほしい。誤解があったり、何度も聞き返したりすることもあるだろうけど、どうか恥ずかしがらないで。他人の話し言葉に触れることは、いつだって新鮮で、とても楽しいことだから。相手に興味を持って、どんどん自分から話しかけてほしいなと思います。毎日、生きた人間とお話することを忘れないで」
生きた人間と、という言葉に力がこもっていた。話を聞きながら、これは"グローバル化する世界で"なんて前置きの要らない、他者と向き合うために持つべき意識なのだと気付いた。
「今だと『テキストでやり取りするほうが楽で、気兼ねなく話せる』という人も多いかもしれません。なぜかと言えば、相手の表情や声の調子、ボディランゲージなどを踏まえて、感情の機微を読み取らなくて済むから。労力が省略されているからです。
けれども、それってもはや『相手を人間だと思わない』ってことと、ほとんど変わらないんですよ。そういういびつなコミュニケーションに時間を費やすよりは、誰でもいいから、実際に話をするひとときを大切にしてほしいなと思います」

同じ言語を使っていれば、同じ言葉を知っていれば、わかり合える――私たちはそう思い込みたがる。実際はどうだろうか。誰かが「悲しい」と言った時、それだけでその悲しみを理解することは、到底不可能だ。「どうしたの?」と聞き返し、相手の語りを引き出すことで、初めてわかり合える可能性が生まれる。
「話すことでお互い理解できることもあるし、できないこともある。むしろ話せば話すほど、近しい相手でも自分と全然違うことに気付いていって、『これでよく一緒にいられるな』と驚いたりする。反対に、全然違う文化圏の相手で、言葉のやり取り自体はぎこちなくても、肩の角度や顔の傾け方だけで通じ合うこともある。不思議だし、面白いですよね」
生まれた国の違い、文化の違い、母語の違いよりも先に、人間は一人ひとりがそれぞれ違う存在だ。それでもどこかに共通項はある。「どこに行っても、いるのは同じ人間。全部が丸きり分かり合えない、なんてことは絶対にない」と、多和田さんは言った。違いを豊かさとして分かち合い、心を通わせるきっかけを掴むためにも、私たちには生きた会話が必要だ。
「時々でいいから、全然知らない人と、用もなく喋ってみてください。これは私からの提案です。意味のない会話が、今の日本には欠けているんじゃないかな。用がないと話さない社会なんて、とても寂しいです。何もないところから、あることないことを引き出していくやり取りって、大事だと思うんですよね。そういう会話にも、楽しさや喜びがあるんだということを、ぜひ覚えていてください」
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 多和田葉子(たわだ・ようこ)
-
小説家、詩人。1960年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。ハンブルク大学大学院修士課程修了。文学博士(チューリッヒ大学)。1982年よりドイツに在住し、日本語とドイツ語で作品を手がける。1991年『かかとを失くして』で群像新人文学賞、1993年『犬婿入り』で芥川賞、2000年『ヒナギクのお茶の場合』で泉鏡花文学賞、2002年『球形時間』でBunkamuraドゥマゴ文学賞、2003年『容疑者の夜行列車』で伊藤整文学賞、谷崎潤一郎賞、2005年にゲーテ・メダル、2009年に早稲田大学坪内逍遙大賞、2011年『尼僧とキューピッドの弓』で紫式部文学賞、『雪の練習生』で野間文芸賞、2013年『雲をつかむ話』で読売文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞、2016年にドイツのクライスト賞を日本人で初めて受賞、2018年『献灯使』で全米図書賞翻訳文学部門、2020年朝日賞など受賞多数。著書に『ゴットハルト鉄道』『飛魂』『エクソフォニー 母語の外へ出る旅』『旅をする裸の眼』『ボルドーの義兄』『地球にちりばめられて』『穴あきエフの初恋祭り』などがある。2020年4月、最新作『星に仄めかされて』が刊行予定。