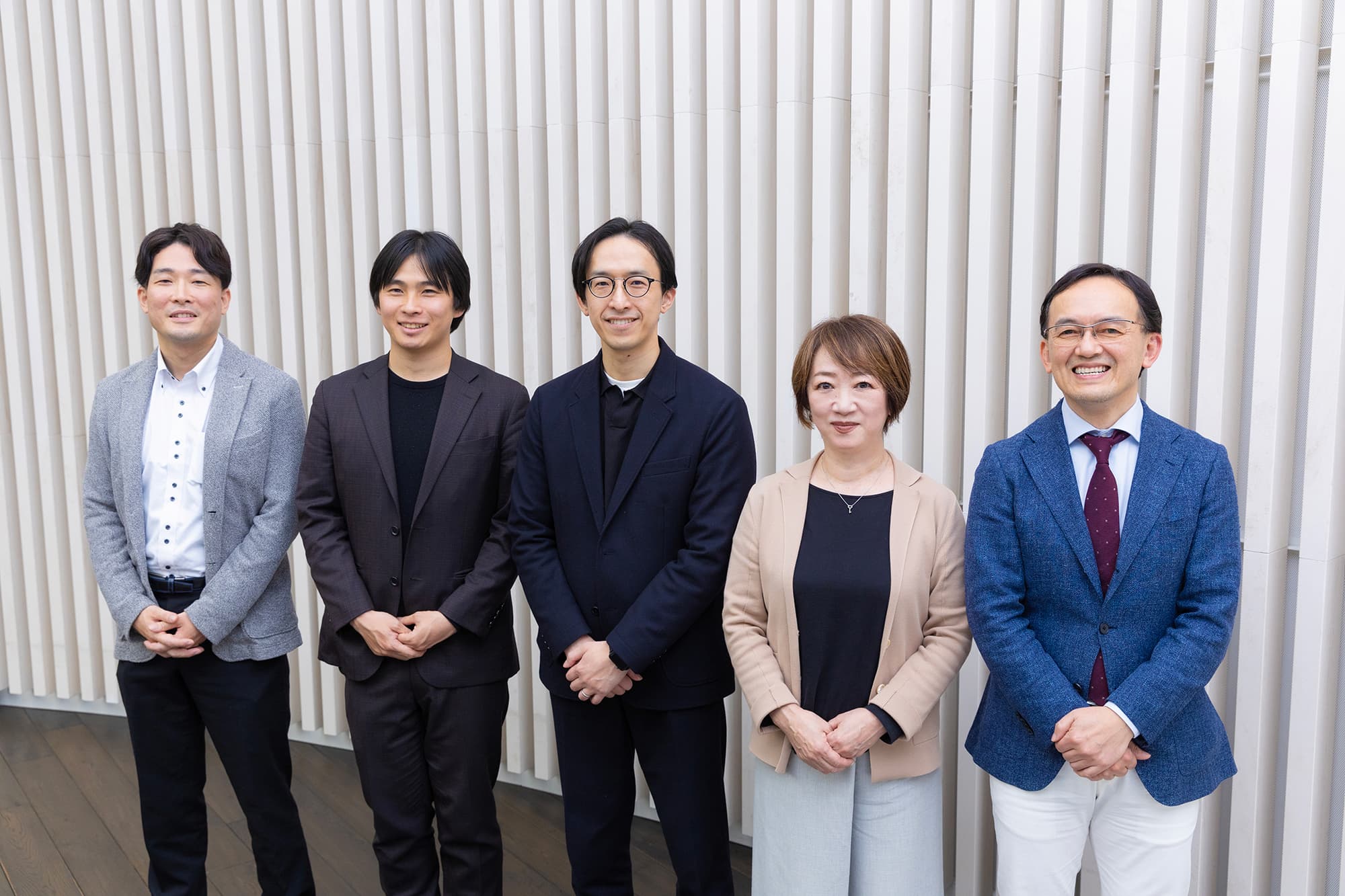蓄積された「現場の知見」をAI活用で自動化 「ベテラン×若手」が生んだイノベーション

写真は左からリクルートコミュニケーションズ 隈本、保坂
*本記事は2019年3月6日に東洋経済オンラインに掲載された記事広告からの転載です。
目覚ましいスピードで進展するテクノロジーは、ビジネスだけではなく、人々の「働き方」そのものを変えようとしている。労働時間短縮や残業時間削減の先にある、働き方改革の本質とは何なのか。そして、そのような改革はどうすれば実現可能なのか。全3回にわたり、先進的な取り組みを行うリクルートグループの事例を基に、答えをひもといていく。第1回となる今回は、書店やコンビニエンスストアで販売する雑誌の配本業務にAIを導入し、現場の負担を軽減するとともに、実売部数をアップするというイノベーションを実現した、リクルートコミュニケーションズの中心メンバー2人に話を聞いた。
2016年の夏、リクルートコミュニケーションズで新たなプロジェクトが立ち上がろうとしていた。従来、担当従業員の手で行われていた「配本」の仕組みにAIを導入し、その有用性を検証することを決定したのだ。自動で、なおかつ高精度に配本できる「AI配本システム」の開発を目指した。
一般的に、出版業界では「取次」と呼ばれる中間流通業者が配本業務を担う中、同社は「1人でも多くの読者に届けたい」という思いから、独自のノウハウや配本モデルを構築し、取次と協働しながら配本を行ってきた。
長年、同社マーケティング局流通デザイン部で配本設計に携わり、現在は機能開発推進プロジェクトを兼任している隈本悟氏は、今回のプロジェクトについて次のように明かしてくれた。

「自社でも配本業務を行う中で、『店残理論』という独自の配本ロジックを2002年に構築しました。これは当時としては優れた理論だったのですが、出版販売額のピークは1997年で、現在、市場は約半分にまで縮小しました。17年経って市場環境が大きく変わると、さすがに実態と合わない部分が出てきました。どうせ手をつけるなら抜本的に見直そうと考え、AIで配本設計するシステムの開発プロジェクトを立ち上げました」
一部の改修ではなく、大がかりなシステム刷新に乗り出した背景には、隈本氏自身の次世代への思いがあったという。
「実は、プロジェクトが立ち上がった翌年に定年予定だったので、周りからは『ノウハウや知見を残してください』とせっつかれていました。マニュアル化して文書にしても、どうせ誰も読まずに形骸化してしまいます。このプロジェクトは、自分が配本業務で苦労したこと、知り得たことをきちんと仕組み化して残すための、絶好の機会になると考えました」
AI配本システムでも生きるベテランの知見
隈本氏からバトンを託された1人が、ICTソリューション局アドバンスドテクノロジー開発部の保坂桂佑氏だ。保坂氏は2016年に同社へ転職したデータサイエンティストだ。「先進的な取り組みをしたい」と希望を出したところ、AI配本システムの開発プロジェクトにアサインされた。
保坂氏は、自身に与えられたミッションについて次のように語る。

「長年のデータ蓄積があり、前例のないプロジェクト。この膨大なデータから信頼に足る予測モデルをつくることが私の使命だとも感じました。例えば『配本は3冊だったが、売れたのは1冊』という売れ残りが起きたり、『配本は3冊だったが、すぐに売り切れ』という売り逃しのおそれがあったり......。売れ残った店の部数を売り逃した店の店頭に置けば、もっと実売を増やせたかもしれない。実売を増やすためには、1店舗ごとに需要を予測して各店舗に最適な部数を配分する必要があります。ただ、個店ごとの需要予測を人力でやるのは困難です。これまで使っていた『店残理論』とはまったく異なるロジックを模索し、結果、機械学習で需要を予測し、数理最適化により部数配分を行うゼロからのモデル構築を行うことになりました」
データサイエンティストの保坂氏にとって、出版流通は未知の世界。配本の仕組みを理解するため、最初の1~2カ月は隈本氏の下に通ってレクチャーを受けた。横で業務を繰り返し見ているうち、「完コピできていると言われるまでになった」(保坂氏)という。
基本を理解した後も、隈本氏とのやり取りは続いた。AIに生データを読み込ませるだけでも、データから学習して実売予測をまずまずの精度で行うことはできるのだが、現場の知見を説明変数として入れ込めば、さらに高精度な予測が可能になるという。
「市場全体のトレンドや、立地の違いによる実売の傾向、キャンペーンを行ったときの反応などを教えてもらいました。また、個店単位で需要予測ができても、それに合わせてどう配本すれば実売が最大化するかという全体最適の部分は、また別のロジックが必要になります。そこに関しては、『店残理論』の考え方がヒントになりました。最初はよく理解できなかったので、隈本さんには何度も教えを請いに行きました」(保坂氏)
ベテランと若手の"思い"がうまくかみ合った結果
現場経験を通してノウハウや知見を蓄積してきたベテランと、現場経験はないもののデータに基づく定量判断ロジックの構築やシステム化に強い若手データサイエンティスト。一般的にはコミュニケーションに苦労する組み合わせだが、2人の場合はうまくかみ合ったようだ。
「システム開発を外部に依頼することもありますが、『何か違う』と疑問をぶつけても、『何かじゃよくわからない。スケジュールに間に合いませんよ』と言われてしまう。しかし、保坂さんは『じゃあ一緒に考えましょう』と受け止めてくれた。おかげで遠慮なく話ができました」(隈本氏)
「正直、『グイグイくるな』と思っていました(笑)。でも、自分の都合で無理難題をふっかけてくるわけではない。共通のゴールに向かうまでの課題をご自身の目線で話してくれたので、素直に耳を傾けることができました」(保坂氏)
プロジェクト立ち上げから約1年。AI配本システムは、2017年7月末に一部の情報誌から運用を開始した。システムがはじき出した実売予測は、前年比2桁%増。予測値を聞いて隈本氏は耳を疑ったという。
「当時は市場環境もダウントレンドにありました。その流れを食い止めようと苦労していたところでしたので、『2桁%増なんて本当か?』と思い、保坂さんにも『数字がおかしい。どこかに間違いがある』と指摘しました。ところが、ふたを開けてみると実売もそれに並ぶ結果に。これには本当に驚きましたね」(隈本氏)
スペシャリティを尊重し、高め合う文化
この結果を受けて、対象を旅行情報誌『じゃらん』や中古車情報誌『カーセンサー』へと拡大。それらの雑誌でも実売は押し上げられた。
「売り逃しが減ったということは、読者が欲しい雑誌を欲しいときに買えるようになったということです。また、システム導入後は売れ残りも減り、収益性が改善しました。その分、雑誌のクオリティーを高めたり、商品を開発したりするための投資ができます。読者やクライアントにとってのメリットも大きいのです」(隈本氏)

今回のプロジェクトが軌道に乗ったのは、「ベテラン×若手」「経験×データ」のコラボレーションがうまくいったからだ。ただ、この組み合わせは、ともすれば不協和音を引き起こす。同社ではなぜ、うまくいったのだろうか。
2人の言葉から読み取れるのは、他者へのリスペクトだ。隈本氏は、若い力についてこう語る。
「キャリアを重ねると成功体験が積み上がっていきますが、同時にそれが陳腐化する場面も多々経験してきました。社内には、高い能力を持った若手が大勢いる。自分のやり方に固執するより、彼らの力を借りながらやったほうが、もっといいものができると確信していました」
一方、保坂氏は社内の多様性を強調した。
「リクルートグループは、異なるスペシャリティを持った人が集まっています。私はデータ分析が専門ですが、チームには、マネジメントに強い人、部署間のコミュニケーションがうまい人、エンジニアリングに長けている人、インフラの専門家など多種多様な人がいます。皆さんがそれぞれのスペシャリティを発揮してくれたおかげで、私も自分の得意なことに集中できました」
リクルートグループには、「個の尊重」という、一人ひとりがお互いを尊重し、高め合う文化が根付いている。激変する時代において、イノベーション創出の土壌となるのは、こうした多様な人材によるコラボレーションを生む企業文化なのかもしれない。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 隈本 悟(くまもと・さとる)
- リクルートコミュニケーションズ マーケティング局流通デザイン部兼機能開発推進プロジェクト
※プロジェクト開始翌年の定年後も、嘱託として継続勤務している
- 保坂桂佑(ほさか・けいすけ)
- リクルートコミュニケーションズ ICTソリューション局アドバンスドテクノロジー開発部マネジャー