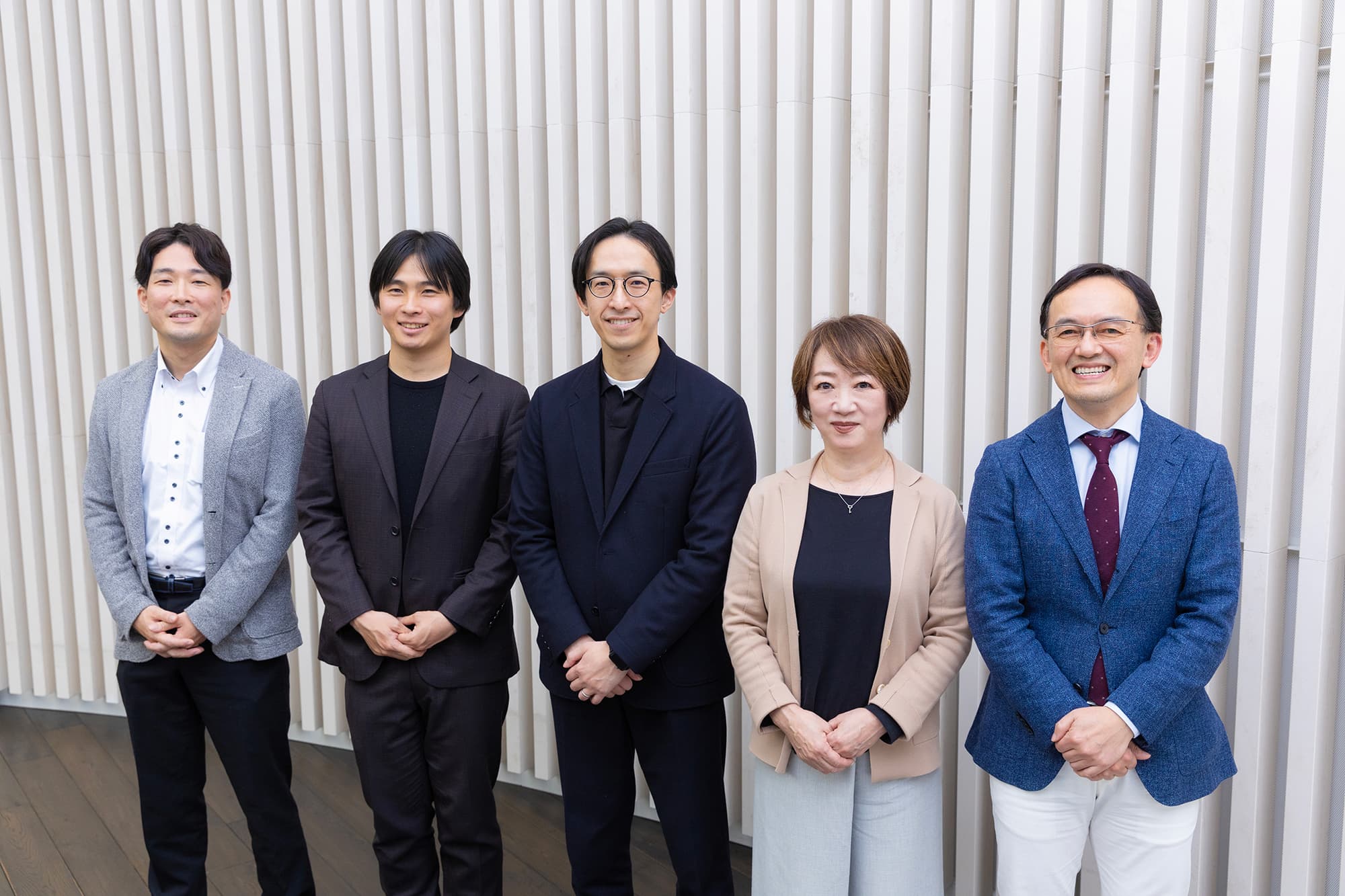現場の声に寄り添う「HRテクノロジー」~「人事×テック」でエンゲージメント最大化~

写真は左からリクルート 興梠、リクルートジョブズ 西川
*本記事は2019年3月15日に東洋経済オンラインに掲載された記事広告からの転載です。
働き方改革の本質とは何なのか。そして、そのような改革はどうすれば実現可能なのか。リクルートグループの先進的な事例を基に、答えをひもといていく連載(全3回)の第2回となる今回は、限られた人的リソースの中で、最大の成果を挙げるために「人事」と「テクノロジー」がコラボレーションしたリクルートジョブズの取り組みについて。人事担当者とエンジニアの出会いから始まったプロジェクトは、今やグループ内に横展開されるまでに。成功の要因を探った。
近年、有効求人倍率は上昇傾向にあり、企業による採用活動はますます活発化している。こうした中、人材採用の総合サービスを提供するリクルートジョブズにとって、営業組織の戦力化はつねに重要な課題である。マネジャーが抱えるメンバーは1人当たり30人以上になることもあり、それだけの人数の組織に対するエンゲージメントを高め、迅速に個人のパフォーマンスを最大化するかが喫緊の課題だった。

テクノロジーで現場のマネジメントを支援してほしい......。リクルート人事統括室人事戦略部のエンジニア、興梠智紀氏に新たなミッションが与えられたのはそのようなさなかの2016年。興梠氏はその半年前に同社に就職し、グループの人事戦略をR&Dに近い立場で支援する同部に配属されたばかり。早速現場にヒアリングしたところ、ある事実に気づいた。
「話を聞く前は、マネジメント手法の違いが、メンバーのエンゲージメントが高い組織のマネジャーとそうではないマネジャーの差になっているだろうと考えていました。ところがヒアリングしてみると、どちらもやっていることは同じで、違ったのは、マネジャーのメンバーに対する認識でした。メンバーのエンゲージメントが高い組織のマネジャーほど、メンバーのコンディションについての認識が、本人と一致していたのです」(興梠氏)
新システムの運用で表れた効果とは?
新入社員のコンディションを可視化するツールを作れば、マネジャーの負荷を増やさずに、より適切なマネジメントができる。そう考えた興梠氏に援軍が現れた。リクルートジョブズ人事部採用グループの西川央明氏だ。
西川氏は、当時の現場の様子を次のように述懐する。

「リクルートには"よもやま"と呼ばれる1対1のミーティング文化があり、マネジャーは、そこでメンバーの悩みを聞いてアドバイスをしています。ただ、よもやまは月1回だけの場合もあります。新入社員は慣れない職場で戸惑うことが多く、月1回程度では対応が後手に回ることもありました。コンディションが可視化されれば、タイミングを逃さずフォローができます。興梠さんの話を聞いて、ぜひうちでツールを試してほしいと思いました」
意気投合した2人はプロジェクトを立ち上げ、メンバーのコンディションを可視化するシステムの開発に着手。プロトタイプは約2カ月で完成し、福岡の拠点でテスト運用していくつかの修正を加えた後、2018年4月から本格的な運用をスタートさせた。
システムの概要はこうだ。
メンバーに自分のコンディションについてのサーベイを行うとともに、BIツールを使って回答の時系列データを集計し可視化。マネジャーはそれを確認し、コンディションに関する認識を一致させたうえで、誰にどのようなサポートをすべきか判断する。
また、対応の効果の確認や、個々人に応じたマネジメントの蓄積、マネジャー間でのマネジメント情報の共有など、データに基づいたPDCAを実行することができるという。
さらに、回答はビジネスチャットツールと連携させてリアルタイムで届くため、緊急性が高ければマネジャーが即時対応することも可能だ。
運用を始めると、早速効果が見え始めた。
ある新人営業担当者はサーベイに人間関係の悩みを告白。それを読んだマネジャーがランチ会を開いたところ、次のサーベイには「距離が縮まって仕事がやりやすくなった」と書かれていたという。
落ち込んでいるように見えた新人が考えていたこと
こんなケースもあった。
別の新人がミスをして、マネジャーの指導を受けた。周囲からは、新人が落ち込んでいるように見えたという。ところが、サーベイには「叱られたことで成長の機会を得られた」との記載が。実際は周囲の認識と逆で、本人は静かに燃えていたことがわかったのだ。
状況を報告するだけなら、一般的な日報でも可能かもしれない。しかし、興梠氏は今回のツールのメリットを次のように強調する。
「チャットツールと連携しているので、情報共有がタイムリーです。データとして定量化できることも大きいですね。新入社員のコンディションを定量化できれば、一人ひとりに個別に対応するだけではなく、組織的な人事施策を打つこともできます」
西川氏も続ける。
「定量化されたデータを分析すると、上司との縦の関係だけでなく、社員同士の横のつながりもコンディションに影響することがわかりました。そこで、他チームのメンバーとのランチ会を企画したり、部活を立ち上げたりしました。とくに部活は今でも継続されています」
現場を主語にしたHRテクノロジーの開発
実際、どのくらいの定量的効果があったのか。システムを導入した組織のeNPS(従業員エンゲージメントの指標)は、導入していない組織と比べて12ポイント高かったという。「12ポイントは、簡単に言うと業界平均と業界トップくらいの差です。導入した組織のエンゲージメントの改善幅はかなり高かったといえます」(西川氏)
マネジャーの負担を増やすことなく、新人の成長を支援する同社の取り組みは、着実に実を結びつつある。しかし、ITを活用して同様の課題に取り組んでいる企業は多いものの、必ずしも順調なところばかりではない。2人はなぜうまくいったのか。興梠氏は次のように分析する。

「HRテクノロジーは、人事部門やIT部門が主語になり、現場が置き去りにされがちです。しかし、大切なのは、現場が使いたいと思うかどうか。僕らは『現場マネジャーの"強化スーツ"になればいい』という思いで、ユーザーエクスペリエンスに徹底的にこだわりました。つまり、現場を主語にしたことが功を奏したと考えております」
一方、西川氏は、既成の枠組みにとらわれずに挑戦させてくれる組織風土について言及した。
「今回のプロジェクトは上からの大号令で始まったわけではなく、興梠さんと2人でスモールスタートしました。今だから言えることですが、実は、現場のマネジャーたちを巻き込んで『いいね。そんなシステムがあったらほしい』という反応を確かめてから、人事部長に話を上げました。人事部長は一発で了承してくれ、このボトムアップ文化はリクルートらしいと改めて感じましたね」

興梠氏も同じことを感じていたようだ。
「長い歴史を持つリクルートは、マネジメントのスタイルが確立されているイメージがありました。ただ、私は入社したばかりだったので、リクルート流がわかりませんでした。そこで、プロジェクトを学術的な視点で、部内のメンバーにプレゼンしたところ、『面白い』と好感触を得られました。私なりのやり方を歓迎し、楽しんでくれたので、進めやすかったです」
今後もさらなる改良を続けていくという。
「支援する期間を延ばして、自分の成長を振り返ることができる仕組みにしていきたいです」(西川氏)
「新人だけではなく、部署異動した社員にも使えるようにしたいです」(興梠氏)
若手2人で始めた小さなプロジェクトは、徐々に広がりを見せ、2019年2月現在、グループ内の組織が利用している。興梠氏が所属するリクルート人事統括室人事戦略部では、データサイエンティストやエンジニアが活躍しており、「人事」と「テクノロジー」のコラボレーションが着々と進んでいるという。
AIやRPAなど、新しいテクノロジーの導入は、ともすればそれ自体が目的になってしまいがちだ。リクルートがそうならなかったのは、「どこまで現場の社員を尊重し、寄り添えるか」にこだわり抜いたからだろう。つまり、デジタル化が進展しているとはいえ、「企業」は「人」で成り立っているのだ。それを見失わないことこそが、これからの時代を生き抜くうえで最も必要なことなのではないだろうか。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 興梠 智紀(こうろぎ・ともき)
- リクルート 人事統括室人事戦略部
- 西川 央明(にしかわ・ひろあき)
- リクルートジョブズ 人事部採用グループ