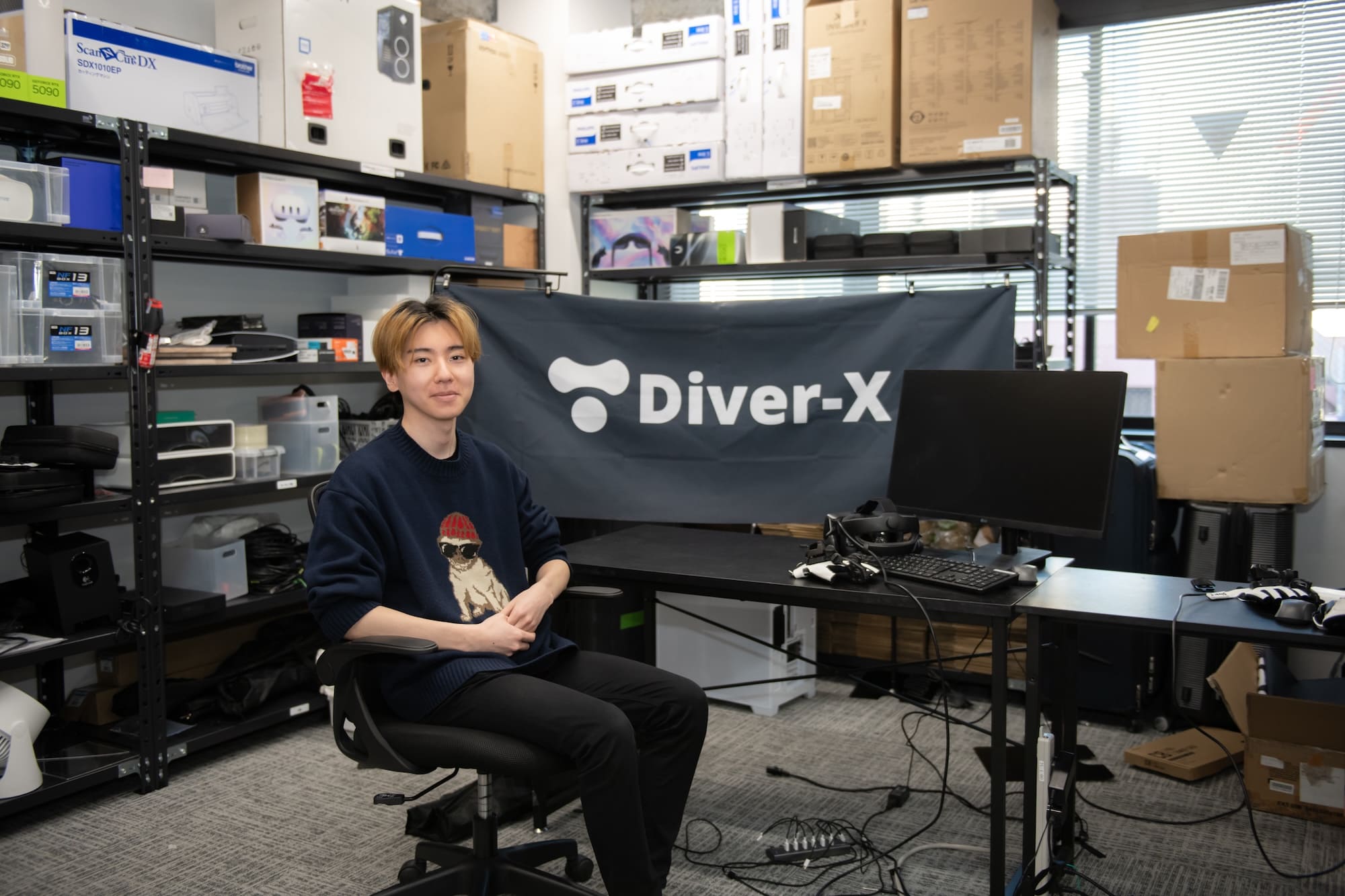人的資本経営のヒント~革新に挑む中堅・中小企業事例を『GOOD ACTION AWARD』に学ぶ「人材価値循環への投資」編

人的資本経営の調査・研究を進めるリクルート。今回は、『リクナビNEXT』が主催する、イキイキと働ける職場の共創を実現した企業を表彰する『GOOD ACTION AWARD』を受賞した、中小企業の人的資本のベストプラクティスのなかから、ヒントとなる9つの好事例を『GOOD ACTION AWARD』審査委員であり、HR統括編集長、『リクナビNEXT』編集長も務める藤井 薫が3回にわたって解説します。
人的資本経営における3つの投資戦略とは?

藤井:「人的資本経営」に今、注目が集まっていることは皆さんもご存じかと思います。2022年7月に、経済産業省及び金融庁がオブザーブするコンソーシアムが設立され、企業投資の観点でも国内外で情報の開示が求められ始めています。
リクルートでは、「人的資本経営」を「人材を最重要の資本と捉え、全ての人材を活かしていくことで、人的資本の持続的な価値向上につながり、それがひいては経営目的の達成・企業価値の向上につながっていくもの」と定義し、その実践のためには「人材価値の向上」「人材価値の活用」「人材価値の循環」にこそ、投資していくべきだと考えています。
上記の3つの視点における先進的な取り組みを紹介する企画の第3弾は「人材価値循環への投資」に関する事例です。
「人材価値循環への投資」は、主に下記3つの行動を指します。
- 人材の価値を、企業の枠を超えて広く社会で巡らせるための取り組み
- 自社の従業員の副業・兼業を認め、従業員の知見を社外でも活用してもらうこと。アルムナイネットワークを構築して、元従業員と退職後もつながり続けること
- 投資の対象は自社の従業員だけに限らない。学生へのキャリア教育や理系人材・博士人材育成への支援なども人材価値循環への投資に該当する
企業の枠を超えた人材価値循環を実現するには、人的資本の価値を高める3STEPのなかで特に、「個とチームのエンパワーメント」「セルフ・リスキリングの促進」が必要です。
「個とチームのエンパワーメント」で培った、外に目を向ける重要性・自発的な目標の尊重・挑戦的な仕事の依頼・従業員の強みや持ち味の伝達・何でも発言し合える職場づくりなどをベースに、「セルフ・リスキリングの促進」を働きかける必要があります。
これまでの従業員は、「企業(会社)内で学ぶ」以外のことをあまり経験してきていません。そのため、「リスキリング・教育などの機会は企業が提供してくれるもの」という認識を強く持っています。
従業員自身に「変化対応力を身につける必要がある」と認識してもらうためには、企業側が企業の枠を超えた活動の経験、セルフ・アンラーニング、セルフ・リスキリングの重要性を従業員に伝えていくことが重要です。
マルイグループでは、「個人のなかの多様性」を実現することを目的に、積極的な人事異動による「職種変更」を推進し、新たな付加価値の創出に努めています。同社が行った社内調査では、職種変更を行った人の約86%が異動後に「成長を実感した」と回答。社を挙げて、「人材価値の循環への投資」に取り組む価値を感じさせてくれます。こうした結果を見ると、従業員のキャリアアップに対して真剣に取り組むべき時期が来ていると実感します。
「人材価値循環への投資」に関する取り組み―事例1
副業・兼業に取り組む「二刀流職員」が子どもたちの新たなロールモデルに
―学校法人 新渡戸文化学園―
取り組み内容:
同学園は、「未来の学校の教員は、社会を広く知る人物であって欲しい」という理事長の思いから、現職の教員の外部副業を認めたり、民間人材を副業教員として受け入れる、「学校ダイバーシティ」を進めた。教員の副業推進に向けてはチーム担任制・教科担任制を導入し、ひとりでクラス運営を抱え込むことなく、残業削減にもつながる体制を整備。社会人による授業の導入では、「Happiness Bridge」というオンライン環境も活かしたプログラムを導入し、多様な人材が教壇に立っている。
その結果、生徒への調査では「社会への関心」「自己肯定感」のスコアが全国平均を大きく上回った。教員も教職以外の活動を経験することによって視野が広がり悩みを抱え込みがちな状態から改善。イキイキと働く教員を生み出し、現場の活性化につながった。
課題:社会的に問題になっている「18歳意識調査」での自己肯定感の低さ、いじめ・不登校問題、教員の長時間労働
実施背景:社会には今こそ「未来の学校づくり」が必要で、そこに貢献したいと考えたため
他社で活かせるポイント:
・働く人を自組織に縛り付けず、皆が自由にキャリアを描ける体制を整えたこと
・働く人がイキイキと働き、充実するために何が必要なのかを考え抜いたこと

学校法人 新渡戸文化学園 理事長 平岩国泰さん
*お名前、肩書等は『GOOD ACTION AWARD』受賞当時のものです
藤井:まず同学園の取り組みが成功したのは、「これからの時代を担う子どもたちには、自分の力で社会をより良くできるという実感を持ち、自律的に考えて判断する力が必要。そういった子どもたちに育てるには、先生自身が多様な経験を積み、社会のリアルを伝えていくことが重要」という考えがあったからこそだと思います。
一般的に長時間労働といわれる教員が副業・兼業を始めると聞くと、現実的ではないと感じる方も多いのではないでしょうか。同学園は、チーム担任制・教科担任制という新たな体制を準備して副業・兼業をスタートし、職員業務との両立を実現。また教員同士がTeamsを活用した情報共有を行う・授業以外の保護者対応などの業務も連携を取るなど、滞りなく動けるチーム体制を整える工夫が功を奏しました。
私が特に素晴らしいと感じたのは、社会との接点が生まれたことによって組織内が活性化し、顧客価値(子どもたちの自己肯定感・社会への関わりなどのスコアアップ)につながっていることです。
人的資本経営というと、つい自組織内に閉じた人材活用を考えてしまいがちです。しかし、地域社会や別組織などの“外”に貢献することは、これまで持っていた権限や社内だけ通用する暗黙知に頼らずに、相手に共感しつつ、相手と共同しやすい形式知をベースに仕事をしなければならないということです。逆に、外の組織での体験後に自組織に戻った際には、力に頼らない共感力やより普遍的な共創力の発揮が期待できます。
「自組織が育てた人材が外で活躍する」と考えると、今ある資源が流出したように感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、外で得てきた知見に対して“関心を持って”聞くようにすれば、自組織が成長する鍵を見つけることが可能です。
異なる業界の世界観・構造・機能を把握して持ち帰り、自組織と新たに結合するところまで推進できれば、副業・兼業推進の価値は格段にアップします。だからこそ、今後、企業は副業を単に「容認」するだけにとどまらず、「自組織の競争力を強化するヒントを得られるもの」という視点で捉え直し、「積極的に推進」していく必要があると感じます。
「人材価値循環への投資」に関する取り組み―事例2
元事業ライバルたちの協業による「収益拡大」と「後継者育成」の実現
―宮城県漁業協同組合 七ヶ浜支所―
取り組み内容:
宮城県宮城郡にある七ヶ浜町の海苔養殖業は、個人事業者の海苔漁師たちが競合していたが、東日本大震災で加工施設が壊滅的な被害を受けたことをきっかけに協業をスタート。協業したことで各社の「秘伝」ともいえるノウハウが詰まった海苔ができ上がり、品質が飛躍的に向上。ブランド化・取引単価の上昇・施設共用による経費削減や、ひとりあたりの収益増加を実現した。こうした変化により、新規就業者にとっても魅力的な仕事となったため、県内外から意欲的な人材の受け入れも可能に。進んでいなかった世代交代への準備も進んでいる。
課題:高齢化・後継者不足、震災による壊滅的な被害
実施背景:七ヶ浜支所は、従前からグループ化による設備投資・後継者育成の実現を進めたいという意向があった。また、震災による被害は甚大で個人レベルの復旧が難しかったため
他社で活かせるポイント:
・得意分野を担当する分業制を推進し、横一列の組織でも衝突しない協業体制を構築したこと
・地域社会の活性化の重要性を伝えて協業推進したことで、収益拡大・後継者育成という価値を生み出したこと

*お名前、肩書等は『GOOD ACTION AWARD』受賞当時のものです
藤井:七ヶ浜支所は他の第一次産業と同様に、高齢化・後継者不足に悩む海苔漁に関わる個人事業者が多く、以前からグループ化による協業を提案していました。しかし、家業の歴史・誇りが障壁となり、グループ化には至らずじまいでした。
しかし、震災によって加工施設が崩壊。事業者単位での再建が難しいことから皆で協業するという形に踏み切ることになりました。ただ、加工方法は事業者ごとに異なる部分も多く、それぞれの意見が衝突することもしばしば。そこで、業務範囲を決め、分業化して進めるようにしたところ、協業がスムーズに進むようになりました。
七ヶ浜支所のように、業務プロセスを大きく変える場合は、危機意識が発端となるケースは多いものです。人的資本経営というと、組織内で能力を循環させるイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、七ヶ浜支所のようにお互いに持っている能力を開示し、得意な分野を担当する協業形式を取れば、それぞれの得意を最大限に活かせます。
その結果、「ブランド化」という大きな競争力につながったことは、個人の能力をライバル企業・地域社会・その他の組織と分かち合うことの価値を感じさせてくれる事例であり、加えて、「人的資本とは誰のものか?」「一企業のものか? 地域社会のものか? 日本全体のものか?」という問いを突き付けてくれる好事例だと思っています。
「人材価値循環への投資」に関する取り組み―事例3
市役所職員の壁を破り「副業で起業」。ビジネスの力で地域課題の解決を実現
―一般社団法人KAKEHASHI―
取り組み内容:
公務員として地域課題解決の取り組みに持続性を持たせるため、副業で起業という道を選んだ、横須賀市役所職員。地元野菜の販売拡大を目指す事業の立ち上げ、コロナ禍の影響を受けた事業者支援として、生花店に「活け花おけいこ定期便」事業を提案するなど、「職員という立場を超えて地元に関わりたい」という思いを実現している。現在はこうした事業を知った市民からの市役所に対するイメージが向上、他自治体職員から「同じような活動を自分の地域でも行いたい」という相談が入るなどの副次的な効果も表れている。
課題:市役所職員や有志活動の限界、市民の事業者・住民が持つ課題の多さ
実施背景:外部講師を招いた広報戦略研修を受けるなかで、外部の方とのふれあい、市民の方の課題意識を知り、職員の枠を超えて解決したいという思いを抱くようになったため
他社で活かせるポイント:
・目的にフィットする働き方を作るという、働き方の枠組みを再定義できたこと。それが自組織・他組織の活性化につながっていること
・従来組織では対応しきれない顧客(市民)ニーズに応えることで、イメージ向上という成果が生まれていること

*お名前、肩書等は『GOOD ACTION AWARD』受賞当時のものです
藤井:これは、公務員という働き方の枠を、「副業で起業」という形で乗り越えた事例です。それによって、「市民への手厚いサポート・地域社会とのつながりの深化・働き方の枠組みのアップデート」の3つを実現しました。
公務員というと、公平性を保つために特別な対応や、既存の枠組みを超えた活動はNGというイメージがあるもの。そこで副業で起業というアクションをとったことで、職員や有志活動の限界を乗り越え、大きな価値を地域社会に生み出しています。
今は民間企業もSDGsを意識した公共的な仕事が求められ、逆に公共系事業を行う団体には同法人のように民間的な成果を求める働き方が推進されていることを考えると、対局にいるものが相互浸透する流れがきていることを感じます。
人的資本経営も同様に、社内にある人的資源を地域に解き放てば、地域資源の価値が上がり、地域資源の価値が上がれば顧客価値が向上する。そのように、メリットを相互浸透するという高遠な思想で捉えれば、同法人のように市民・市役所・地域社会の“三方良し”が実現します。本取り組みは、そんな可能性を感じさせてくれる好事例だと思います。
従業員を内外の風に触れさせること。それが、人材の才能開花・企業の革新的な成長を生み出す
藤井:今回ご紹介した3団体の共通点は、従業員(職員・個人事業者)に他の組織や社会で学んでもらう機会を創り出し、それによるメリットの相互浸透を体感されていることです。
人材の成長というと自組織内での育成を思い浮かべてしまいますが、先に申し上げたように、両利きの経営のごとく、今は対局にあるものを包摂し、新結合することが成長につながっていく時代です。そのため、成長機会は自組織に閉じず、外から新たなものを持って帰ってきてもらって自組織を成長させるヒントを得ることが重要だと考えます。
その際、重要になってくるのが全3回の全てで申し上げている、“関心”ということです。外で積んできた経験について、関心を持って聞けば、ヒントになることは必ず見つかるはずです。むしろ企業側が「副業を推進するので、どんな気づきや学びがあったか、どんどん教えて欲しい。そして良いものは自組織に取り込んで欲しい」というスタンスで向き合えば、従業員側もノウハウや新たなビジネスの種を見つけて帰ってこようと動いてくれます。
この3回を振り返ってまとめると、「人材価値の向上」のために、一人ひとりをかけがえのない存在として接し、その人のある一面を見て「できる人・できない人」と分類しないこと。
その人が「できること・できないこと」を切り分けて認識し、適材適所に配置して、人材の才能開花を最大限支援することで「人材価値の活用」を叶えること。
さらに社内だけの枠組みにとらわれず、人材が内外の風に触れる機会を作り、内にも外にも今までになかった価値を還元してもらう「人材価値の循環」の仕組みを整えること。
これらに取り組むことが、人的資本・企業の持続的な価値向上につながると認識して取り組んでいただければ幸いです。
ご紹介した事例のなかで、似た課題を持ったもの・自社が目指す理想を実現しているものなどがあれば、それらを参考に、全ての人材がイキイキと才能開花する人的資本経営の一歩を踏み出していただけたら大変嬉しく思います。
プロフィール/敬称略
※プロフィールは取材当時のものです
- 藤井 薫(ふじい・かおる)
- 株式会社リクルート HR統括編集長
HR統括編集長。『リクナビNEXT』編集長。1988年リクルート入社以来、人材事業に従事。『TECH B-ing』編集長、『Tech総研』編集長、『アントレ』編集長、リクルートワークス研究所Works編集部、リクルート経営コンピタンス研究所を歴任。デジタルハリウッド大学客員教授、情報経営イノベーション専門職大学客員教授、千葉大学客員教員。厚生労働省・採用関連調査研究会の委員歴任。著書に『働く喜び 未来のかたち』(言視舎)
関連リンク
【リクルートの人的資本経営】
- 人的資本経営のヒント~革新に挑む中堅・中小企業事例を『GOOD ACTION AWARD』に学ぶ〜 「人材価値向上への投資」編(コーポレートブログ)
- 人的資本経営のヒント~革新に挑む中堅・中小企業事例を『GOOD ACTION AWARD』に学ぶ「人材価値活用への投資」編(コーポレートブログ)
- 今、世界が注目する『人的資本経営』の実現モデルとは?“働く人”こそ企業の競争優位性を生み出す時代を見据えて(コーポレートブログ)
- レポート「人的資本経営の潮流と論点 2022」(プレスリリース)
- リクルート、「人的資本経営コンソーシアム」に発起人として参画(プレスリリース)
- 「人的資本経営」の実現に向けた課題とは? ~学習院大学教授 守島基博氏と考える“潮流と未来”(コーポレートブログ)
【GOOD ACTION AWARD】