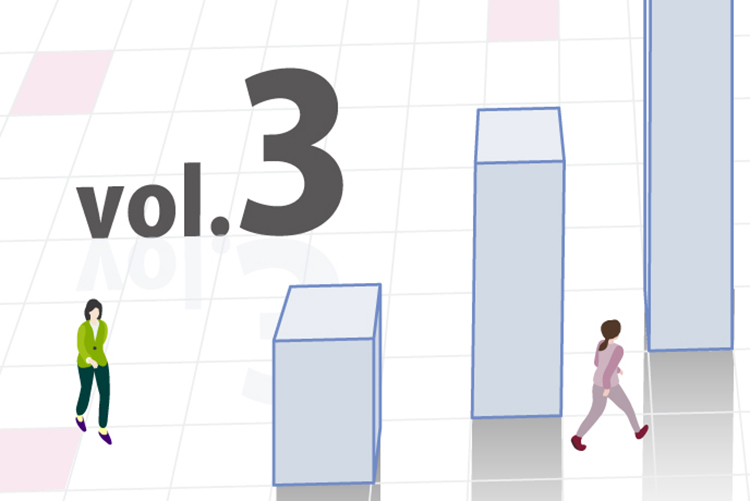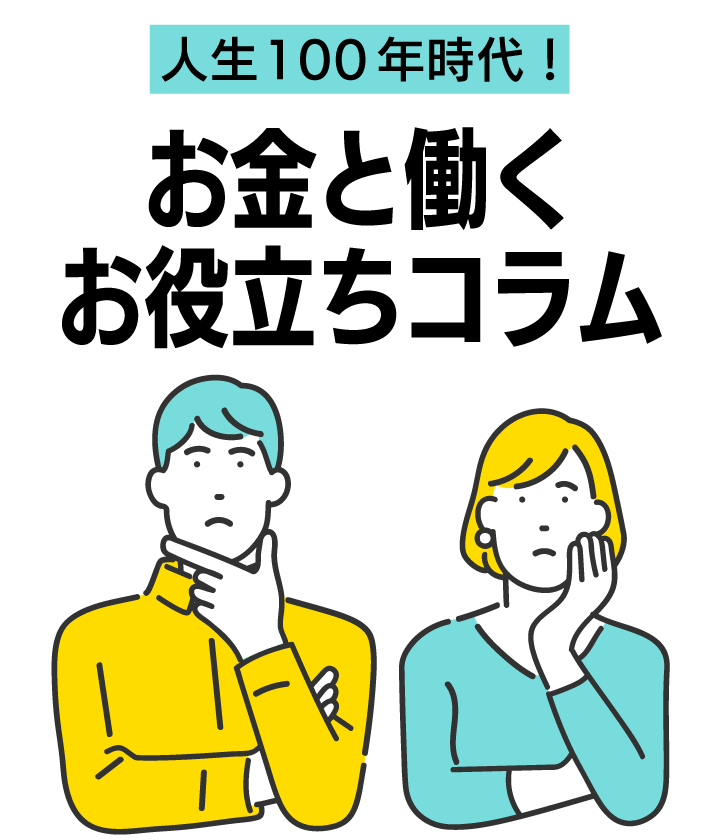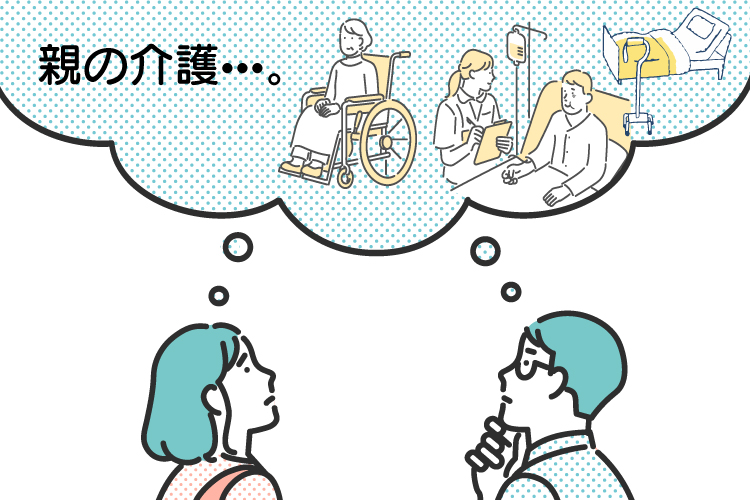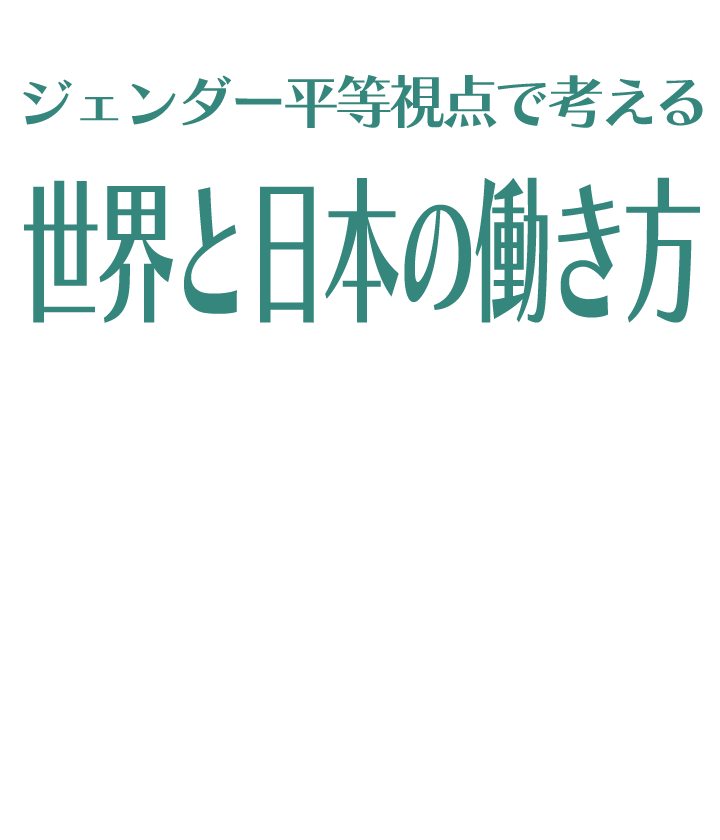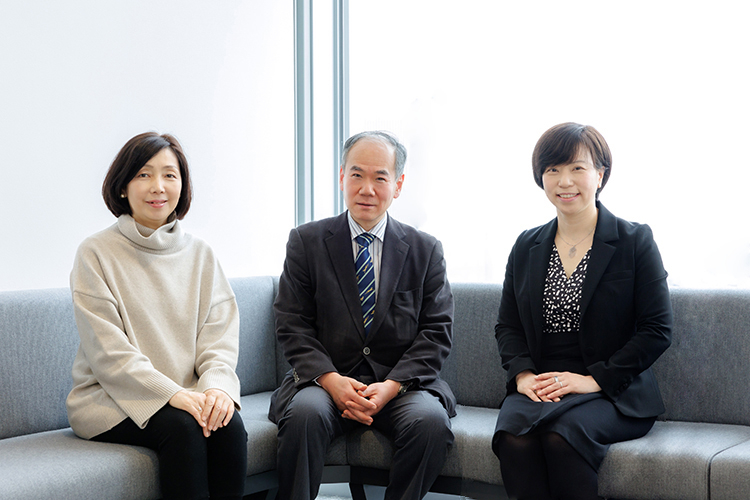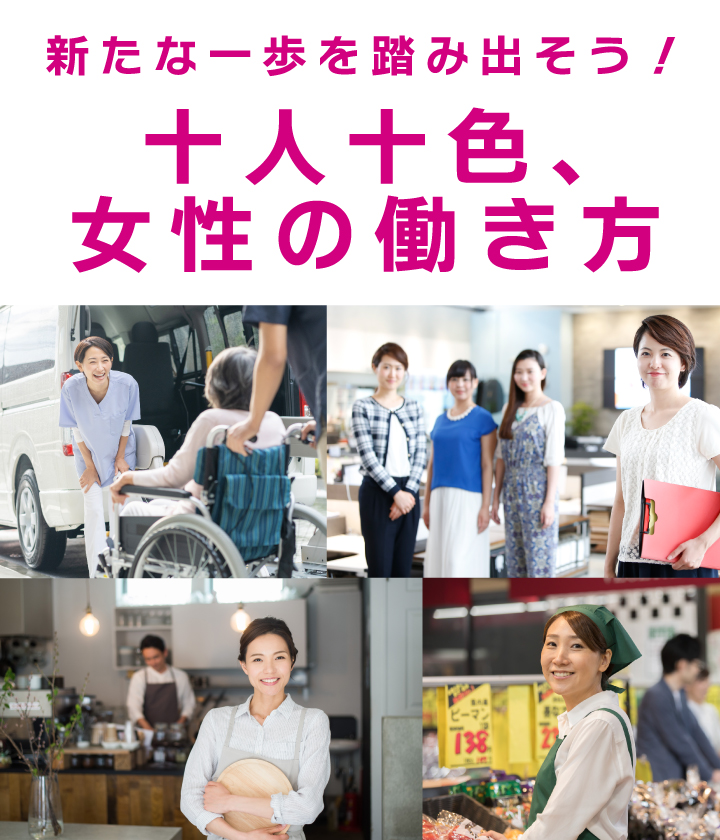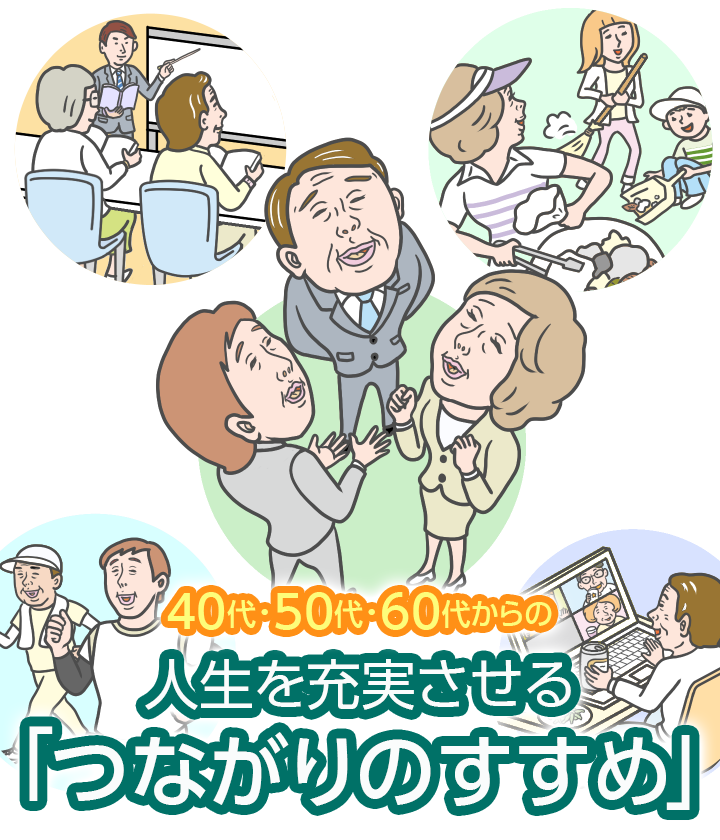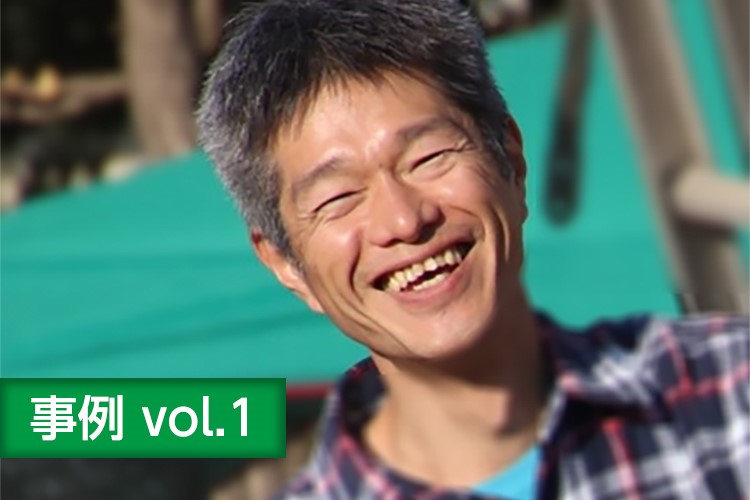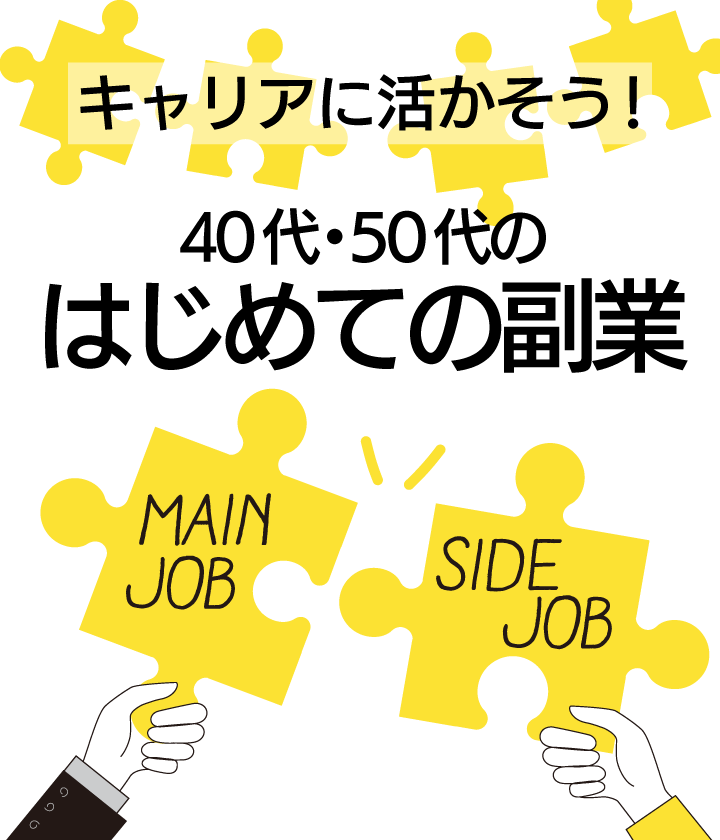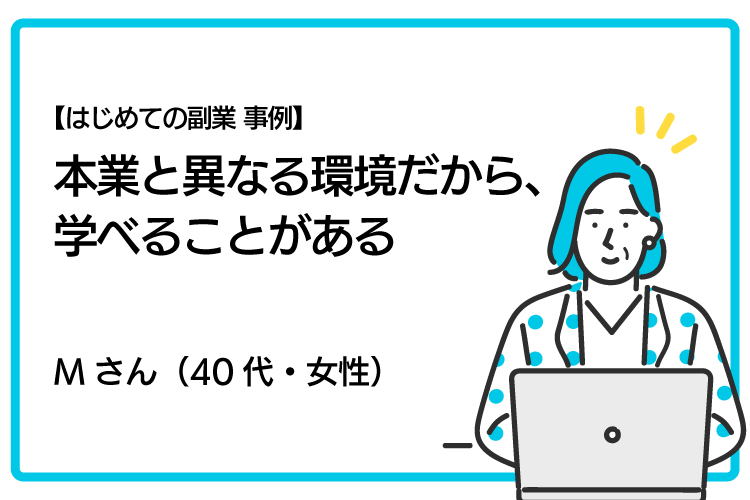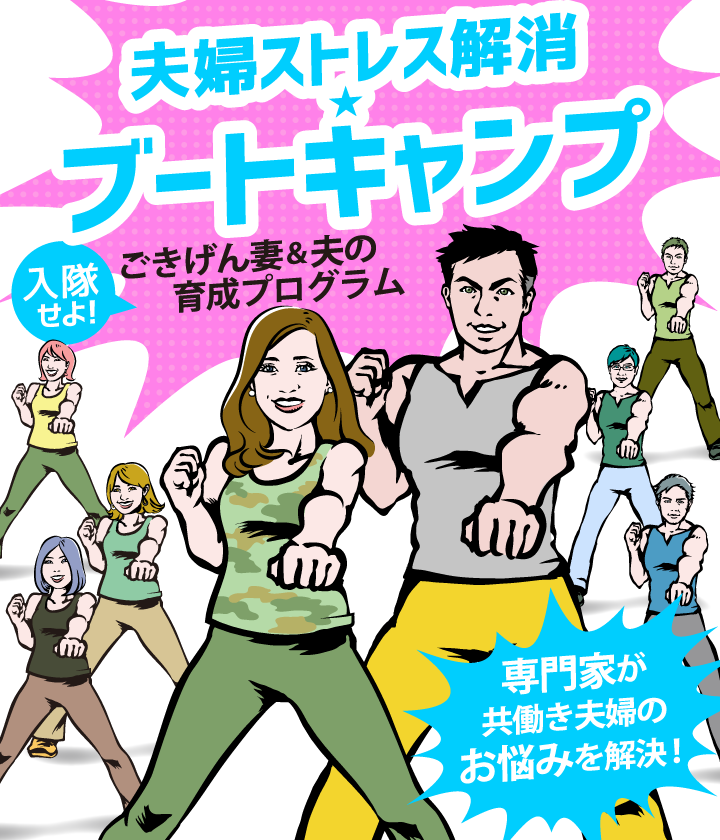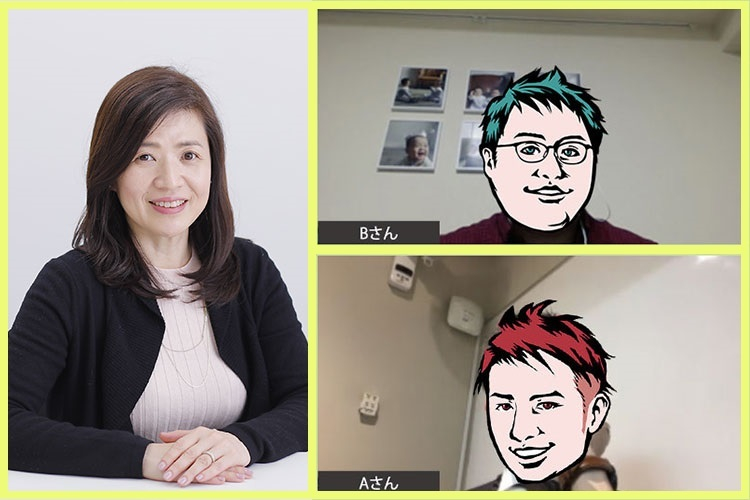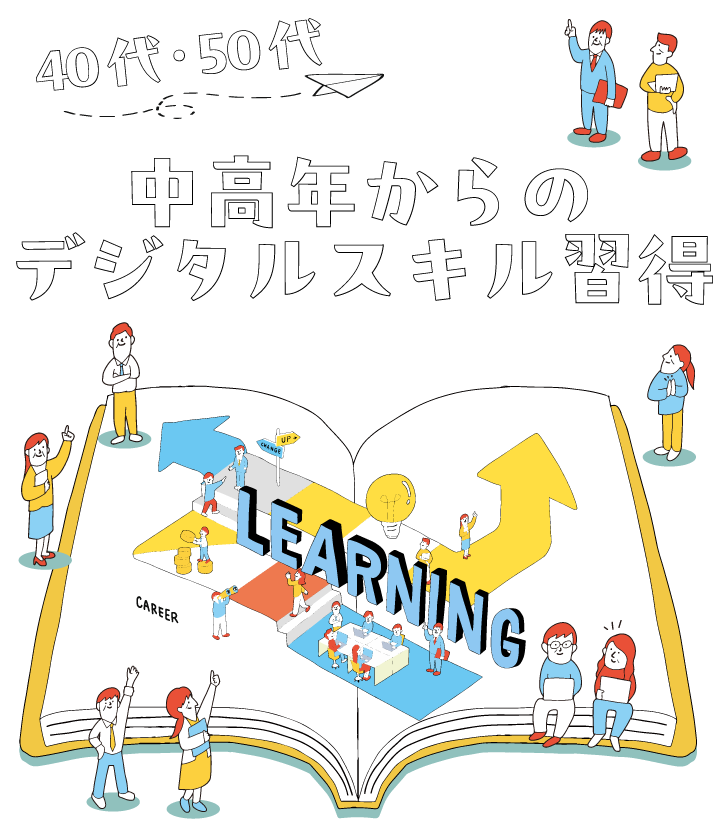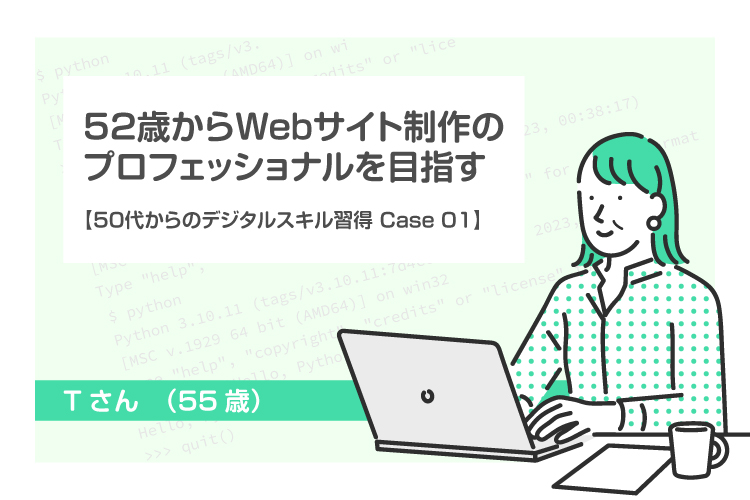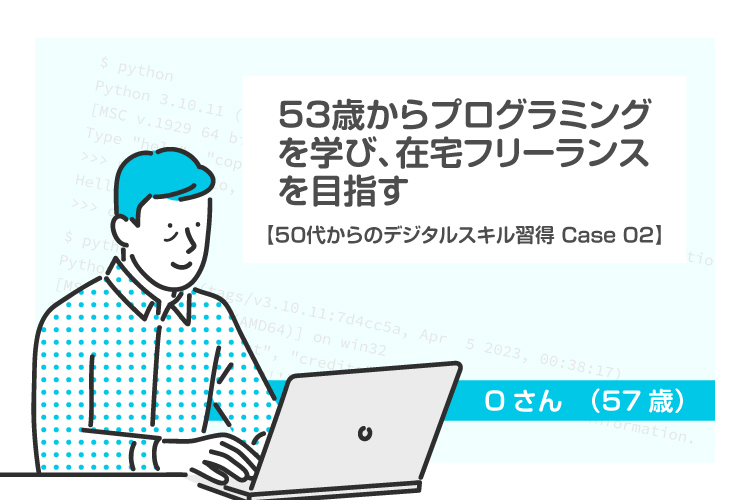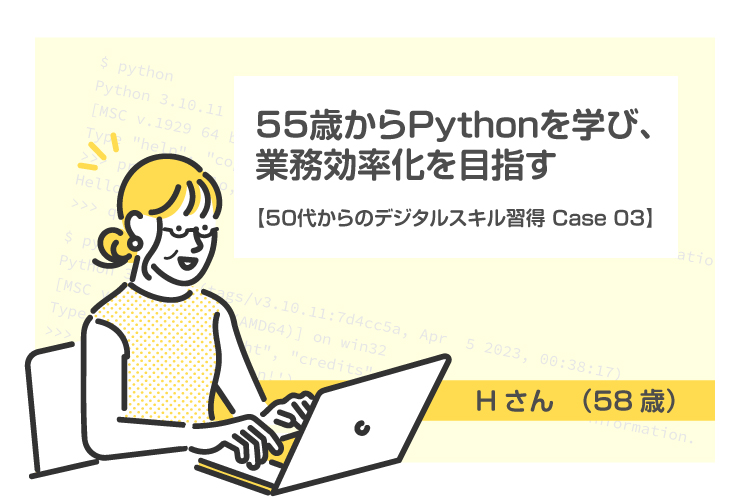育児や介護などで働き方に制約のある社員が増える中、企業は両立支援の仕組みを充実させている。ただ制度を整えるほど企業の負担が重くなったり、同僚に仕事のしわ寄せが及んだりするジレンマもある。企業はどこまで多様な働き手に「配慮」すべきか、リクルートワークス研究所主任研究員の大嶋寧子と研究員・アナリストの坂本貴志が話し合った。
長期的な能力形成には「配慮」も必要
――まず従業員に対する配慮について、お二人の基本的な考え方を聞かせてください。
坂本:企業は生産活動を行う場であり、あくまで社員のアウトプットに対して報酬を支払うべきだという考え方もあります。例えばケアを担う間の休業制度など、一定の支援は必要だと思いますが、ケアを理由に仕事を休んでいる間はパフォーマンスがゼロになるのに企業全体が報酬を負担するとなれば、対象外の従業員が不公平を感じる場合もあるかもしれません。アウトプットに見合わない報酬を支払うということについては注意も必要です。
大嶋:ペイフォーパフォーマンスは大原則ですし、各種の支援制度によって企業負担が増えているのも事実です。ただ一方で、仕事にフルコミットできない社員は一律にパフォーマンスが下がるとみなし、労働時間だけを基準に報酬を引き下げることには違和感を覚えます。ケアのため仕事をセーブすると、役割や評価が大幅に下がり、それまで積み上げてきたキャリアが大きく後退してしまうケースも多く見られます。
坂本:長い職業人生の中、ライフに重きを置く期間はあってもいいと思います。その間、フルコミットでない働き方に変更できる仕組みも必要です。ただその場合、数年間育休を取るなどしてキャリアに空白が生じた社員と、働き続けている社員の能力や経験、スキルに差が生じることは、現実問題としてあり得ると思います。例えば、シングルで仕事に一生懸命に取り組み、継続的に高い成果を出している社員の立場もあります。報酬や昇進、家族との時間のすべてを自分の思い通りにコントロールすることは簡単ではないですし、実際にはトレードオフになることもあるでしょう。
大嶋:実際問題として、キャリアに空白がある人とそうでない人で能力や経験、スキルに差が生じる場合もありますよね。その差を取り戻せる機会があることが大事だと思うので、それに必要な仕事をアサインすることが、本人の意欲を高め長期的に能力を発揮してもらうことにつながると思います。一方で、育児や介護を担うことで過去に積み上げた実績が、不当にリセットされる場合もあり、それは問題です。ケアを担う間は役割や職務の変化に応じて報酬水準を下げても、ケアの負担がなくなったり、小さくなったりした際には元の位置に近い水準から再出発できるようにすることも必要ではないでしょうか。