明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科教授
リクルートワークス研究所特任研究顧問
野田 稔さん
野村総合研究所、リクルートフェロー、多摩大学教授を経て、現職に至る。組織論、経営戦略論を専門分野とし、組織で人がいかに行動するかということを研究。組織論、リーダーシップ論に関する書籍も多く、人材マネジメント分野の開拓者の一人である。
ミドルシニア 「人手不足時代のミドルシニア活躍 ~50代・60代がモチベーション高く働き続けるには~」

2030年問題、2040年問題という言葉が示すように、少子高齢化により今後も人手不足が深刻化すると予測される日本社会。労働力の中核を担う第2次ベビーブーム生まれの団塊ジュニア世代が50代となり、ミドルシニアの活躍は、社会や企業にとってますます重要になっています。そこで、彼らの活用やキャリア支援について、企業の組織論やマネジメントの専門家である明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授の野田 稔先生にインタビュー。【前編】では企業がミドルシニアの活躍促進に取り組む上でのポイントについてお話しいただきました。【後編】となるこの記事では、40代半ば以降のミドルシニア世代へ、これから役職定年や定年といったキャリアの大きな転換点を迎える上で大切にしたい意識や考え方、そして明日から実践したいアクションを紹介。人生100年時代とも言われる社会で、豊かな人生を送るためのアドバイスをお届けします。
※この記事の内容は、リリース当時(2025年3月現在)のものです。

明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科教授
リクルートワークス研究所特任研究顧問
野田 稔さん
野村総合研究所、リクルートフェロー、多摩大学教授を経て、現職に至る。組織論、経営戦略論を専門分野とし、組織で人がいかに行動するかということを研究。組織論、リーダーシップ論に関する書籍も多く、人材マネジメント分野の開拓者の一人である。

― 【前編】でお話をいただいたように、企業にとってミドルシニア世代の活用は今後ますます重要になってくる一方で、ミドルシニア本人は、役職定年や定年といった時期を迎えてなお働き続ける意義を、どう捉えるとよいでしょうか。
もちろん、何歳まで働くかは個人の自由ですし、早期リタイアして悠々自適に生きることに憧れる気持ちも分かります。ただ、私は長寿命社会かつ変化の激しいこの時代において、働かないという選択は二つの意味でリスクが高いと考えています。
一つは時間を持て余して寂しくなること。特に今の50代~60代が若手の頃はハードな働き方が当たり前で、これまで仕事一辺倒だった人も多い世代です。そんな人は往々にして趣味もなく職場以外の人とのつながりも希薄だから、仕事を辞めても特にすることがない。余暇を十分に楽しめるならいいのですが、人とのつながり、社会とのつながりという点では少し物足りないと感じてしまうかもしれません。
― 社会とつながり、生きがいを感じるためにも、働き続けた方がよいということですね。
そうですね。そして、もう一つは金銭的なリスク。年金+貯金を切り崩すギリギリの生活では、自分や家族に予期せぬ出来事が起きるとうまく立て直しができず、あっという間に生活が破綻してしまうことも。またこの年齢で一度働かない選択をしてしまうと、その後、年齢とともに気力体力が衰えていく中で再び働くことは、思った以上にハードルが高いものです。なにも現役時代と同様に働く必要はありません。1日数時間、週何日かでも働き続け、できるだけ長く定期的な収入を得ることができれば、老後の生活も安定しますから。 今のシニア世代の場合、支給される年金で生活をすることを前提に考えると、持ち家の夫婦なら月に10数万円。夫婦で分担するなら1人5~6万円くらいをめどに働き続けると、生活にゆとりを感じながら暮らしていくことができると言われています。この水準をできるだけ長く維持して、貯蓄を切り崩す時期を後ろ倒すことが、人生100年時代を安心して暮らす方法の一つと言えるでしょう。
― それくらいなら、確かに週5日のフルタイムで働かなくてもいいですね。シニアはバリバリ働いてたくさん稼ぐことよりも、“薄く長く”続けることが重要だ、と。
必ずしも今までのように稼がなくてもいいということです。とはいえ「嫌いな仕事」や「つまらない仕事」なら続けたくないですよね。長く続けるには、「好きな仕事」や「得意な仕事」、「挑戦したい仕事」であった方がよいと思います。だからこそ、シニアになっても楽しく働き続けられるように40~50代のミドル世代のうちから準備が必要なのです。

― では、ミドルシニアが今後も長く働き続けるためにどのような準備が必要なのでしょうか。
【前編】でもお話しした通り、まずは「キャリア自律」です。会社に自分のキャリアを委ねるのではなく、自ら主体的にキャリアを作っていくマインドに変わらなければ、前向きに準備もできませんから。特にミドルシニアは、「自分の座る椅子(ポジション)は自分でつくる」くらいの気概でいてほしいです。ポジションを“降りる”のではなく、“譲る”。後身に席を譲り、自分は次のステップに進むのだというスタンスを持ちましょう。
では、自律的なキャリア形成をどうすれば実現できるのか。その答えは少々矛盾するようですが、「周囲からの期待」を意識するとよいでしょう。キャリアは自分だけで作るものではなく、周囲との関わりの中で自分の可能性に気付くことも多いからです。私はかつて「キャリア自律をして社会で活躍しているビジネスパーソン」数十名にインタビューしたことがありますが、彼らに共通していたのも、「周囲からの期待を巧みに集めて自らの原動力にしている」ことでした。
― 会社や職場などの周囲からの期待が、自分のキャリアを考えるヒントになるんですね。
そうです。そして、会社から期待されることは、年齢を重ねるにつれて変わってくるということも理解してほしいですね。例えば、新入社員の場合、まずは「自社の人になる」、つまり入社した会社の業務や仕組みを理解することを求められます。20代後半になれば、「優秀な人材になって」と言われます。これは、ポータブルスキルと自社特有のスキルの両方を身に付けてほしいということ。30代では「専門性」が問われます。自分自身の旗印となるような強みや専門性を、自分で見つけそれを自ら磨くことを期待されるわけです。40代は、自分一人でできる以上の成果を求められる機会が増えますから、組織や集団で事を成し遂げる「リーダーシップ」が必要とされます。そして、50代。ミドルシニアの皆さんへの期待は、先ほども言ったように「自分のポジションは自分でつくる」こと。社内外を問わず、次のキャリアを自分で考えて動き出すことを期待されているわけです。
ただ、自分の可能性を信じられなければ、主体的に自分の進むべき道を選んで飛び込んでいくことも、そのために必要な努力もできません。とはいえ、日々いろんな出来事が起こる中で、自分一人で可能性を信じ続けられる人は少数派。だからこそ、周りの人たちから「いいね」「すごいね」と言われ、期待されていると実感するプロセスが必要なのです。
― 自分に期待を向けてもらうにはどうしたらよいのでしょうか。
何が得意で何が好きで嫌いなのかといったあなたの個性、「私は何者か」を周囲に知ってもらえなければ期待を集めることはできないでしょう。だからこそ、まずは就活生がやっているように、自分自身を見つめ直してみてください。 特に私が推奨しているのは、小学高学年~中学生くらいに得意だったことや没頭していたことなどを思い返してみること。そこには自分の生まれながらのCan=強みともいうべき要素(原点のCan)が眠っていることが多いです。その一方、ミドルシニアには社会人になってから身に付けた能力や知識・経験(大人のCan)もありますよね。この「原点のCan」と「大人のCan」を書き出して自分の好きや得意を自覚していくことがファーストステップです。
― いわゆる「自己分析」や「キャリアの棚卸し」に近いですね。
それができたら、Canの一覧を周囲の人に見せて、あなたのCanが活かせる仕事を作ってもらいましょう。例えば「人の揉め事を仲裁するのが昔から得意なんだね。それなら渉外部の仕事も向いているのでは?」といった具合。これが周囲からの期待です。
自分一人で「キャリアの棚卸し」をしても、今の仕事の延長線上に落ち着いてしまうことが多いですが、それは自分自身でCanの活かし先を考えても発想が広がらないから。一方で他人に無邪気にCanを組み合わせてもらうと、自分が想像していなかったようなジョブに着地することもあります。それがきっかけとなって「言われてみれば、自分には○○という可能性もあるかもしれない」と新たなキャリアにも前向きになれるのです。

― キャリアに対するマインドチェンジが大切な一方で、実際にミドルシニアが自分のやりたい仕事を長く続けるにはどのようなアクションが必要でしょうか。
意識してほしいのは「リスキリング」です。大きなキャリアチェンジをする場合はもちろん、今の仕事を続けるにしても、役職定年や定年のタイミングで立場や環境や業務内容の変化が少なからず発生するでしょう。そこで自分の強みを仕事にうまく活かすには、新たな職場に適応するための学び直しが必要になってくるはずです。
そのとき、ミドルシニアに意識してほしいのは「新人に戻った気持ちで学ぶ」こと。やりがちな失敗例は「前職では~」「前の部署では~」と何かにつけて過去の経験を引き合いに出す、“ではのかみ(出羽守)”になってしまうことです。これでは新たな知識を十分に得ることもできませんし、周囲との信頼関係も構築できません。もちろんこれまでの知識・経験には価値があるので、何もかも迎合しすぎる必要はありませんが、分からないことは分からないと認め、素直に教わりましょう。
― まだ具体的な道が見つかっていない場合や、将来の変化に備えて今から準備をしておきたい場合は、どんなアクションを行うとよいですか。

普段の環境からちょっとだけ外に出てみることです。会社が認めているのであれば、副業をやってみるのもよいでしょう。もしくは関心があるテーマでボランティアをやってみてもよい。今の仕事はそのまま継続しつつ、いつもと違うことや興味のあることに手を出しみて、体験しながら将来の方向性を見極めていけばよいのです。これはつまり、自分のキャリアを全て会社に預けないというキャリア自律の具体的アクションの一つ。10年後に大きく飛び立つための滑走路=助走期間だと捉えて焦らず取り組めばよいと思います。
― 副業やボランティアだけでなく、趣味(遊び)でもよいのでしょうか
趣味もキャリアによい影響を与えると言われていますよ。直接的効用と間接的効用があるのですが、前者は、「趣味が高じて仕事になる」というパターン。例えばジャズが好きで定年後にジャズ喫茶を開業するといったことが、直接的効用の典型例です。しかし、趣味が仕事として成り立つところまで実現できる人はあまり多くありません。多くの場合は間接的効用。趣味を通じて知り合った人が、この先のキャリアのヒントをくれるというパターンです。
アメリカの社会学者、マーク・グラノヴェッターの研究結果からも、新しい仕事のチャンスをもたらしているのは、家族や会社といった毎日顔を合わせる人との結び付き「強い紐帯」よりも、趣味の仲間や学生時代の同級生といったたまに会う程度の「弱い紐帯」と呼ばれる人脈ネットワークからの場合が圧倒的に多いことが分かっています。
― 自分と深く関わっているはずの「強い紐帯」よりも、「弱い紐帯」がきっかけになりやすいのはなぜですか。
一つは、日常のコミュニティーが違うこと。異なる会社・業種・地域で暮らしている人だからこそ、いつもとは異なる視点であなたの能力や経験を評価してくれます。利害関係もないから意見も率直。また、自分の世界では当たり前にみんなが持っているスキルが、相手の世界では重宝されることも往々にしてある。「そういえば○○さんが得意だって言っていたな。ちょっと聞いてみようかな」なんて声が掛かるのです。だからこそ今、会社と家を往復しているだけの人は、趣味でも副業でもボランティアでも何でもいいから、第3、第4のコミュニティーを作ってネットワークを広げていくことが一番の将来への準備だと思います。
<おすすめ記事> 40代・50代・60代からの人生を充実させる-つながりのすすめ-

― ここまでお話しいただいたことを踏まえつつ、最後にミドルシニアが明日から今すぐ始めたいアクションについてアドバイスをいただきたいです。野田先生が言うようにキャリアには「滑走路」が必要だとしたら、年代別にやるべきことも違うはずですよね。40代・50代・60代のそれぞれのアクションを教えてください。
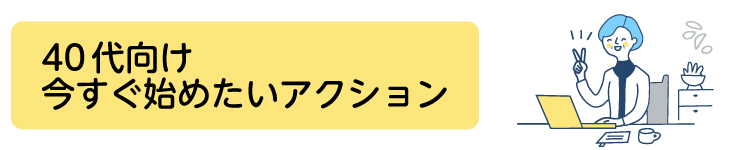
40代なら、まずは先ほどお伝えした「原点のCan」「大人のCan」を自分で見つめ直すところから丁寧に始めましょう。定年・再雇用と今の会社で過ごすとしたら、まだ15~20年近くあります。社外に目を向けてもよいですが、それよりも先に社内を広く見渡して、自分の好き嫌いや強みにマッチした仕事がないかを考えてみることをおすすめします。特に入社以来同じ部署・役割だった人は社内でのキャリアチェンジの可能性を探ってみましょう。 例えば営業一筋の人が人事も経験すると、営業で培ったコミュニケーション能力に人事的観点が加わることで、優秀なキャリアコンサルタントになれる可能性もあります。40代ならまだじっくりと時間をかけられるので、自分の強みを活かしながらこれまでとは全く違う経験をもう一つ、できれば二つくらいできるとよいですね。
また、機会があるなら「社内起業」にも挑戦してほしい。イチから事業を立ち上げる中でさまざまな経験ができ、キャリアのヒントになるからです。当然のことながらすぐにはうまくできないと思いますが、だったら社会人大学院などに通って学ぶことも40代ならじっくり取り組めます。また、そうした学びの機会で出会う仲間はまさしく「弱い紐帯」です。
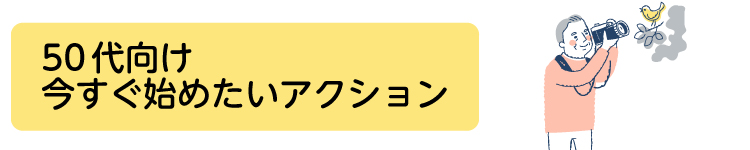
50代はそろそろ今の会社での先が見え始めるころ。40代よりも意識的に外へ目を向けることが大切です。例えば、趣味のない人なら、趣味を見つけることから始めてもいいと思います。いつの間にか辞めてしまった趣味をもう一度復活させたり、子どもの頃の習い事をもう一度始めてみたりするのもいいですね。ただ、メジャーな趣味だとコミュニティーが出来上がっていて、外から入っていく障壁が高く感じられる場合もあります。逆にマイナーな趣味だと人数が少ない分仲間同士の親近感が湧きやすいので、おすすめですよ。
あとは、具体的に将来の方向性を定めていくためにも、周囲の人とキャリアについて対話する機会を作ってください。自分の頭の中で考えるだけではなく、他の人に話してみることが大切。客観的なアドバイスをもらうという意味だけでなく、周囲に自分のやりたいことを発信しておくと、いつか誰かがそのチャンスをくれるかもしれないからです。話さないことには誰もきっかけはくれませんから、「チャンスの種を蒔く」感覚で話しましょう。そして、いざチャンスが来たら思い切って乗っかってみる、外へ飛び出してみるのもよいと思います。
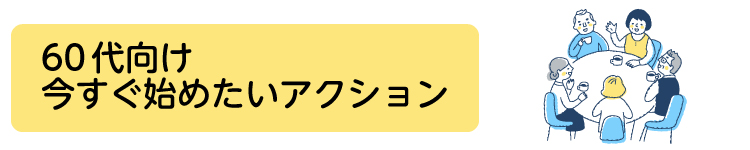
最後に60代ですが、やること自体は40代・50代と変わりません。でも、あまり時間的余裕はない。だからしっかりと準備してから踏み出すというより、準備とチャレンジを同時にやる。やりながら学ぶというくらいの意識が必要です。また、60代になると定年などで自分を取り巻く環境が大きく変わり、周囲との関係性も変化します。特に配偶者がいる人は、これからのライフプラン・キャリアプランをしっかりと話しておかないと、関係性に亀裂が生じてしまいます。熟年離婚に至った場合、女性はそうでもないのですが、男性は平均寿命が下がるとも言われているそうですから気を付けないと(笑)。周囲との関係を維持・構築し、孤立しないことが重要でしょう。
もちろん何歳になったとしても遅いということはありませんし、前向きに自らのキャリアを選択することに年齢は関係ない。ただ、ライフステージに連動して効果的な始め方が少しずつ異なるのも事実です。自分の将来を想像しながら、年代に合った適切な準備をしていけるといいですね。
50代以降のミドルシニア世代は役職定年や定年、再雇用といったキャリアの大きな転換期。この先も長く働く意欲があるからこそ、自分らしい働き方に悩むことも多いのではないでしょうか。
これからのキャリアや働き方を考えるためには、まずはこれまでにやってきたことや関心があることを振り返る。そこから自身の強みや周囲からの期待に気付くことが、今後のキャリアを前向きに選択することにつながります。もしすぐに具体的な将来像を描けないときは、興味関心があることで新しいコミュニティーとつながってみることから始めてみてください。例えば趣味やボランティア活動、副業などを通じた新たな交流は、異なる視点や新しいアイデアを得る機会となり、将来の可能性を広げてくれるでしょう。
こういった野田先生からのアドバイスは、この先のキャリアを前向きに選択するためだけでなく、自分らしく豊かな人生を送るためのヒントとも言えそうです。人生100年時代、今この機会に、新しい一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか