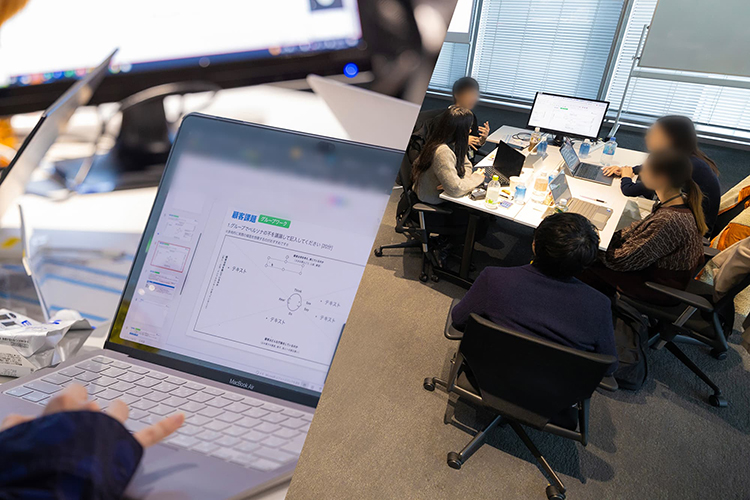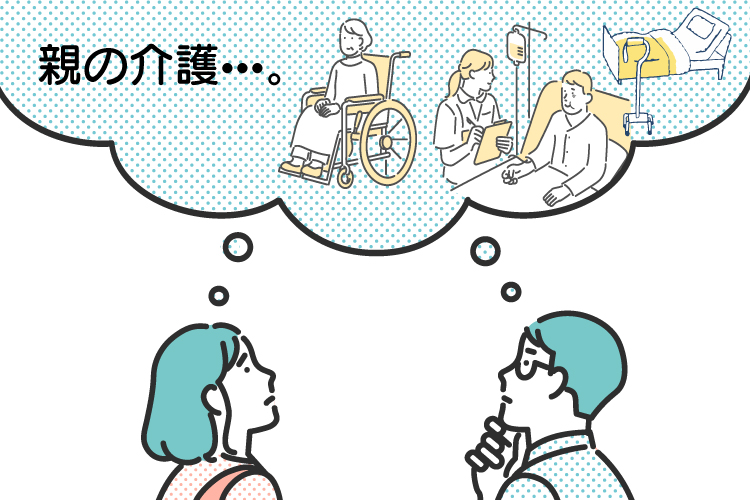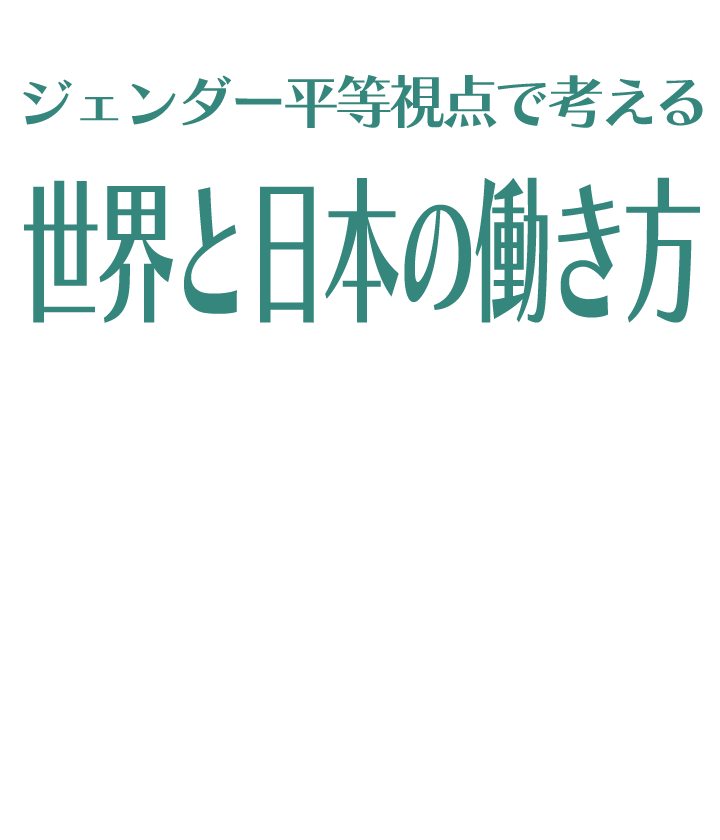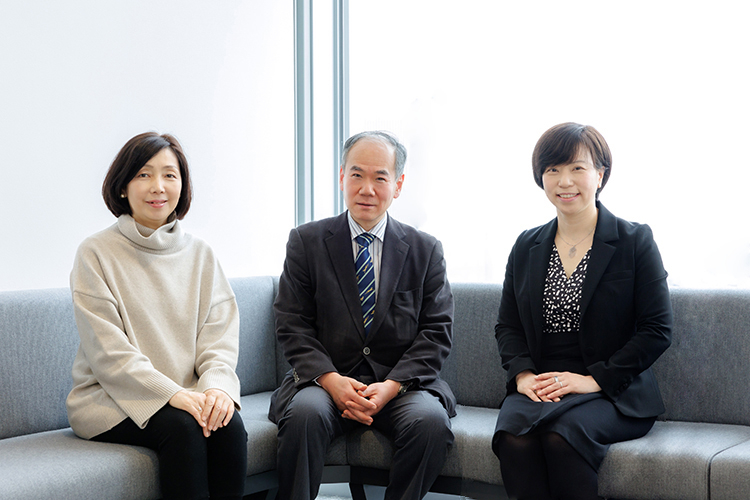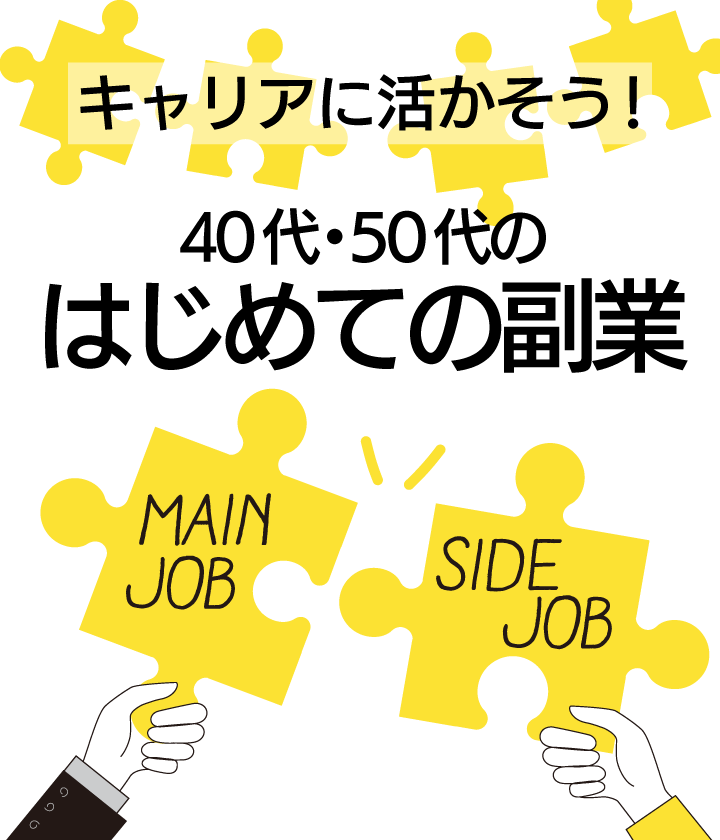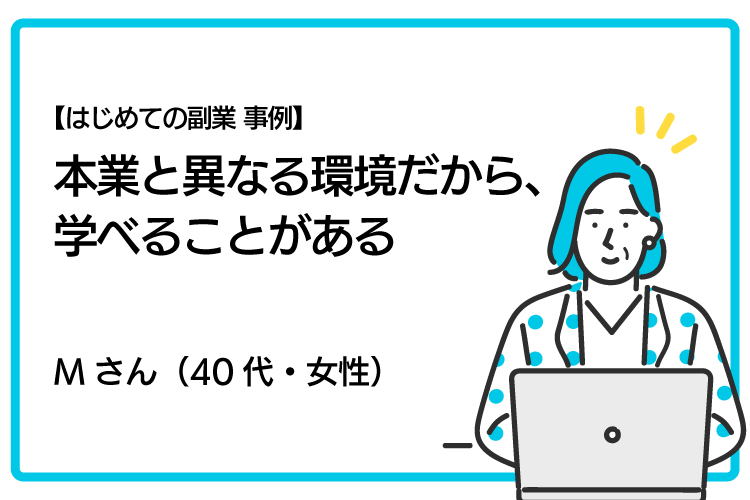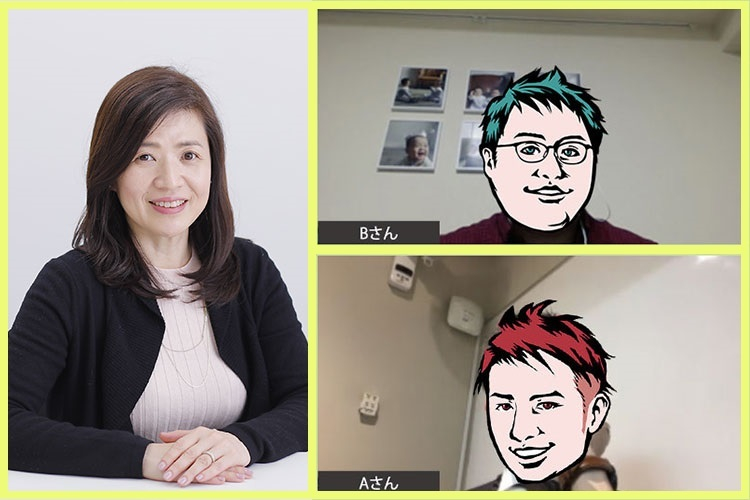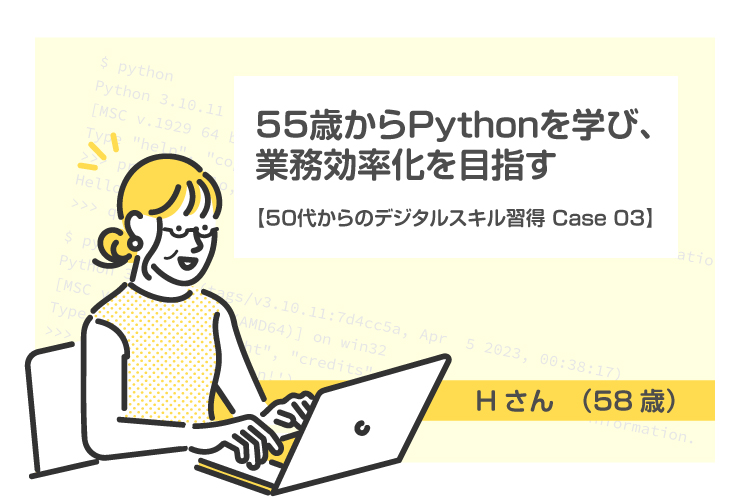ドイツ在住35年以上。母語の外側から文学と向き合ってきた日本人作家は、「言葉」から日本をどう捉えるのか。グローバル化の時代に求められる、姿勢を訊く。
2018年、アメリカで最も権威のある文学賞のひとつ「全米図書賞」の翻訳部門に"The Emissary"という作品が選ばれた。原題は『献灯使』、著者はドイツ在住の日本人作家、多和田葉子さんだ。日本人の受賞は36年ぶりだったことから、その知らせは快挙として、多くのメディアで伝えられた。
多和田さんは「母語の外側に出て、そこで感じるものから創作をしたい」と、大学卒業後すぐに渡独した人だ。若くして自らグローバルな環境に身を投じた多和田さんには、今の日本はどう見えているのだろうか。複雑に多様化する世界で、私たちが見失ってはならないものとは何だろうか。「言語」と「日本」と「グローバル」をキーワードに挙げながら、お話を伺った。
"私"を省略する世界と、そうではない世界がある
人を人たらしめるもの。そのひとつに「言語」があることを、私たちは普段、あまり意識していない。言語があるから、人間は他の動物より高度なコミュニケーションが取れるし、高度に思考できる。言語がなかったら、目に映る光景をどのように把握し、物事をどのように理解するのだろうか。こうした問いも、言語に乗ってやって来る。言語のない世界とは、もはや想像もつかない。
一口に言語と言っても、その種類はさまざまだ。一説には、7,000以上もの"living languages(実際に使用されている言語)"があるとも言われている。それぞれの言語は、使われる人や土地の影響を多分に受け、独自の発展を遂げてきた。人と母語は密接に関わり合っていて、そこには翻訳でくみ取りきれないニュアンスが必ず存在する。
もしかしたら、使う言語が違うと、世界が全然違って見えるのではないか----中学校で英語を習い始めてから、多和田さんはそんな思いをよく巡らすようになった。