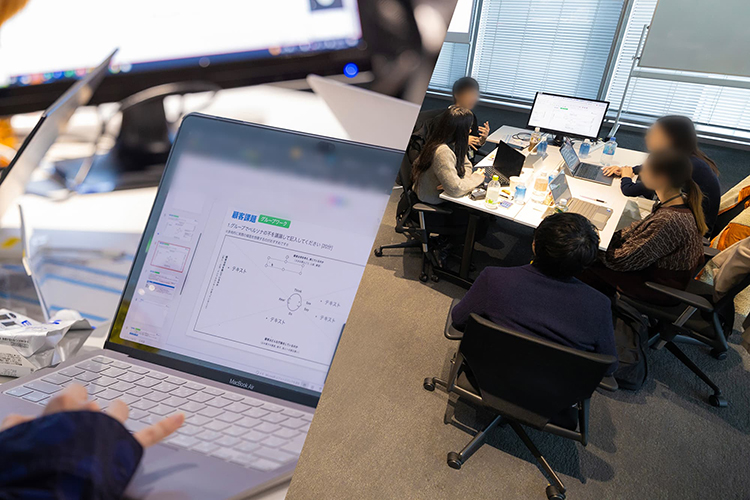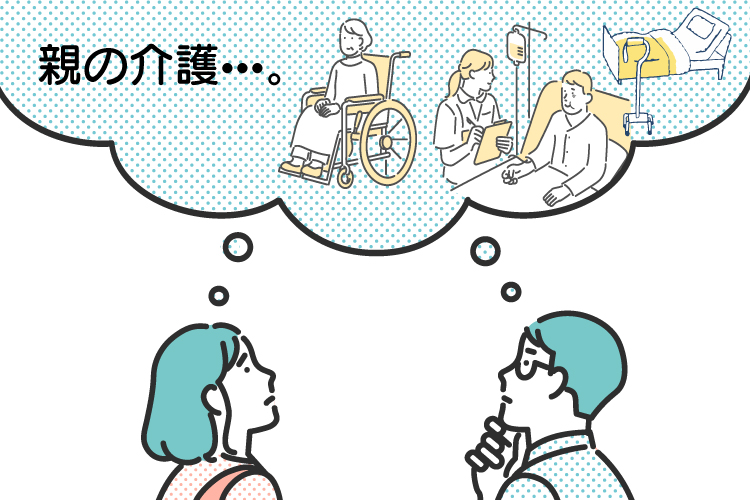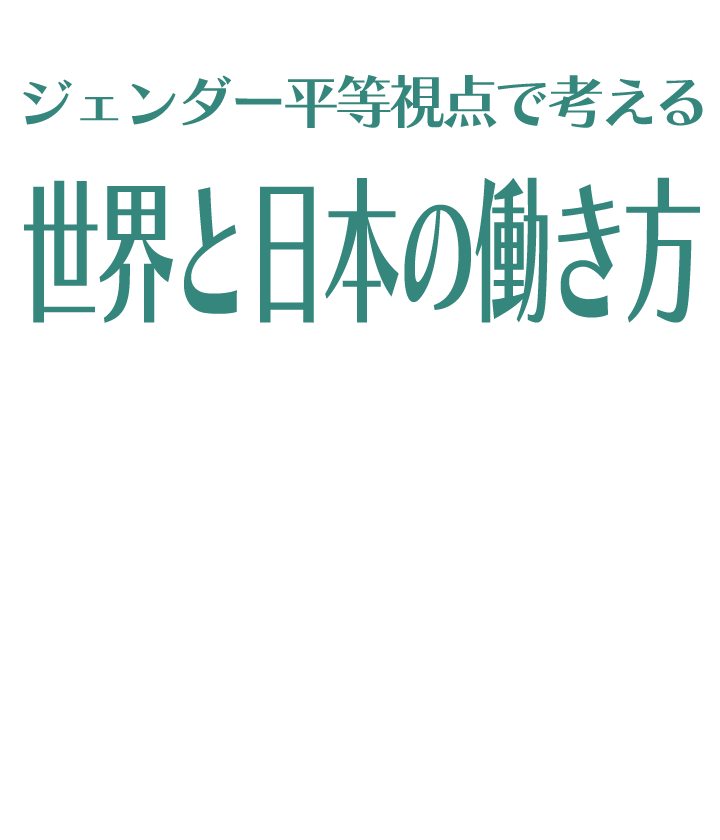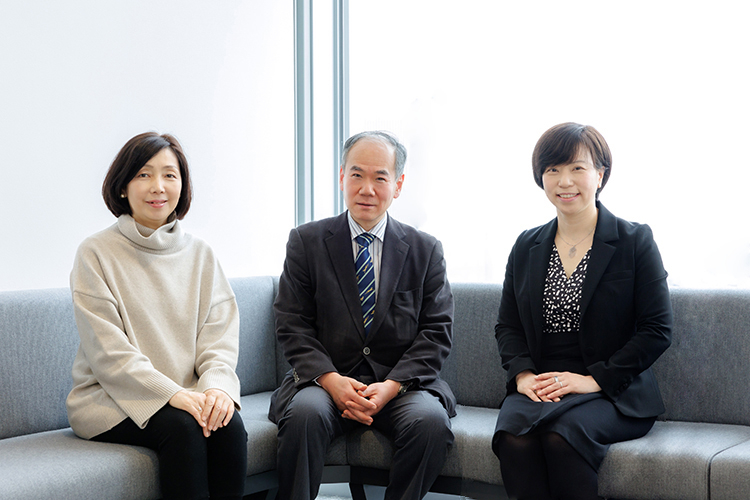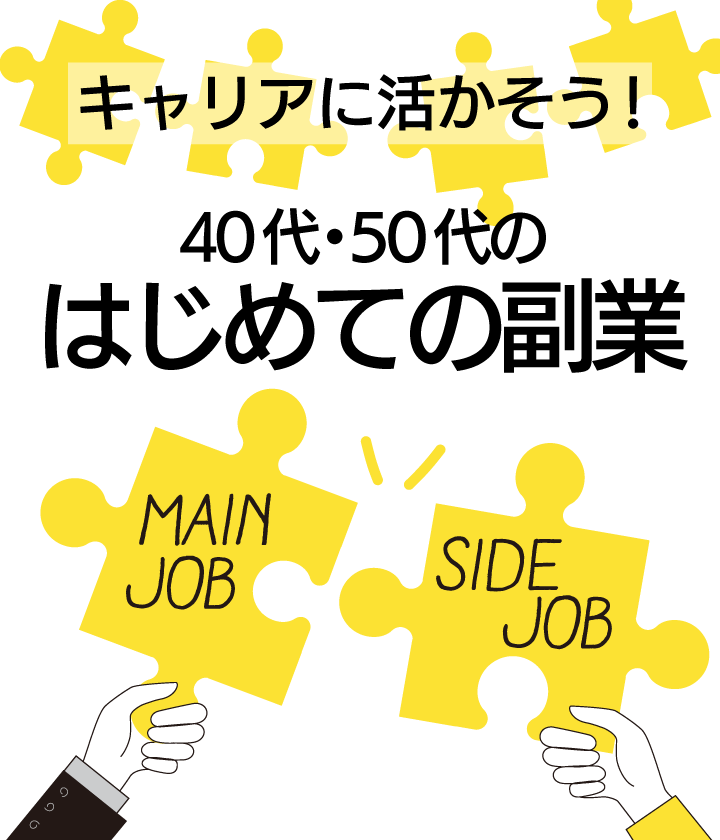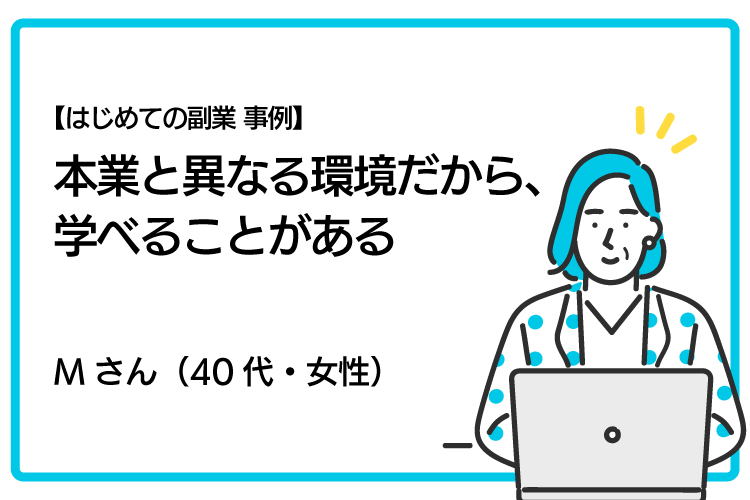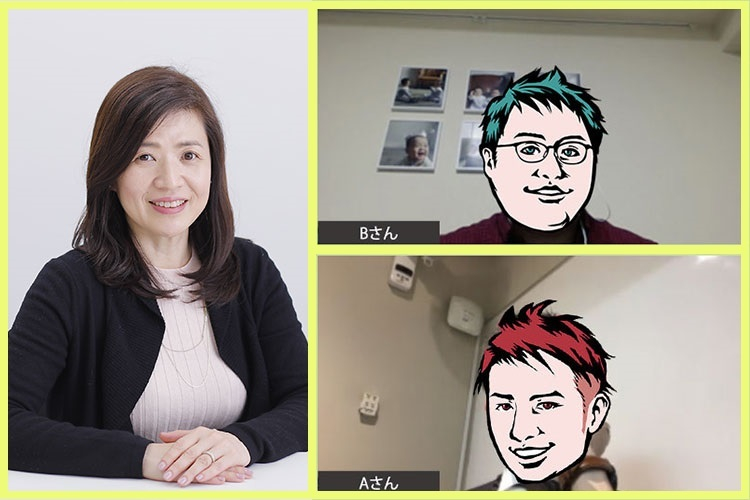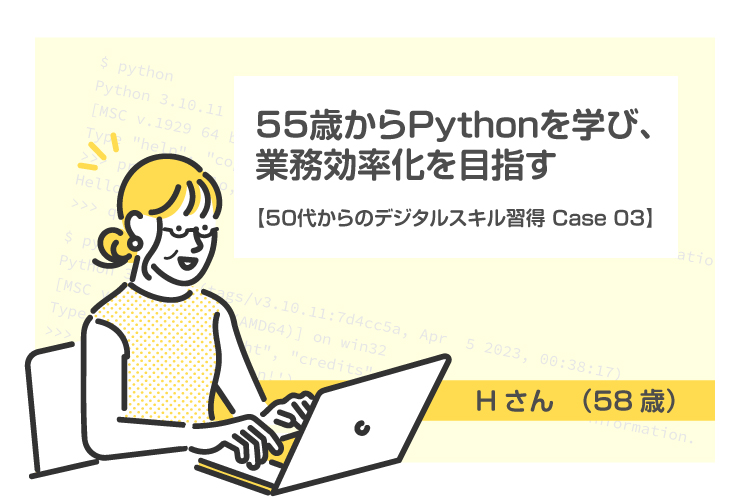多様な人材が参加し、活躍する組織には何が必要なのか。「やさしい日本語」研究を手掛ける一橋大学 庵功雄教授に、バックグラウンドが異なる人々と共生・共創していくための秘訣を聞く
「たいふう19ごう は おおきくて とても つよいです。 き を つけて ください」
2019年10月、NHKの公式アカウントがSNSでこう呼びかけたことが話題となった。これは、日本語を母語とする人たち(日本語母語話者)が標準的に使用する言葉よりも文法や単語をシンプルにした「やさしい日本語」。外国人(以下、「非日本語母語話者」の意味でこの表現を用いる)に分かりやすいのはもちろん、日本人にとっても外国語より扱いやすく、言語的背景の異なる人たちが一つの社会で共生していくために有効なアプローチだと言えるだろう。
このような、違いを埋めるために活用される「やさしい日本語」は、企業が取り組むダイバーシティ&インクルージョンの施策とも共通点が感じられる。「やさしい日本語」の普及の道のりには、言語的背景の違いに限らず、国籍・性別・年齢などを問わず多様な人材が活躍するためのヒントがあるのではないか。そこで今回は、「やさしい日本語」研究を牽引する一橋大学国際教育センターの庵功雄(いおり・いさお)教授にインタビュー。「やさしい日本語」の歴史や活用のポイントから、企業が多様性を実現するためのコツを探った。
情報伝達手段としてだけではなく、社会に参加するための共通言語として
「やさしい日本語」が社会で活用される契機となったのは、1995年の阪神淡路大震災。
当時、公共の情報発信は多言語対応がされておらず、英語の案内すらほとんどなかった。そのため、日本語を習熟していない人々には命に関わる情報が十分に届かず、逃げ遅れた人もいれば、避難所はどこか、水や食糧はどこに行けば手に入るのかと困り果てた人もいたという。「やさしい日本語」はこうした出来事を教訓に、「緊急時に安全を守るための情報を多くの人に伝える手段」としてはじまったものだ。
一方、庵先生のグループが約15年にわたって研究しているのは、緊急時というよりは日常のコミュニケーション手段としての「やさしい日本語」だという。庵先生は、日本に定住している外国人が日常生活の様々なシーンで情報を理解できないことにより、機会を逃していると指摘する。