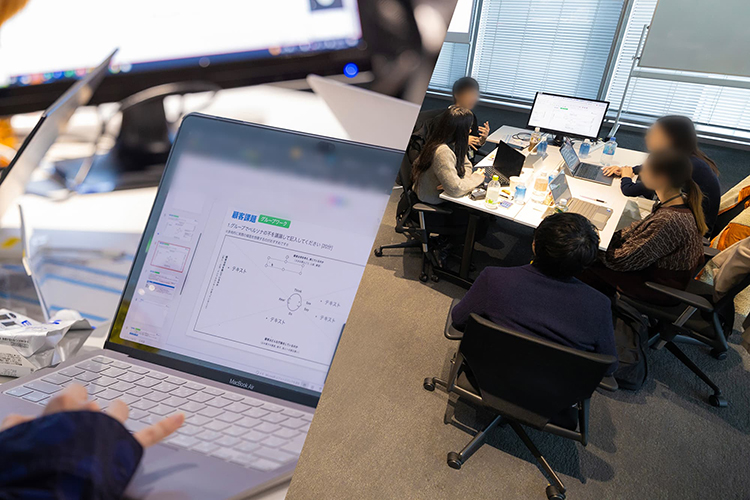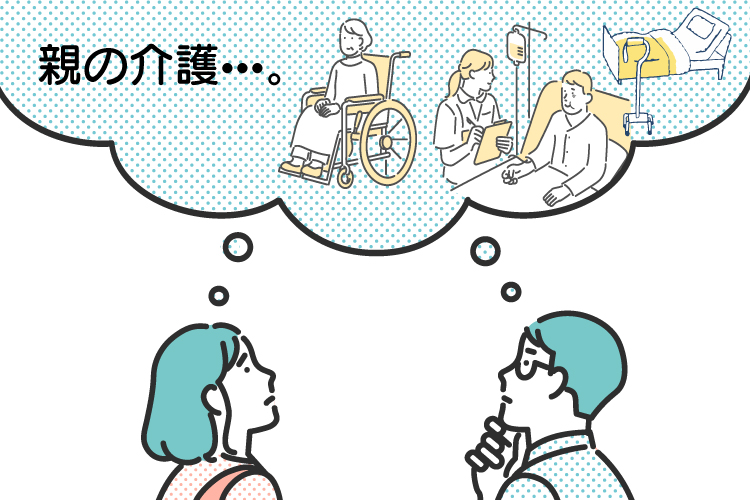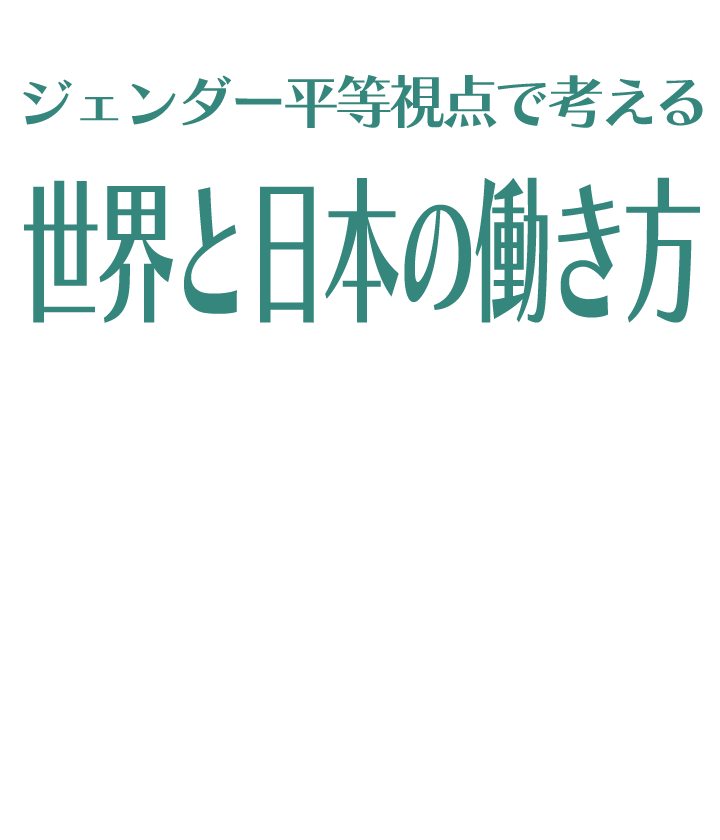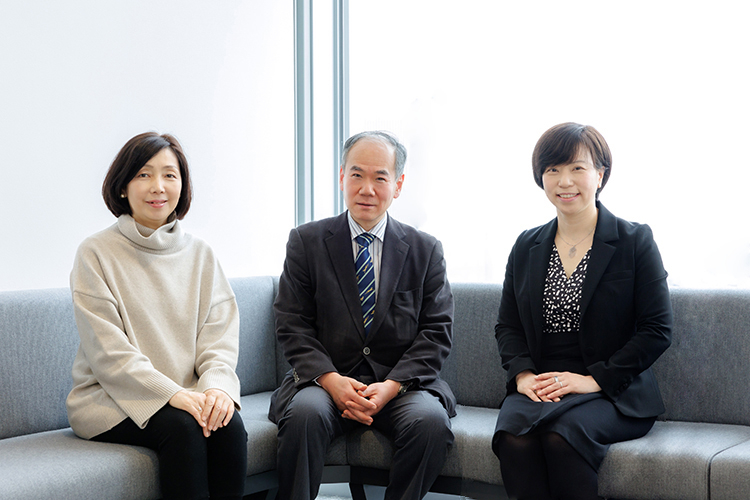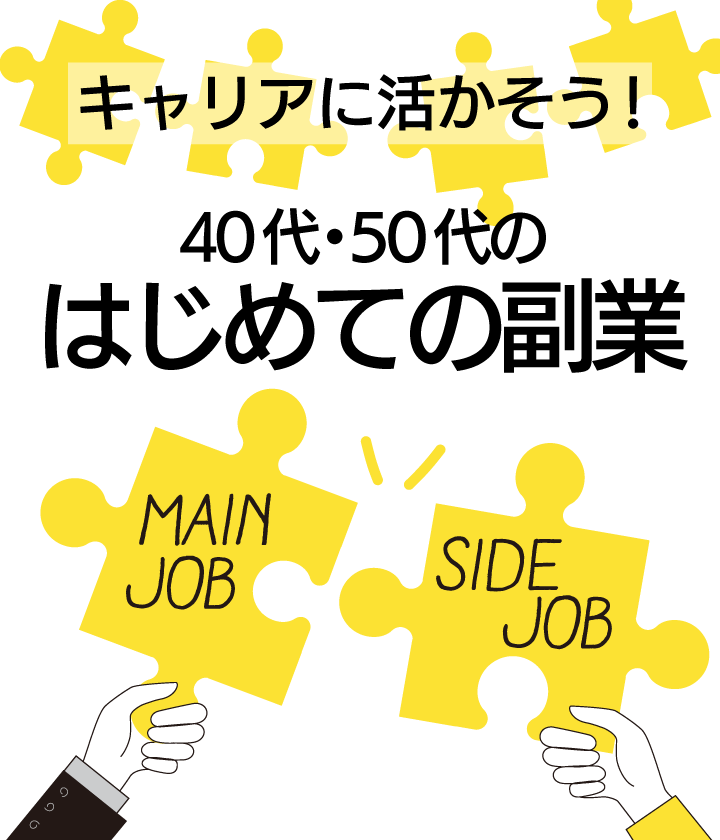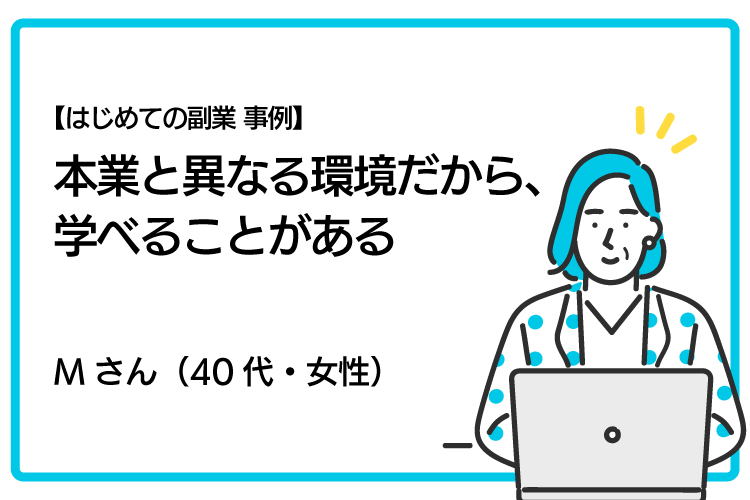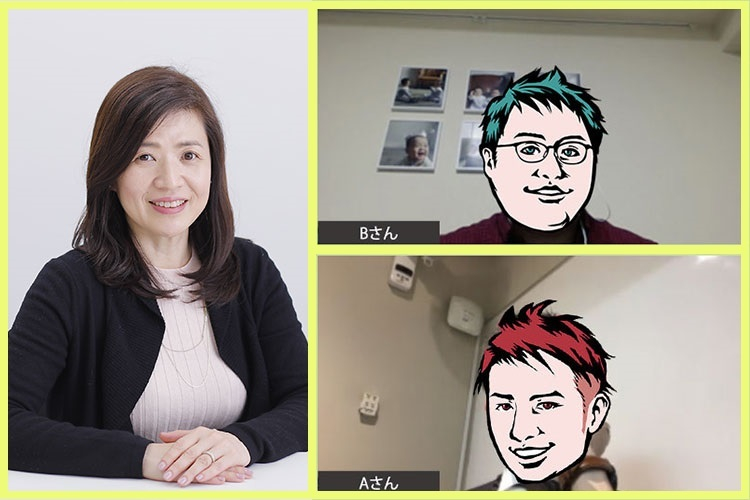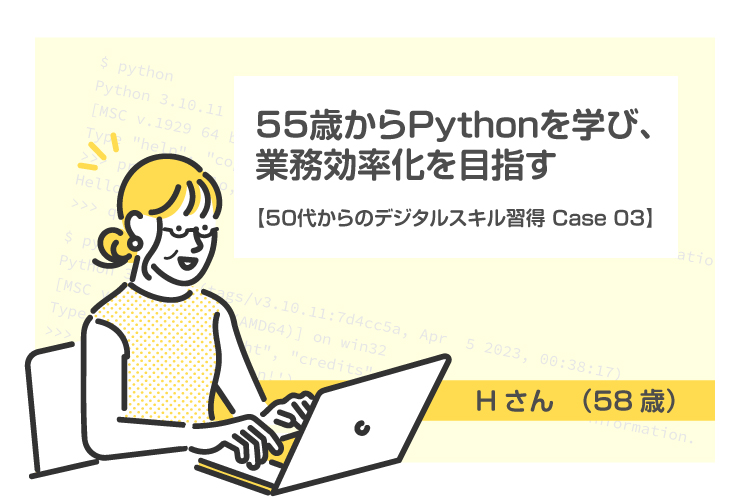行政機関が業務にチャットGPTを導入するなど、人の仕事を人工知能が担うケースは着実に増えている。代替が進んだとき、社会はどのような姿に変わるのか。そして人が幸福に働ける社会を作るためには、AIとどのように向き合えばいいのだろうか。「人工知能の哲学」を研究する東京大学大学院総合文化研究科の鈴木貴之教授と、リクルートワークス研究所の大嶋寧子主任研究員が、AIと労働の将来の姿について話し合った。
道具としてAIを捉え、人間が使い方をデザインする
大嶋:鈴木先生の専門である哲学に、人工知能がどのように関わってくるのかについて教えてください。
鈴木:私は心に関する理論的・原理的問題を考える「心の哲学」を研究しています。この領域では、人工知能研究が始まった1950年代から、人工知能には何ができて何ができないかということが議論されてきました。人工知能研究が究極的に目指すのは、計算や会話、運動などさまざまな能力を備えた、汎用で自律型の人工知能、つまり、SF映画に登場するような人工知能を作ることです。
現在、計算なら計算、チェスならチェスなど特定の課題に特化した高性能なAIはありますが、汎用性の高いAIの実現には、まだ高いハードルがあります。これまで、多くの哲学者は、汎用人工知能の実現可能性には否定的な立場を取ってきました。
大嶋:人間に近い姿を目指すほど「人とは何か」という問いに直面し、倫理的な問題も発生する。だからこそ哲学者は否定的なのでしょうし、実現するとしてもまだまだ時間がかかるだろうことは想像がつきます。一方、先生は人間らしい生き方や働き方をアシストするという「道具としてのAI」の持つ可能性を指摘しています。道具としてのAIと、汎用人工知能の本質的な違いはどこにありますか。
鈴木:汎用人工知能が一人の人間に置き換わることを目指すものなのに対して、道具としてのAIは、人間の足りない部分を補い、能力を拡張することを目指すものです。道具としてのAIが目指すのは、電卓を使うことで人間の計算能力を高めるのと同じように、AIを利用することで、人間のさまざまな能力を向上させたり、拡張させたりすることです。道具としてのAIと「何でもできる」汎用型AIとは目指す方向性が異なるので、両者の違いを区別し、道具としてのAIの開発に取り組んだ方が、少なくとも短期的には役立つし、活用の可能性も広がると考えています。