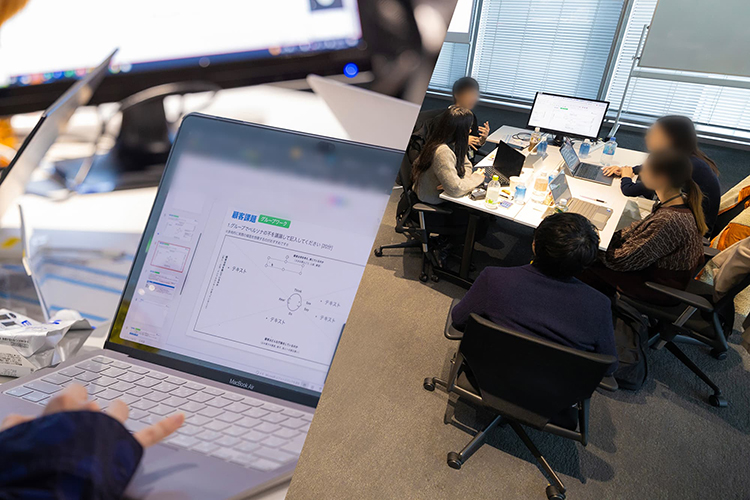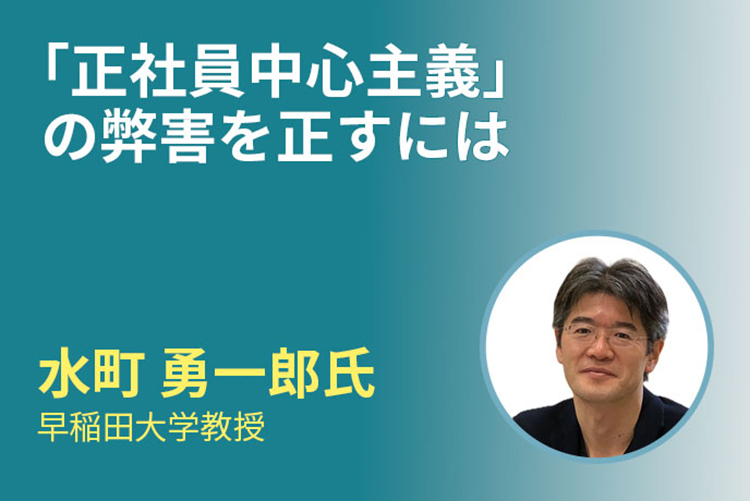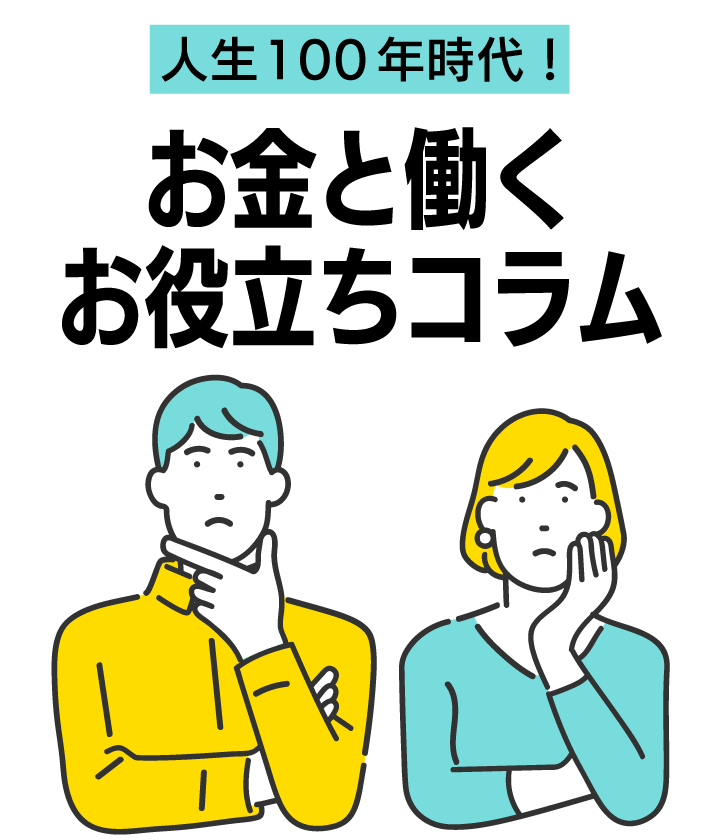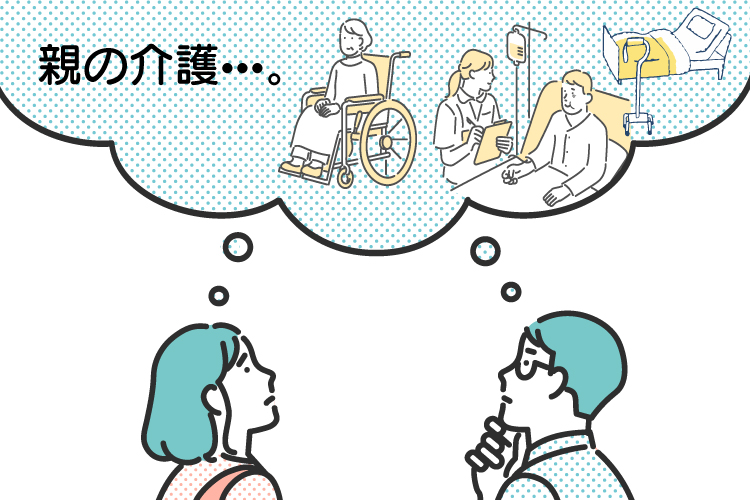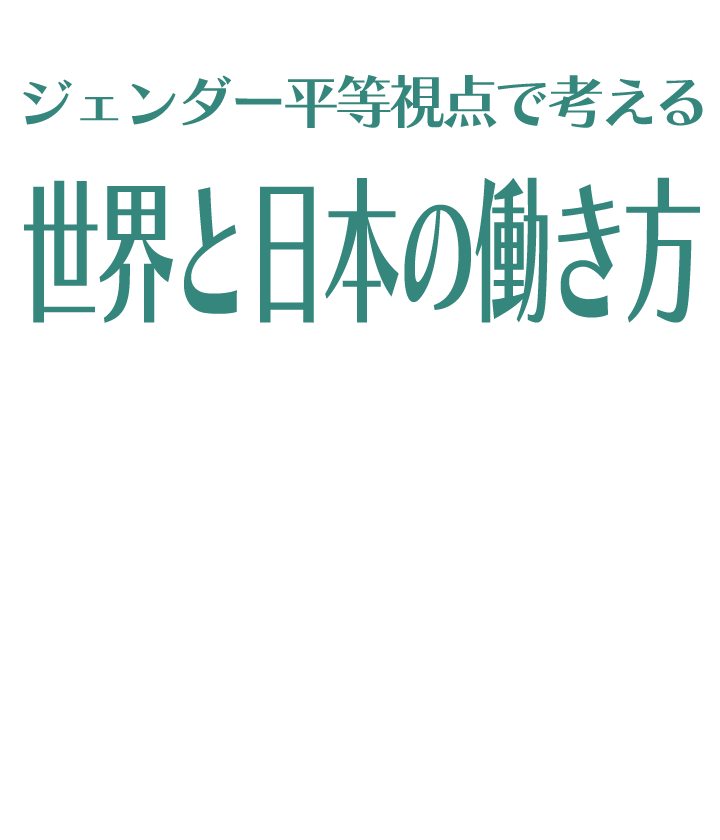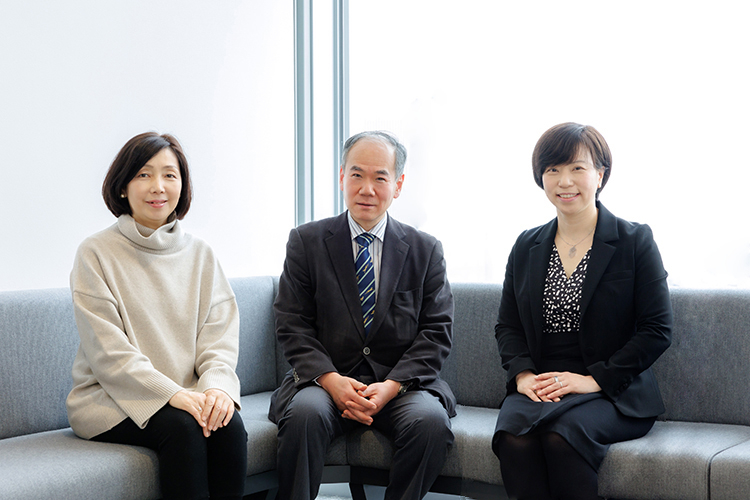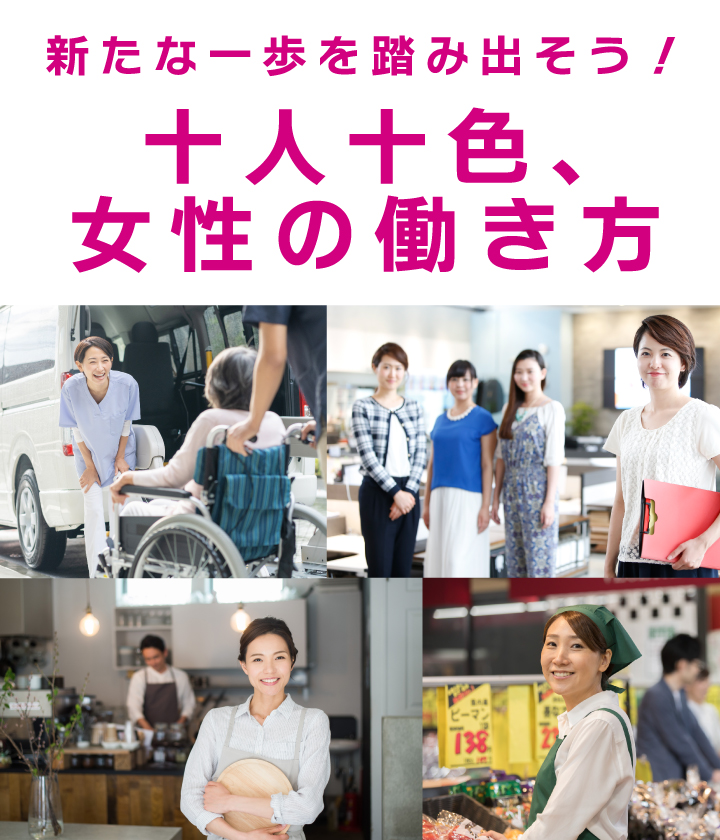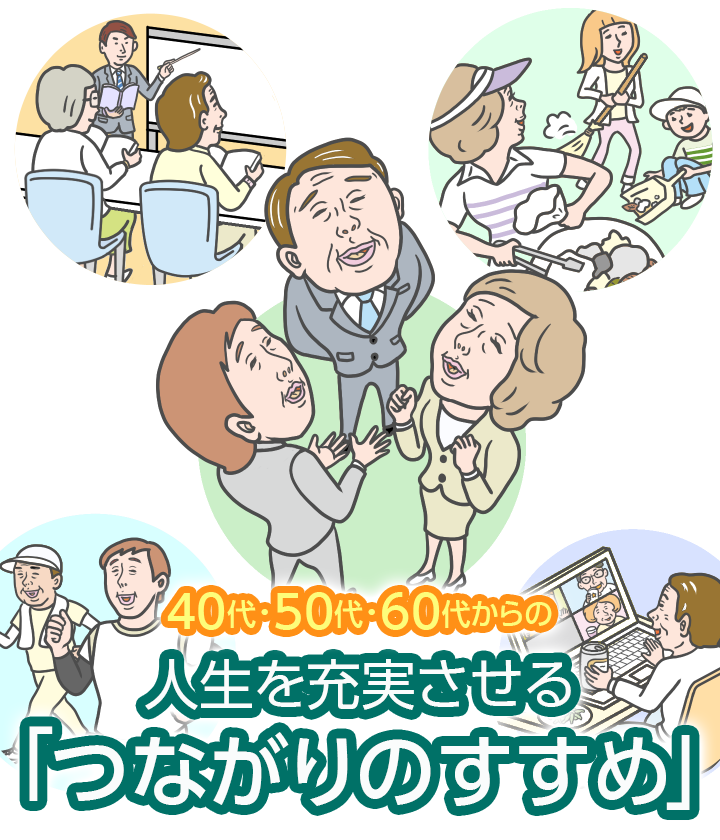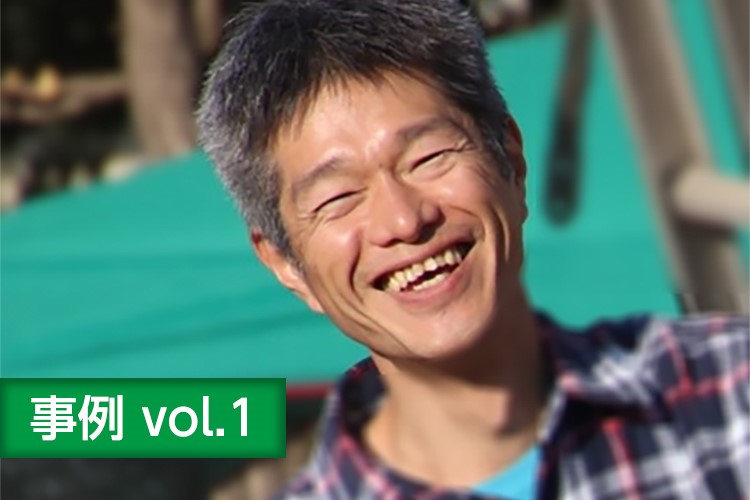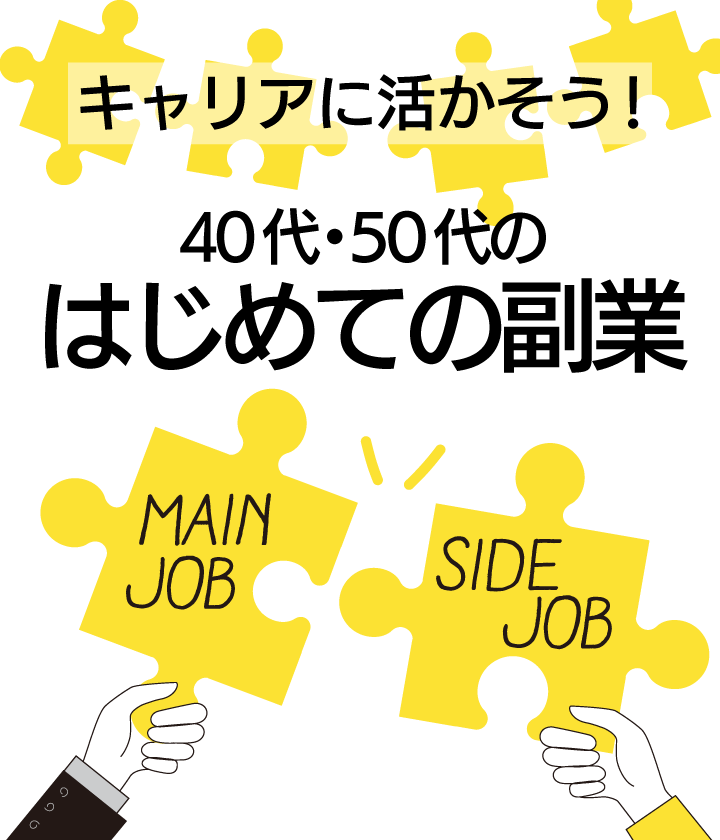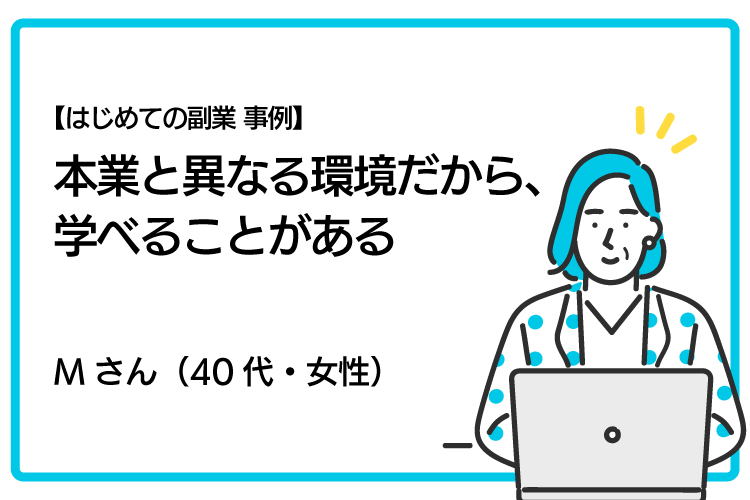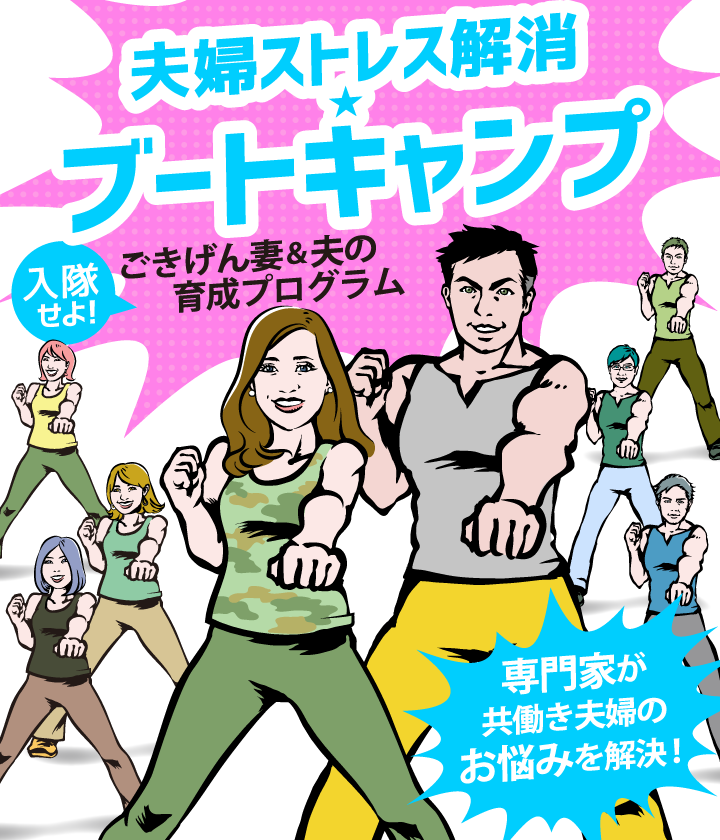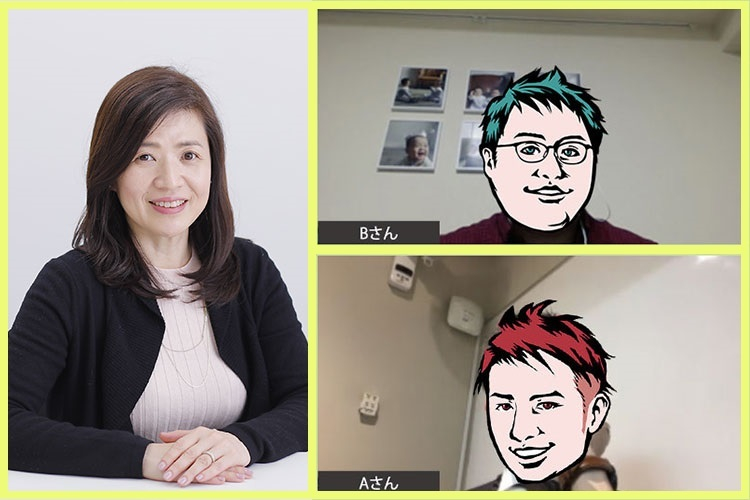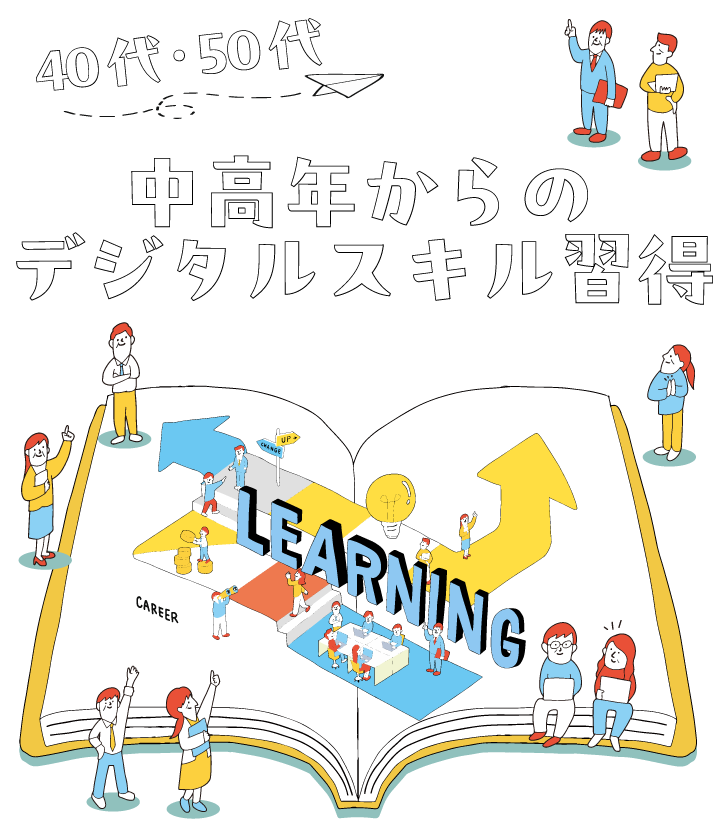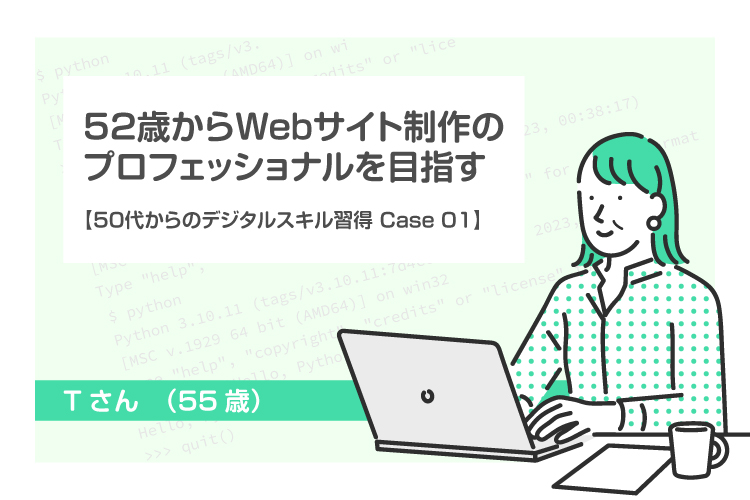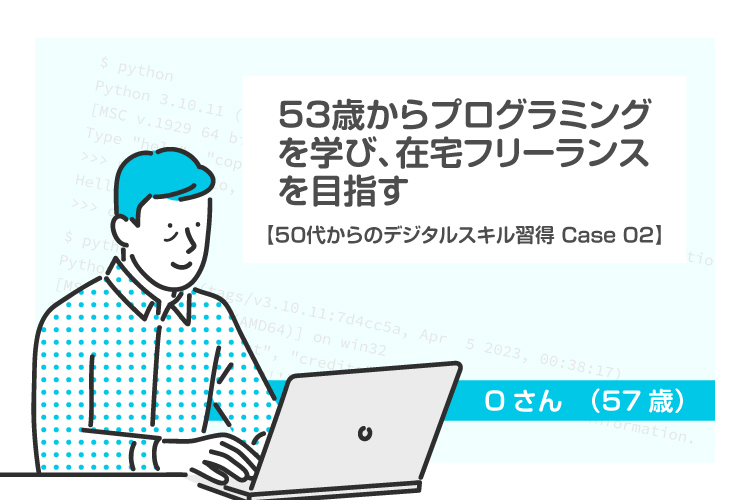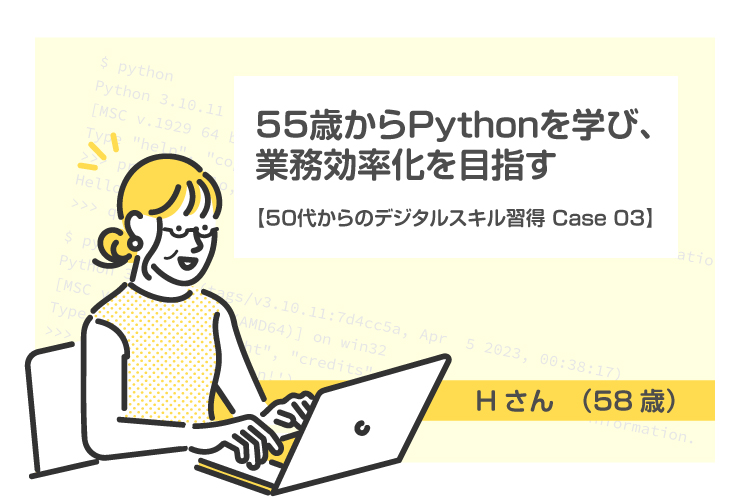近年、「働き方改革」により労働時間の削減に取り組む企業が増えています。しかしながら「労働時間が長くてつらい」と感じている人もまだまだ多いようです。「長時間労働」とは何時間くらいを指すのか、長時間労働にはどのようなリスクがあるのか、長時間労働の改善・防止策について、社会保険労務士・岡佳伸さんが解説します。
- 長時間労働の定義・目安の基準
- 長時間労働することで生じるリスクとは
- 長時間労働を避けるための対策
- 長時間労働を改善するために
長時間労働の定義・目安の基準
「そもそも「長時間労働」とは、どの程度の時間を指すのでしょうか。法律上の定義、目安となる基準を理解しておきましょう。
法定労働時間とは
法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間を指します。現行法では以下のように規定されています。
・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない
・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない
長時間労働とは何時間を指すのか
長時間労働の目安となる基準の一つが、「月80時間以上の時間外労働」です。時間外労働が80時間を超え、かつ本人が医師の面談を希望した場合、企業はその労働者に対して「産業医面談」を行うことが法律で義務付けられています。
もう一つの基準が「月100時間以上の時間外労働」です。労働基準法に基づく「36協定」では、時間外労働と休日労働の合計時間を月100時間未満及び年720時間未満とすることが定められています。つまり時間外労働が100時間以上になると法律違反となるのです。
なお、36協定に基づく時間外労働の上限は、「月45時間及び年間360時間まで」と定められています。「臨時的な特別な事情」がある場合には、「特別条項」を設ければ月45時間超の時間外労働が認められますが、それでも月45時間を超えてもよいとされるのは「年6回まで」です。
月45時間の時間外労働が3カ月連続で続いた場合、自己都合で退職したとしても「会社都合退職」(特定受給資格者)と見なされます。
目安となる「36協定」とは
「36協定」とは、時間外労働や休日労働について決めた協定のことで、正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。労働基準法第36条に基づくことから、一般的に36(サブロク)協定と呼ばれています。
先述のとおり、労働基準法において、労働時間は原則「1日8時間、1週40時間以内」、休日は「毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上の休日」と定められています。
この法定労働時間を超えて働く場合、「1日」「1カ月」「1年」の各期間に対する時間外労働の上限について、労働者と使用者との間で協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を締結しないまま残業や休日出勤をさせれば法律違反となります。