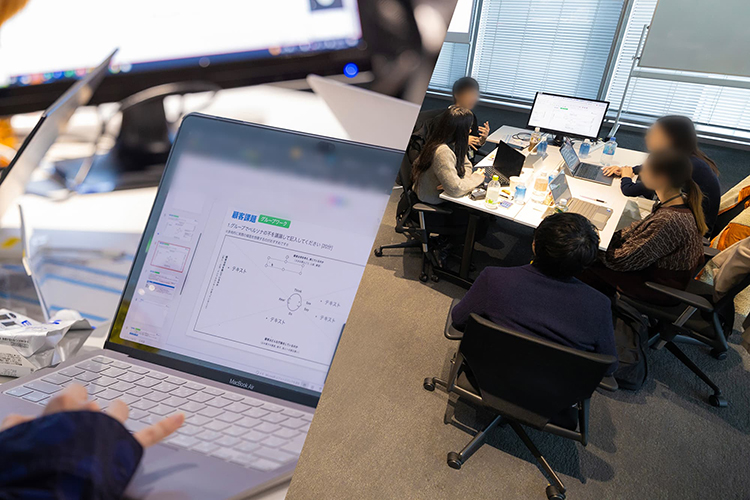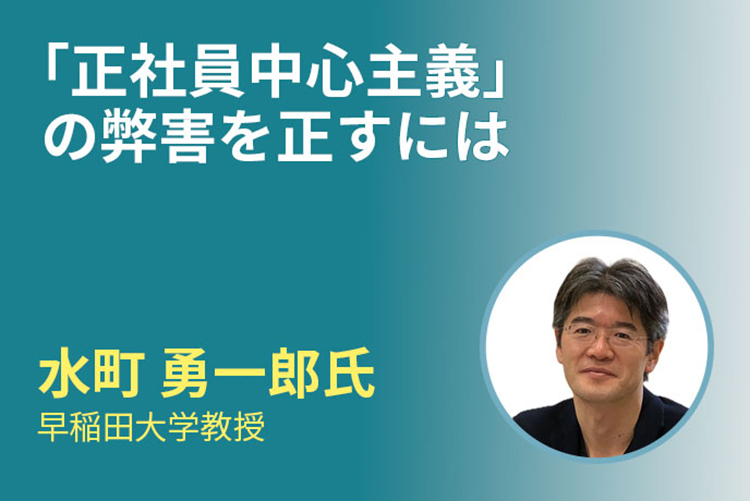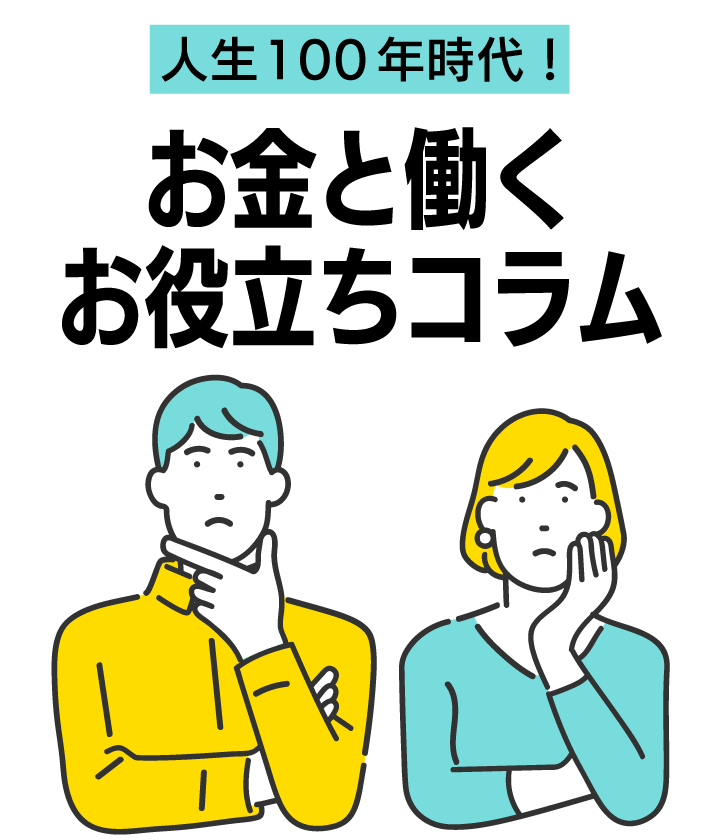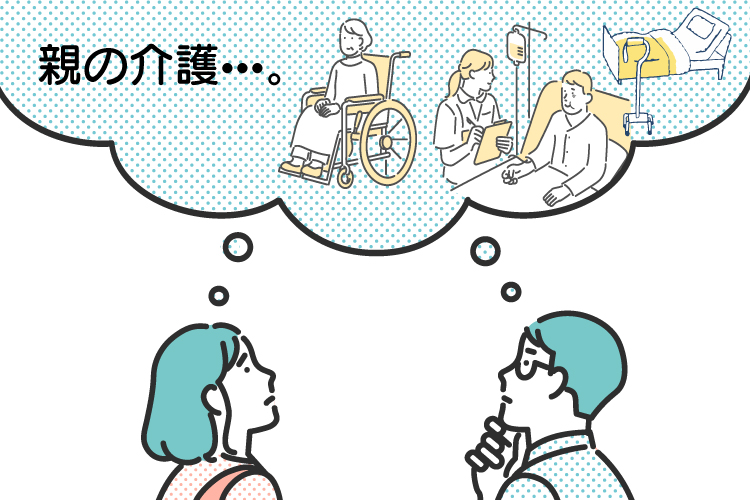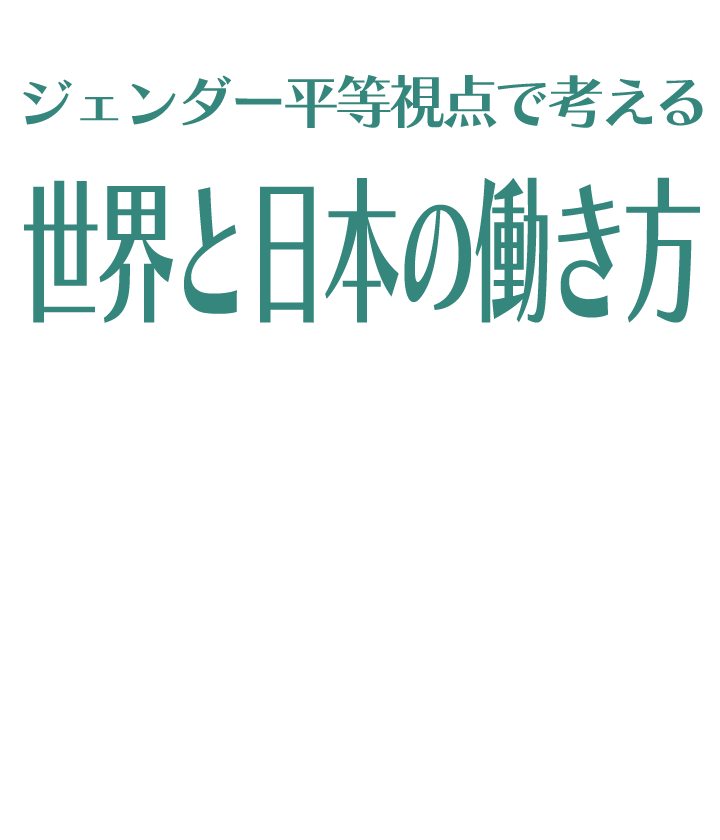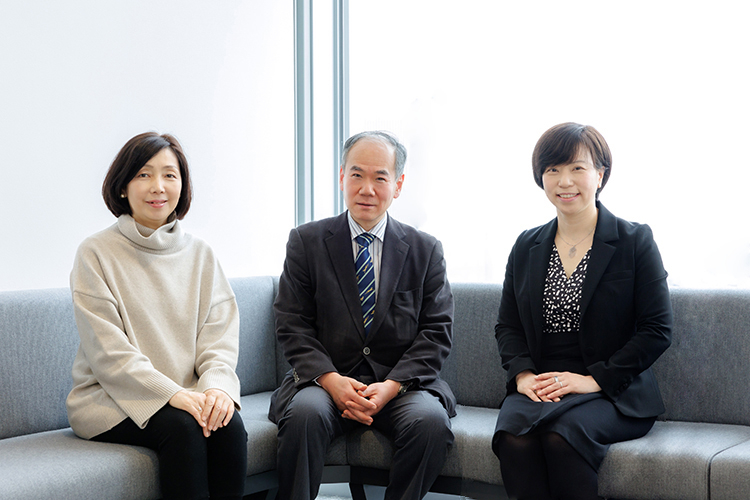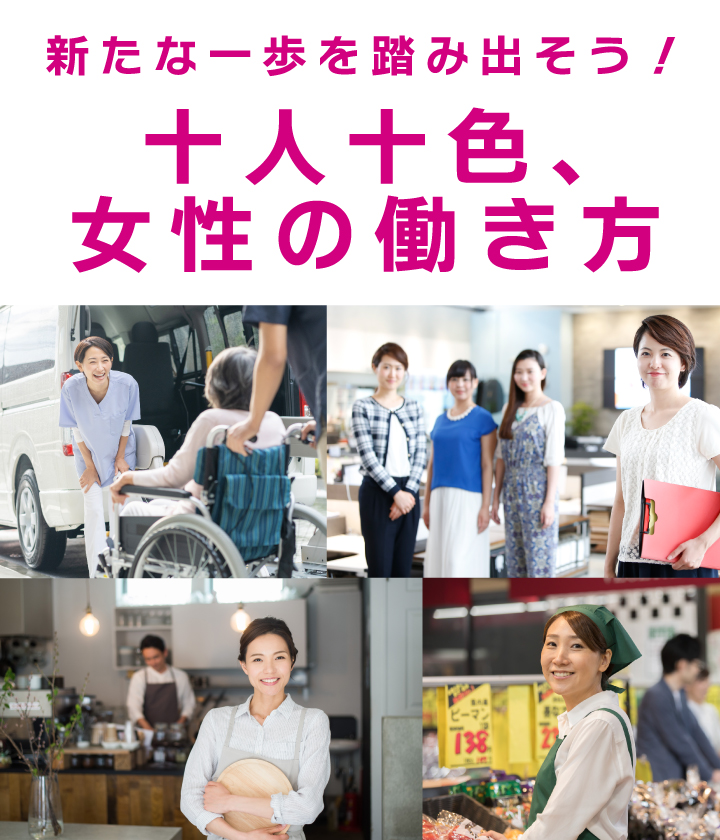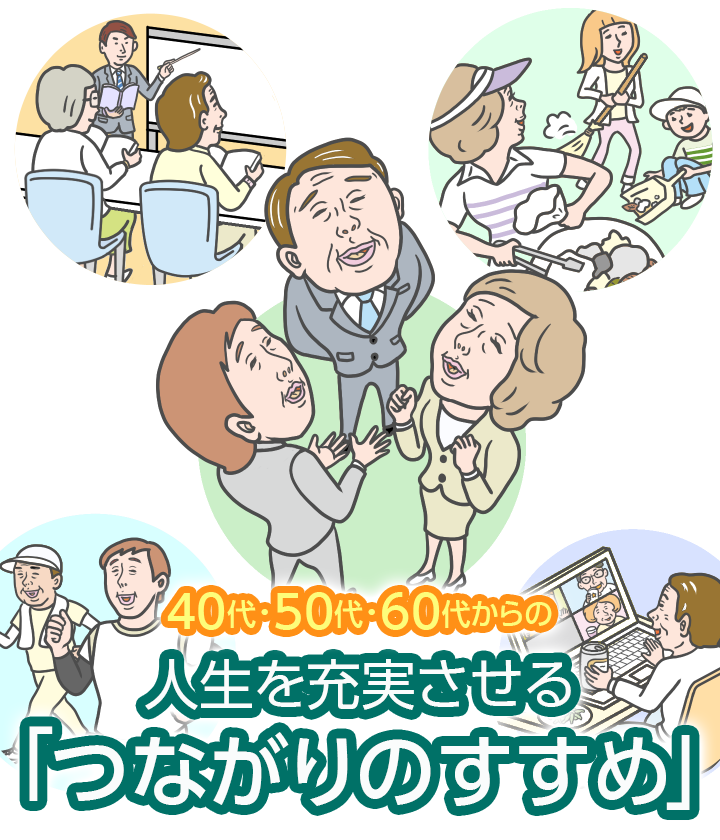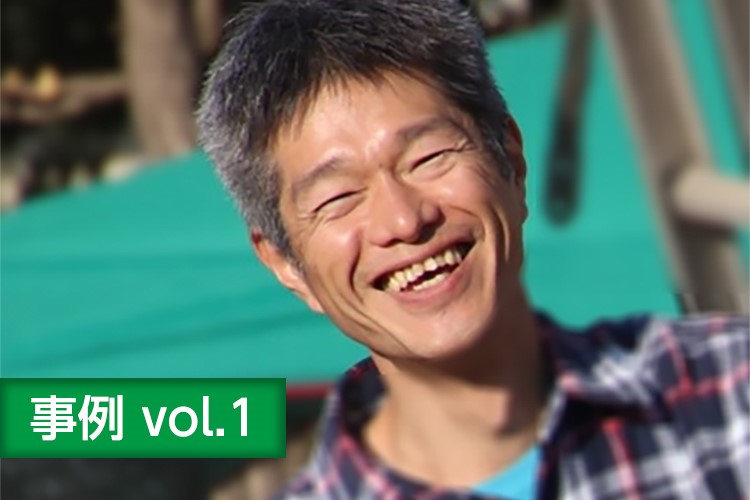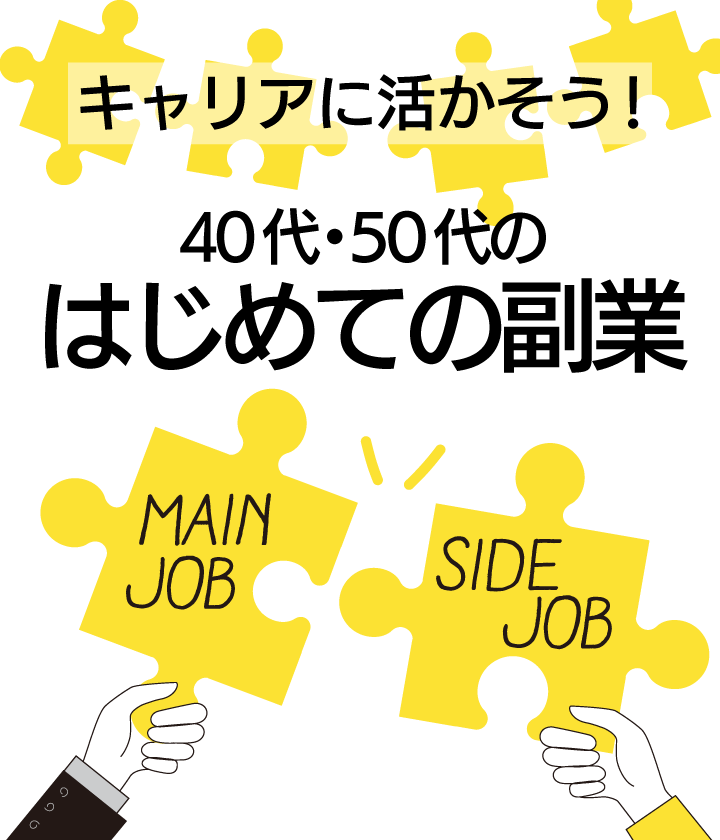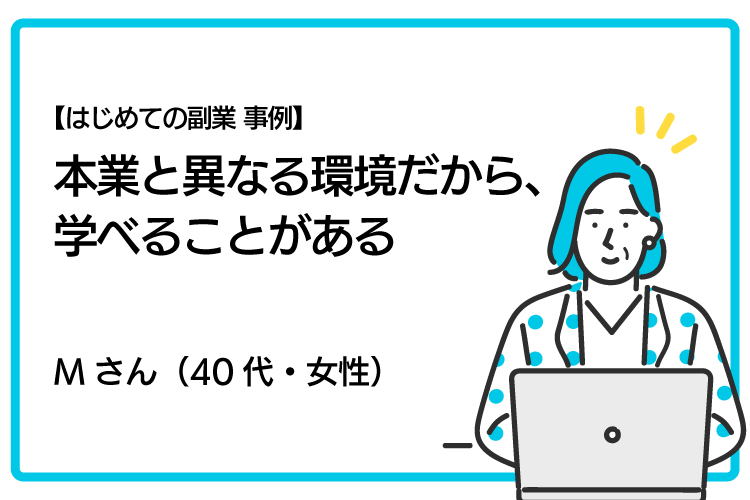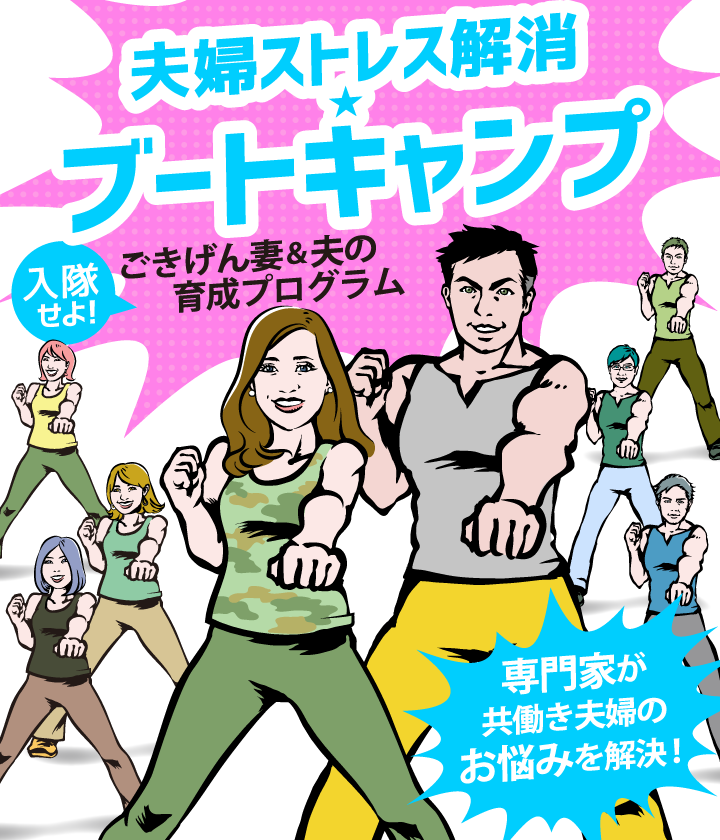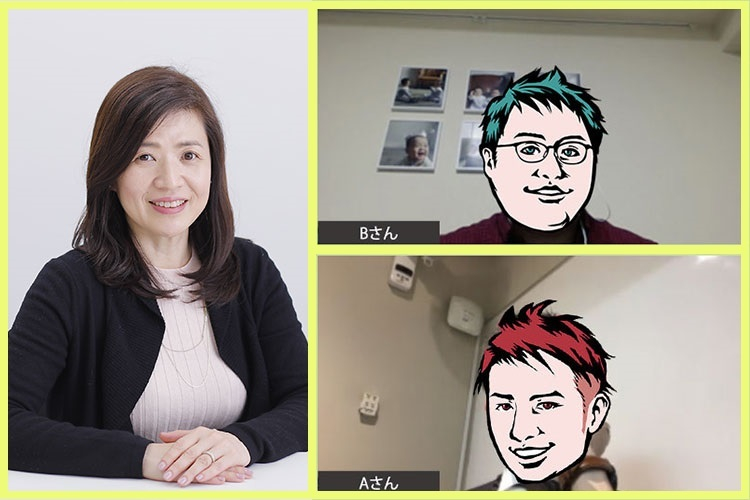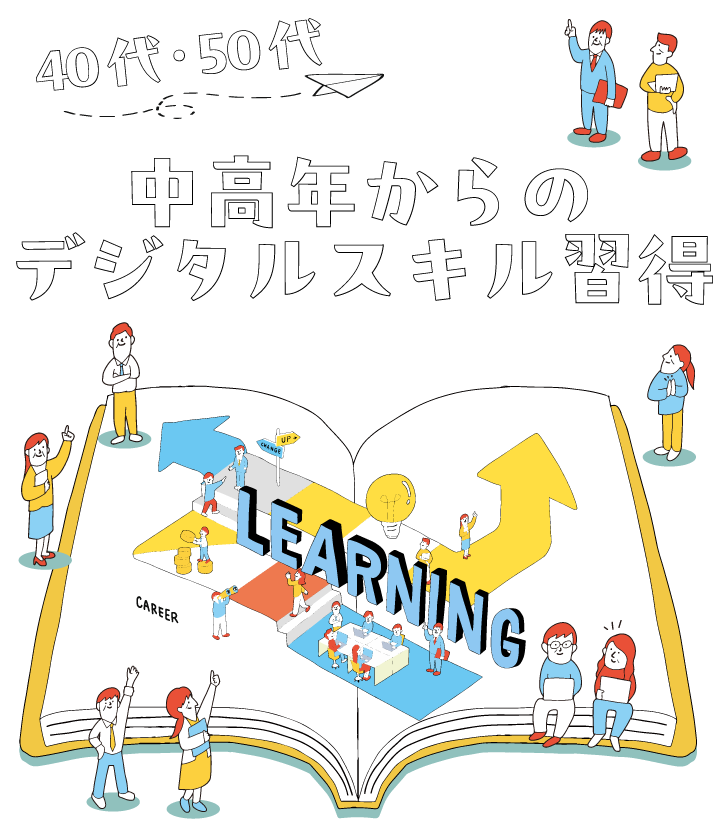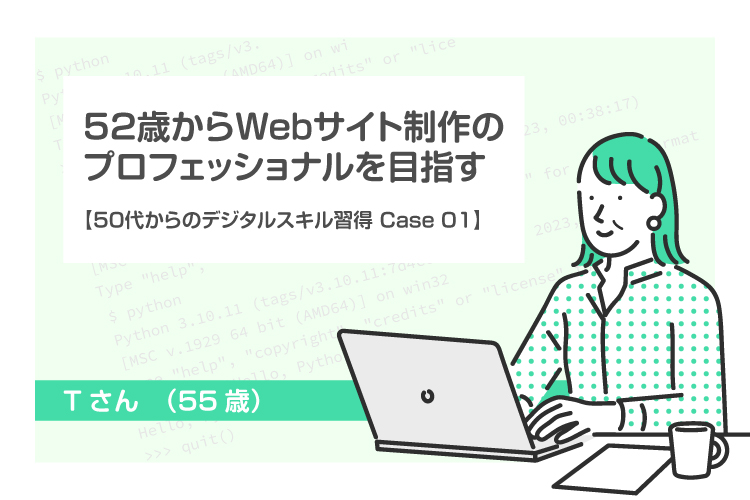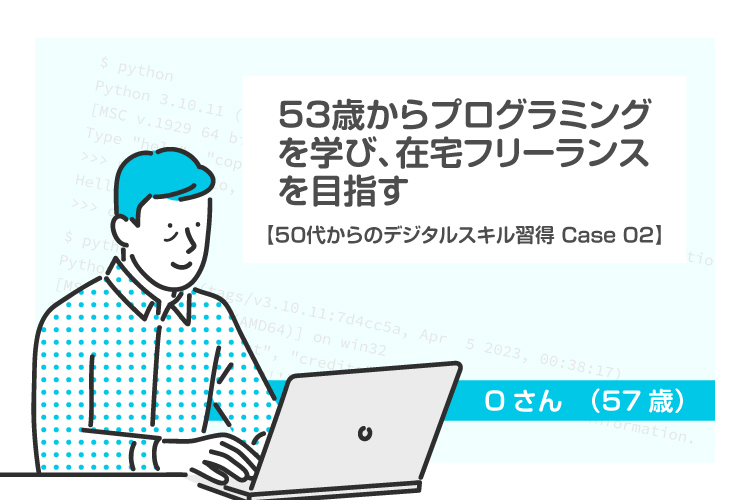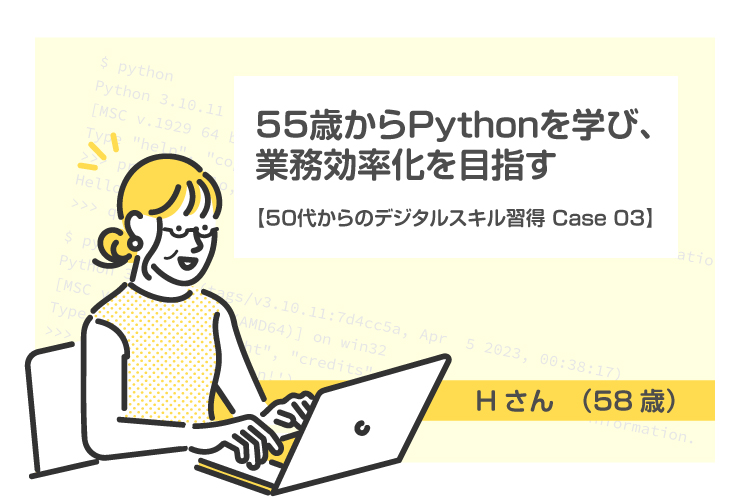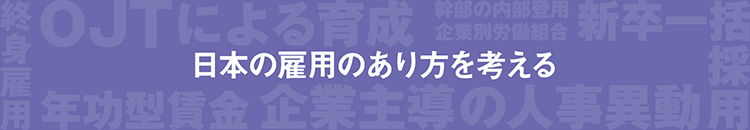
国際的に見た日本の生産性や経済成長率の低迷を背景として、他国を真似した人事制度の導入が盛んに議論されている。たとえば、日本(の会社)は長期雇用制度を維持してきたために、人材の流動性が低く非効率になっており、アメリカのように頻繁に解雇し中途人材を雇用するような人材の流動性が高い状態を目指すことで生産性が高まる、といった主張がなされることがある。このような、他国の「良いところ」を真似した人事制度改革はうまくいくのかについて、ここでは考えたい。
先に結論を述べてしまうと、特定の人事制度だけを真似して導入しようとしてもそれを軌道に乗せるのは難しいと考えられる。なぜならば、人事制度はその中の個別の制度の間で連動していることに加え、労働市場の形や、社会保障システムと絡み合って機能しているためである。これらは、各国の雇用社会が成立する中で出来上がった複合システムであり、一部を安易に変えることは難しい。人事制度はシステムの別の部分の特徴と連動していることが多く、ある制度を導入しようとすると、別の部分に問題が生じてしまうということがあり得る。といっても、具体例がないとイメージしづらいと思われるため、以降では日本の特徴と、それと比べたときの他国の特徴について、社会保障システムを軸に見ていきたい。人事制度それ自体や労働市場の形については、Global Career Survey 2024の多国間調査データを用いて検討したリクルートワークス研究所の2つの報告書や、本コラムの後に公開される有識者インタビューなどをお読みいただきたい(リクルートワークス研究所2024a、2024b)。
「標準世帯」と家族の支え合いを前提とした日本社会
今日の日本社会の雇用と社会保障の仕組みは、1960~1970年代に固まったとされる。そこでの社会保障システムの特徴として挙げられるのは、雇用者中心で、かつ性別役割分業を前提とした仕組みだということである(大沢2020)。つまり、会社、特に大企業に雇用されている男性と専業主婦の女性で構成される夫婦、そしてその子どもを含めた家族で居住する世帯、いわゆる「標準世帯」を主とした社会保障の仕組みをとってきた。具体的には、年金制度が20~59歳の全員が原則加入する国民年金と、企業等の雇用者(第2号被保険者)が加入する厚生年金の2階建ての仕組みであり、第2号被保険者に扶養される配偶者は自己負担なしで第3号被保険者となること、また、配偶者控除・配偶者特別控除によって夫婦のどちらか一方の年収が少ない場合に社会保険料や税負担が減額・免除されることなどが挙げられる。
このような「標準世帯」観とあいまって、社会保障への支出割合が国際的に見て低く、家族での支え合いを前提にしてきたことも、日本の社会保障システムの特徴だといえる。図表1は、国や自治体などが制度を通じて支出する社会支出額が国内総生産(GDP)に占める比率を国ごとに示したものである(※1)。ここで挙がっている国のうち、イギリスを除く4カ国よりも日本の方がこの比率が小さく、社会保障への支出が少ない様子がうかがえる。この裏にあるとされるのは、育児や介護をはじめとする福祉を家族が負担する構造である(宮本2008、エスピン=アンデルセン2001)。